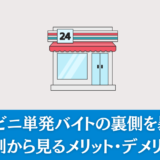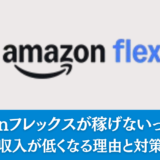近年学校に通えない、通わない子どもたちが増加しており、普通の学校に代わる教育の場が注目されています。フリースクールやオルタナティブ教育といった言葉を、最近見聞きしたことがある方も多いのではないでしょうか。
普通の学校ではない選択肢の一つとして、シュタイナー教育を実践する学校があります。ドイツで始まったシュタイナー教育は1970年代から日本に広がり始め、現在では10校以上のシュタイナー学校があります(2025年5月現在/日本シュタイナー学校協会HPを参考)。
シュタイナー学校では教育を総合芸術として捉え、詩や絵、歌などを通して子どもの心身の発達に合わせた教育を実践しています。その特徴的な教育方法は、一般的な学校のものとは大きく異なっているようです。
今回は、関西で初めてのシュタイナー学校である「京田辺シュタイナー学校」の内海真理子先生に、教育内容や学校の運営、シュタイナー教育を受ける子どもたちなどについてお話を伺いました。最後にイベントのご案内もありますので、オルタナティブ教育に興味のある方はぜひご覧ください。
(記事公開日:2025年5月9日)
子どもの成長に伴わない教育に疑問
――まずは内海先生ご自身についてお聞かせください。京田辺シュタイナー学校には、勤められて何年になるのですか。
京田辺シュタイナー学校の教員としては、開校からなので今年で25年になりますが、さらにその前身である「土曜クラス」の時から関わっているので実際はもう少し長い関係になります。土曜クラスとは毎週土曜日に開いていたシュタイナー教育を実践する教室で、全日制のシュタイナー学校を作る準備段階でした。保護者や教員が集まって運営しており、そこから数年かけて京田辺シュタイナー学校を立ち上げました。土地探しや資金集めなど本当に1から関わり、保護者と一緒になって学校を創ったんですよ。

そもそもシュタイナー教育に関わるようになったきっかけは、中高一貫校の教員だった時に感じた子どもたちの成長の面白さと、それに対して変化しない学校への疑問でした。中高一貫校なので中学1年生から高校3年生までを見ることができるのですが、この6年間の間に子どもたちはすごく変化していきます。その子どもたちの変化が、私にはとっても面白く思えました。でも校則は子どもたちに合わせて変わることなく、6年間同じです。私はだんだんそのことに難しさや矛盾を感じるようになりました。中学1〜2年生にとっては矛盾のなかったルールも、中学3年生〜高校生になるにつれて納得できなくなってくるなと。そんなときにシュタイナー教育に触れ、子どもの成長段階に合わせて教育の方針を変えていく考え方にとても共感を覚えたんです。
シュタイナー教育が面白いな、もっと知りたいなと思うようになりましたが、当時関西にはシュタイナー学校がありませんでした。そこでシュタイナー教育に関心を持っている先生たちで、シュタイナー教育を学校現場にどう活かせるか議論する研究会を始めました。その研究会で小学校から高校までの教員が一緒になって話をしていると、自分が所属していない学校段階の子どもたちへの意識がすごく薄いことに気が付きました。私の場合だと中学1年生以降の子どものことはよくわかっていましたが、小学校6年間をどういう風に過ごしていたのか、そうしたところへの意識があまり無かったんです。逆に小学校の先生も、子どもたちが中学生になったら急に反抗的になったり荒れたりするのを見て、「中学の教員が何か間違っているのではないか」とお思いのようでした。
こうして交流しなければ小学校1年生から高校3年生までという大きな視野で子どもたちを見ることがなかなかできず、自分が見ていない段階の子どもたちについて考えることもあまりありませんでした。この研究会に参加して、より広い視野、長いスパンで子どもたちを見ることの大切さを知りましたね。どんな風に子どもたちがこれまで育ってきて、今そこからどのように変化しているのかを知ろうとすることが大事だなと。
このときに学んだことは、現在のシュタイナー学校での教育実践にもとても役に立っています。

8年生までと9年生からでガラッと教育を変える
――一般には小学校6年、中学校3年、高校3年と学校を分けていることにも矛盾を覚えていらっしゃったのですね。シュタイナー教育では、基本的にどのような教育課程になっているのですか。
まずシュタイナー学校には、1年生(小学校1年生)から12年生(高校3年生)までの12年学年があります。1年生から8年生(中学2年生)までを1つの成長段階と考えており、基本的にはその8年間同じ担任が受け持とうとしています。9年生(中学3年生)からは子どもの発達状態がそれまでとは大きく異なると考えられているため、教育方針もガラッと変えます。この変化を非常に大切にしています。
1年生から8年生までは生きていく上での基本的なこと、たとえば生活リズムなどをちゃんと身につけていけるように教えます。社会には大人がきちんと決めたルールがあって、そのルールを守ることで成長していく側面もあると考えているからです。
しかし9年生から12年生では、これまで学んだ基礎を元に自分で進んでいく力を身につける段階となります。これまでは大人によってある程度守られていましたが、そこから飛び出して自分の力を伸ばしていきます。8年生までに大人の価値観を理解し、知った上で自分はどうしていくのか。それを試していく段階です。もちろん失敗もたくさんしますが、まだ学校や親に守られている状態ではあるので、むしろその間に失敗をしてもらえたらと考えています。また、親や教員にとっては子どもを心から信頼して「これからは彼らが何かをやろうとする内側からの力を育ててあげよう」と見守る段階でもあります。
したがって、保護者にも大きな変化を求めます。それまで大切に想って接してきた子どもから少し手を離すようなものですから、親にとっても試練となります。

保護者も学校運営を担う
――シュタイナー教育では学校と保護者が共に教育を行うことが大切なのですね。
はい。特に京田辺シュタイナー学校はもともと保護者が中心となって設立された学校ですので、現在の運営にも保護者が大きく関わっています。ですから子どものことや教育のこと以外のことでも、普段から教員と話し合いを重ねています。普通の学校に勤めていた時ですと面談の時くらいしか教員と保護者が顔を合わせる機会がありませんでしたが、本校では月に2回、土曜日に隔週で運営会議を行いますので、しょっちゅう保護者と関わります。クラスは12年間変わりませんし、保護者同士もよく顔を合わせて話し合うので、みんなが深い関係になっていきます。教員や保護者が、ひとつのチームとなって子どもを育てていくような感覚ですね。もちろん普通に揉め事などもありますが「一緒に子育てをしていこう」という考えは共有していると思います。
先程8年間は担任が変わらないと申しましたが、すなわち8年間ずっと同じ保護者、同じ先生が付き合うということなので、最初は互いに覚悟が要ります。ただみんなが子どもたちのためを想っているので、それで色々なことを乗り越えていけるのだと思います。
「この学校は親にとっても学びの場なんだ」「子どもだけでなく、自分も学び、成長しました」と仰る保護者も多いですね。

1年生から12年生が共に過ごす学校
――もちろん子どもたちも長い間を共に過ごすと思うのですが、子どもたち同士はどのように関わり合っているのですか。
一学年20〜25人ほどなのですが、やはり長くて12年間を一緒に過ごすわけなので、兄弟のような関係になりますね。
異年齢間の交流も盛んです。1年生の教室の隣が12年生の教室なのですが、低学年の子たちはお兄さんやお姉さんのことが大好きで、また上級生の方もよく遊んでくれます。12年生の男の子が小さい子を両腕にぶら下げて歩いている姿なんかは、本当に微笑ましいですね。
低学年の子どもたちは身近に上級生を見て育つので、何年生になったらあんなことができる、高等部になったらあんなことができる、と憧れを持ちながら大きくなります。

――身近に年の離れたお手本がいる環境は、子どもたちにとって良い影響を与えそうですね。ところで子どもたちはみんな家から通っているのですか。
そうです。京田辺シュタイナー学校では特に小さい間は学校に歩いて通うことが理想的だと考えているので、家が遠い場合には引っ越してもらうこともあります。関東には大きなシュタイナー学校が3つありますが、西日本では本校が初めてなので、遠方から本校に通うために引っ越して来られる方も多いです。
普通の学校ではなく京田辺シュタイナー学校に通うことを決めるのは、基本的に保護者です。入学は保護者と学校の面談で決定します。中高生の編入の場合は本人がどう思っているかも聴きますが、保護者がシュタイナー教育を実践している学校づくりに参加したい、子どもにシュタイナー教育を受けさせたいという場合が多いですね。
学校を辞める子も時にはいます。家庭の事情で辞める場合が多いですが、高等部では他にやりたいことができ、それを実現するために違う道を選びたいためというケースもあります。
成長段階に合わせた教育

――普通の学校とは考え方や教育課程など、色々な部分がかなり違うのですね。授業内容もやはり異なるのですか。
そうですね。シュタイナー学校では子どもたちの成長段階に合わせて教育内容を変えていきます。
たとえば歴史の授業では、最初は古代の神話などから、当たり前に神様の存在が信じられ尊ばれていて、神様と人とをつなぐと考えられていた祭司や王様の存在に矛盾がなかった時代。そんな時代の人間の意識に触れることから始まります。5年生ぐらいの子どもたちはまだそのような意識に近いからです。
7年生(中学校1年生)になり、思春期を迎えて反発が始まるころには、ルネッサンス期を学びます。権力者に言われた通りに物事を信じていた時代から、自分たちで航海に出て世界を知っていく時代へ。例えばガリレオが天体を観測して、地動説を唱えたのは意識の大転換ですよね。
昔ながらの権威にすごく反発し始める8年生になると、ルネッサンスを経て人々が国や教会に疑問を持つようになり、それまでの体制を倒した市民革命や宗教改革について学びます。
このように、子どもたちの成長段階とちょうど一致するように、学ぶ内容を組み立てていきます。人間のありようの変化を、より共感・理解しやすいようにという意図からこのようなカリキュラムになっているんです。
また、通常の学校のような定期考査や点数評価もありません。学年末にそれぞれの成果と課題が表現された、文章と詩による通信簿を一人一人の子どもに贈ります。他者との比較ではなく自分が学んだことや取り組んだことが「自分でどれくらいできたか」で評価をされるので、みんな人と違って当たり前という感覚が育つのかなと思います。
指導法も子どもたちの発達に合わせています。低学年の子たちへの指導は幼児教育の方法と地続きです。保育園連盟の先生方が視察に来られた時に「小学校の壁がなく、感銘を受けた」と仰っていました。幼稚園や保育園から小学校に上がると、環境や教育が違いすぎて馴染めない「小学校の壁」があるという話はよく聞きますが、シュタイナー学校では低学年の子たちにより馴染みやすいような授業をしています。
逆に高等部では大学教育にも近い指導が行われます。卒業プロジェクトでは自分で決めたテーマを1年半ほどかけて研究するのですが、その発表会に外部評価委員としてお呼びした大学教授の方が「大学の卒業論文にも負けない面白さがある」と感心しておられました。
このように、成長段階に応じて変化していくような教育を行っています。
卒業プロジェクトや卒業演劇を通して自分と向き合う

――普通の学校とかなり違う教育を実践されていますが、卒業したら大学などに進学する子もいるのですか。
自分のやりたいことが大学での学びにあるならば大学に行く子もいますし、専門学校での学びにあれば専門学校に行く子もいます。ただ、なかなか卒業してすぐにやりたいことはわからないので、ギャップイヤーを設ける子も多いですね。学歴ではなく自分が何をやりたいかで進路を決めるので、大学に行ける学力があってもまず働いてみることを選ぶ子もいます。過去にはまずは農業をやってみようという子もいました。
大学に行く場合は、基本的に浪人して行ってください、と伝えています。なぜなら12年生の間は卒業プロジェクトと卒業演劇で大忙しなんです。とても受験勉強ができる環境ではありませんし、学校としても卒プロや卒業演劇を優先してほしいと考えています。
卒プロや卒業演劇を通して、自分自身や12年間を共に過ごした友人たちともう一度深いところで向き合い、出会い直す体験が本当に大切だと思っているからです。18歳という時に「自分とはどういう人間か」を考えることが、これからの長い人生を生きていく上での礎となると思っています。
それでも大学に行きたい、行くには勉強が必要だと自分で思えば、卒プロや卒業演劇に取り組む中で時間を見つけてやっているようです。浪人をして有名私立大学や国公立大学に行く子もいますし、たまに浪人せずに行く子もいますので、本当にそれぞれですね。卒プロでの研究が推薦入試で評価されることもあり、シュタイナー学校での学びや研究がそのまま進路につながることもあります。
こんなふうに自分のやりたいことを軸にして進路を選んでいくので、大多数の人が社会の流れに流されて進路を決めることに違和感を覚える卒業生も多いようです。

卒業生の話を直接聞けるシンポジウムを開催
――シュタイナー教育を受けた卒業生の方々が、それぞれどのような道を歩んでいくのか、とても気になりますね。
それぞれが違っていいということを前提に、その中で自分はどうあるのかを考える力を身につけられる。そんな場であろうと、京田辺シュタイナー学校は25年間頑張ってきました。
ここで積み上げてきた友人関係や世界とのつながりから、自分が生きる世界や自分自身への信頼感が生まれてきます。この信頼感が今の社会を生きていく上でとても大切だと思います。不安に支配されずに「大丈夫、なんとかなる」そんなふうに思えることは本当に力になりますから。
今年で開校から25年が経ち、卒業生も300人を超えました。それを記念して、5月17日土曜日に「卒業生シンポジウム」を開催します。「今という時代を自由に生きる」をテーマに、社会に向き合って活躍する卒業生たちが話をしてくれます。シュタイナー教育に興味のある方、シュタイナー学校にお子さんを通わせたいと考えている方など、関心のある方はぜひお越しください。事前申込制となっていますので、詳しくはHPをご覧くださいね。
――内海先生、この度は貴重なお話をいただき、ありがとうございました。