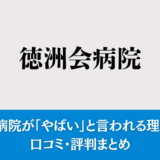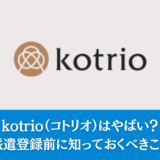本州の最北端、青森県。太平洋と日本海の両方に面しているため、地域によって気候が異なり、風土や言葉もさまざまだと言われています。白神山地や恐山、十和田湖など豊かな自然もある一方、県庁所在地である青森市は空港やフェリー、新幹線などの交通インフラが整った地方都市でもあります。
今回のインタビュイー、磯野咲さんは、そんな青森で「移住促進」をミッションに地域おこし協力隊員として活動し、退任後の現在はフリーの編集者及び青森市移住コーディネーターとして活躍しています。「訛ったまま喋っていいですか」と津軽アクセントで話してくださった磯野さんからは並々ならぬ地元への愛郷心を感じますが、そんな青森の魅力は「得体の知れなさ」だと語ります。いったいそれはどういうことなのか、これまでの磯野さんの経歴をたどりながら、お話を伺いました。
青森県で生まれ育ち、東京からUターン
――ではまず、磯野さんのこれまでについてお聞きしたいと思います。青森県のどちらのご出身でいらっしゃるのですか。
中泊町の小泊地区というところで高校生まで暮らしていました。青森市まで車で2時間ぐらいかかる田舎町です。
高校卒業後は秋田の短大に進学しました。大学は美術系で、イラストレーターやフォトショップなどを使って製作をしていました。そこからまた青森に一度戻ってきて、事務系の職に就きました。でもやっぱり制作関係の仕事に就きたいなと思って、上京して占いアプリの運営会社に就職して。そしてさらにもうちょっと自分で作ることをしたいなという想いが強くなって、未経験から編集プロダクションに飛び込んで、数年間働いていました。
6年弱程新宿で暮らしていたんですけど、元々青森に帰りたいと思っていたこともあって、タイミングが重なりUターンすることに決めました。

――ご自身の移住の記録をnoteにもまとめて発信していらっしゃって、同じように移住を考えている方にはすごく参考になるなと思って拝見しました。青森に帰ってからは地域おこし協力隊に着任したんですよね。
はい。2022年7月から、青森市地域おこし協力隊として移住促進業務に取り組んでいました。主にワーケーションや移住体験のアテンドなどを担当していたんですけど、東京で移住イベントがあればスタッフとして参加したり、青森市に移住した方の交流会を開催したりもしていました。
自主企画として2度フリーペーパーの発行もしました。編集の経験を活かして、青森駅周辺の雑貨店をまとめた「AOMORIものづくりMAP」や青森の人と文化にスポットを当てた「青森ふぁん通信」というフリーペーパーを作りました。「青森ふぁん通信」では、私がお世話になった方々に取材をさせてもらったんですけど、本当に皆さん楽しそうに活動をしている方ばかりで。いろんな土地にいろんな面白い方がいると思うんですけど、「青森市にもいるよ!」と、紹介したい一心で作りました。
協力隊の任期を終えた今は、引き続き移住コーディネーターとして働きつつ、フリーで編集や記事執筆の仕事をしています。
――青森ふぁん通信の表紙がすごくいいですよね。顔がイラストで4人分描かれていて、その内3人がおじさんというのが。この世の中でおじさんは結構肩身が狭いですからね。
はい、協力隊の時にお世話になった方々を紹介しました。すごい技を持っていたり、熱意を持って地元のために何かしていたり、本当に好きなことを自分のためにやり続けていたり。


現役の青森市地域おこし協力隊と
なんだかよく分からない、けど面白い
――noteでも繰り返し「青森の良さや魅力を色々な人に届けたい」と書いていらっしゃいますが、磯野さんは青森の良さはどのようなところにあると考えておられますか。
青森は、「なんだかよく分からない得体の知れなさ」が魅力だなと思っています。どういうことかというと、青森って県外の人からするとよく分からないところなのかなと感じることがあって。あまり生活や文化について想像がつかないというか。たとえばワ―ケーションツアーの参加者から「雪が降るとインターネットって繋がらなくなりますか、荷物届かなくなりますか」なんていう質問をいただいたことがあるんです。そういうちょっとした生活のこともなかなか想像しにくいんだろうなと。青森というとリンゴとかねぶたとかはすぐ出てくると思うんですけど、それ以外ってなんだかよく分からない。そういうよく分からない感じが逆に青森の面白さなのかなと思ってますね。
私はラジオが好きなんですけど、「安住紳一郎の日曜天国」という番組を聴いていたら、安住さんが「忍者とかって得体の知れない怖さあるよね」みたいなことを話していて、「得体の知れないものの良さ」ってあるよなと気付いて。青森もそういう部分があるんじゃないかなと考えています。
よくよく考えるとキリストの墓や縄文遺跡があったり、津軽弁が難解だったり、各地でいろんなお祭りがあったりして、さらに全貌がつかめない感じがします。でもそこがいいんですよね。
よく分からないから、みなさん旅行先としては青森を飛ばして北海道まで行かれてしまいますけどね。



――地域の魅力というと、具体的な産物や文化に焦点を当てがちですが、「よく分からない」ことこそが魅力という観点は面白いですね。磯野さんは秋田や東京で暮らした経験がおありですが、他の土地に比べて青森という場所にはどのような感覚を覚えますか。
私としてはやはり愛着がありますね。なんでも「青森県産」って書いてあると買おうと思うし。あとは方言が話せるのが良いです。津軽弁が私にとって一番馴染みのある言葉なので、感情を表現しやすいんですよ。最近はもっと方言を使いこなしたいと思っていて。私も訛っていない方なんですが、高校生とか若い子はさらに訛っていないので、勿体ないなと思っています。訛ってるおじいちゃんおばあちゃんの言葉を聞くと面白いんです。あんなふうに訛りたいので、もっと津軽弁を使っていきたいですね。
あと、今住んでいる青森市は中泊に比べれば都会なので、あんまり個人が目立たないところが良いなと思っています。田舎だと良くも悪くも目立ってしまうので。東京でも感じていたんですけど、青森市も程よい埋没感があっていいなと思っています。

移住コーディネーターからフリーランスへ
――そんな青森市で移住コーディネーターとして活動されていますが、実際に移住してくる方々にはどのような人が多いですか。
Uターンがかなり多いんですよ。私は今、青森市の連携推進課から委託を受けて移住体験やワーケーションの対応をしているんですけど、直接の体験者よりは、自分や家族が青森出身だとか、それぞれのタイミングや理由があって戻ってきている方が多い印象です。地域おこし協力隊にはIターンが多いんですけどね。関西や埼玉、関東から来ている人がいます。
私としてはもっと色々な方が「青森っていいな、行ってみたいな」と思ってくれるような情報を発信していけたらいいなと思っています。
――そうなんですね。磯野さんは現在、移住コーディネーターの他にフリーランスで編集業もしていらっしゃるとのことですが、具体的にはどのようなお仕事をされているのですか。
元々繋がりのあった方から紹介していただく感じで、ちょっとずつ取材の仕事をしたり、雑誌の記事を書かせてもらったりしています。今受けているようなインタビューをすることもあります。あとは青森経済新聞というWeb媒体でニュース記事を書くことも。編集業はリモートがメインなので、県内に限らずお仕事があれば受けています。
これからはフリーランスとしての仕事ももっと増やしていきたいなと思っているところです。「青森ふぁん通信」のようなフリーペーパーもまた作りたいですし。前回までは青森市の協力隊として作っていたので青森市がメインでしたけど、今度は青森県全域を対象に作ってみたいですね。また、青森での暮らしも続けつつ、今後は東京都の2拠点生活をしてみたいな…なんて考えているところです。
――地元が好きでUターンし、「得体の知れない」青森の魅力を静かに面白がる姿勢がとても新鮮でした。今回はありがとうございました。