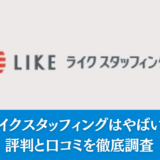かつてのように終身雇用や年功序列が当たり前ではなくなった今、働き方が流動的になっています。その選択肢の一つとして、2022年に新しく施行された「労働者協同組合法」に基づく法人、「労働者協同組合」が注目されています。
今回の記事では、元公務員の3人が設立した労働者協同組合「やさしいまちづくり総合研究所」に関するお話を通して、この新しい法人形態の魅力と可能性に迫ります。労働者全員が出資し、共に経営し、働く――そんな「全員参加型」の働き方は、どのように“やさしいまち”を育んでいけるのでしょうか。

やさしいまちづくり総合研究所
中西 大輔さん
代表理事。元滋賀県職員。
前神 有里さん
常務理事・主席研究員。元愛媛県職員。
加藤 翔大さん
理事・主任研究員。元総務省職員。
「労働者協同組合」とは
―まずは、やさしいまちづくり総合研究所(以下、やさまち総研)の事業内容を教えてください。
加藤さん:
「働く」という視点を大切に、広く「地域づくり」や「ひとづくり」などに関する講座やセミナー、研修等の企画・提供を行い、「ひと」と「地域」を繋ぐ実践を応援しています。また、私たちの法人形態である「労働者協同組合」や「協同労働」をテーマとした講演等も実施しています。例えば昨年度は、市町村職員の方を対象に「地域づくりを仕事にする新しい働き方」というテーマのセミナーが厚生労働省の主催で実施されたのですが、その際のパネルディスカッションの司会やコメンテーターを務め、当法人の設立や取組みについてお伝えしました。
―やさまち総研の法人形態「労働者協同組合」が一体何なのかご存知ない方も多いと思うのですが、どのような組織なのか簡単に教えていただけますか?
中西さん:
世の中には株式会社やNPO法人など、様々な種類の法人がありますが、「労働者協同組合」も法人形態の一つです。例えば株式会社や合同会社は、会社法によって設立や運営等のルールが定められていますが、それと同じように、労働者協同組合(労協)は2022年に施行された労働者協同組合法(以下、「労協法」)によって規定されます。
日本では労協法の成立・施行が比較的最近のことなので、まだそこまで認知が広がっていませんが、労働者協同組合、英語では「ワーカー・コーポレイティブ」ですが、その仕組み自体の歴史は古く、興りは19世紀ヨーロッパとされています。日本においても同法の施行以降、全国各地で労協が組織されるようになり、2025年4月時点では、144団体が設立されています。
労働者協同組合という法人は、労協法第一条に定められる通り「多様な就労の機会の創出」および「持続可能で活力ある地域社会の実現」に資することを目的とした法人です。更に、労協には三つの基本原理があります。
- 組合員が出資すること
- その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
- 組合員が組合の行う事業に従事すること
これは株式会社やNPO法人にはない、労働者協同組合ならではの基本原理であり、この原理に従って、法人の目的である、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行います。
出資して全員が経営に携わるから、お金だけ出す人もいないし、ただ単に雇われて賃労働する人もいない。全員がフラットに、経営にも労働にも出資にも参加するというのが大きな特長だと思います。
―私自身は労働者協同組合がどのような組織なのか詳しくお話を伺うのは今回が初めてなのですが、この法人形態の一番の良さというのは、労働者自らに決定権があるということなのでしょうか?
中西さん:
そうですね。自分に合った働き方をみんなで話し合って決められるというのはとても大きいと思います。現在の労働市場で弾かれてしまうような人たちも、ちゃんと自分の意志で働くことができるというのが、私は労働者協同組合の一番の魅力だと思っています。
滋賀県で県庁職員として働いていたとき、介護保険関係の仕事も色々経験したのですが、「しんどさを抱えた人を置き去りにしたようなまちづくりっておかしいよね」という話を前神さんともよくしていました。
前神さん:
私も愛媛県庁の職員時代は「生きづらさを抱えた人を置き去りにしない地域づくり」を強く意識していました。というのも、福祉制度に関わる者として常々感じていたのが、現行の福祉制度が持つ「全員を救うことはできない」という暗黙の前提。全員を救うことは土台できないのだから、「本当に困っている人」だけ最低限助けます、みたいなのがすごく嫌だったんです。「本当に困っている人」っていうスティグマ(※差別・偏見)も含めて。
そこへきて更に、自分自身が身内の介護でにっちもさっちもいかなくなって、離職せざるを得なくなりました。私自身が労働市場から弾かれたわけです。
今でこそ、転職が当たり前になったり、多様な働き方が許容されつつありますけど、私が介護離職をした当時は公務員を辞めたり転職したりする人って全然いなかったんです。
―そんな呼ばれ方をされるくらい、当時は働き方の多様性も柔軟性もなかったということですね…。
前神さん:
私らの世代は「公務員は潰しが利かない」なんて吹き込まれて育ったので、「公務員の世界の中で勝ち続けないと生きていけない」と思い詰めてしまう職員も多かったですよ。心が疲れてしまったとしても、休職したらもう戻れないって。
そんなことや、自分自身が労働市場から弾かれた経験も、やさまち総研の法人形態として労働者協同組合を選んだ理由の一つになっているかもしれません。働き方を、例えば障害者の方も、就労A型、B型とかの画一的な「制度」に割り振られることなく、自分のやりたい働き方で働くことができる場を作れるのが、労協という法人形態ならではだと思うんです。
労協については私も以前からなんとなく知ってはいましたけど、「理想は分かる、でも自分ではやらんな」って思っていました。でも、2022年に労協法ができたことで色んなことがクリアになったし、実際に全国に色んな形の労働者協同組合ができ始めて、その事例をみているうちに、この法人形態の意義や良さが自分の中で腑に落ち始めたんです。タイミングも良かったですね。

「全員の意見を反映させる」という縛りの利点
―お三方は、元公務員という共通点以外は、年齢もバラバラ、女性も男性もいて、住まいもバラバラなんですね。
中西さん:
そうなんです。バラバラで、フラットだから面白いんですよね。意見なんか、合わないときは恐ろしく合いません。というか、合わないのがほとんどかも(笑)
でも、その合わない意見を話し合いで決めていかなくちゃいけない。この法人形態を選んだ以上、そこを超えていかなくてはならないんです。なぜならそれが法律で義務付けられているから。だから、延々と話していくわけなんですが、そうしているうちにどこかで妥協点が見つかるというか、納得できる部分が出てくるんです。合わない意見の先にあるものが見えてくると、何かこう新しいものが生まれてきそうなワクワク感があるんですよね。
加藤さん:
「組織運営に全員の意見を反映させること」が法律で義務付けられている法人は他にありません。声の大きい人の意見が通りがちとか、たくさん出資している人の意見ばかりが反映されるという構図ではなく、出資額の多寡にかかわらず、一人一票しかない議決権の行使を通じて、全員の意見を反映させて組織を運営していく必要があります。
象徴的に例えれば、一般の株式会社で社長の給料を社員が決めることはできませんが、労協であればそれも全員で話し合って決めることができる。それをメリットと捉えるかデメリットと捉えるかは主観的なところですが、今までの賃労働ではできなかった選択肢が広がったことは大きなメリットだと言えると思います。
経済合理性・効率性重視の視点では、意思決定に時間のかかる「意見反映」や、出資配当ができないことはデメリットと捉えられますが、逆に、経済合理性や効率性を第一に求めない「働き方」、つまり民主的で誰もが自分に合った働き方ができるところに魅力を感じる人にとっては、デメリットとしてあげた点も逆にメリットとして感じられるのではないかと思いますね。

やさまち総研誕生の経緯
―やさまち総研の事業についてもう少し詳しく伺いたいと思います。事業内容である地域づくりに関するセミナーや講座は、場所を問わずに行っているのですか?
前神さん:
オンライン開催もありますし、場所は色々です。私たちの事務所のある愛媛県伊予市でやることもあれば、中西さんのフィールドである滋賀でやったこともあります。
私はやさまち総研の活動と並行してフリーランスとしても活動しているので、あちこち呼んでいただいた先で何かするということもあります。複業がうまく組み合わさっているんです。「好きな仕事を、好きな時間に、好きな場所でできる」っていうのを実践している感じですね。
―それはとても魅力的です。一方で、活動時間の計上など複雑になりそうだとも感じたのですが、そのあたりはいかがですか?
前神さん:
そこは大事なポイントで、労働者協同組合は従事分量配当制なので、誰がどの仕事にどれだけ従事したかを見える化しておく必要があります。まして3人ともバラバラの場所にいて、それぞれにやさまち総研とは別の仕事に従事してもいるので。
なのでそこは、「ダンクソフト」というIT企業さんにサポートしていただいて、私たちが使いやすい、私たちの組織に適した形でのデジタル化を行いました。ダンクソフトさんにとっても、労働者協同組合という新しい組織に合ったソフトウェアを検討する良い機会でもあったようで、win-winというよりgive&giveの協業ができたことも良かったです。
今win-winと言いましたけど、この言葉って、どっちが勝ち・どっちが負けっていう発想じゃないですか。行政の世界にも「自治体間競争」なんて言葉がありますけど、私はそういう価値観はもう嫌なんですよね。大事なのは、私たちがここでどう生きていきたいか、どう未来を作っていけるかってことだと思うんです。今の若い人たちもどちらかというとそういう発想で、教え合ったり共有し合ったりしながら、その次を作っていこうとする、やさしい関係性がだいぶ生まれてきているように感じます。
―お三方には「元公務員」という共通項がありますが、この3人で「やさしいまちづくり総合研究所」を設立されたのには、どのような経緯があったんでしょうか?
前神さん:
私と中西さんの出会いは2008年まで遡るんですが、「地域に飛び出す公務員ネットワーク」という集まりを通じて知り合いました。これは全国の公務員が繋がって、「私たちが一歩動けば社会が変わる」というコンセプトのもと、色々な活動をしていました。SNSがまだない時代なので、メーリングリストでやり取りしていたんですが、そのメーリングリストでめっちゃいいこと書いている人がいる!と思って、会いに出かけていったのが中西さんとの出会いです。
加藤君は総務省から愛媛県庁に出向していて、私の隣の課だったんですが、「地域に飛び出す公務員ネットワーク」のイベントにも一緒に参加していました。出向が終わって総務省に戻ってからもゆるく繋がってはいたので、しばらくして彼が総務省辞めたと聞いて、一緒にやってみない?と誘ってみたところ、引き受けてもらえました。

自治を考え、働いた経験があってこそ
―世代は違えど、志は同じくするお三方ということですね。
中西さん:
私や前神さんの世代は、「自治って何?」ということを公務員としてものすごく考えた世代です。というのも、2000年に施行された「地方分権一括法」という法律によって、それまでは国、県、市町村と縦の流れで物事を考えていたところが、法律上、国も県も市町村も横並びで対等の関係になったんです。この変化は当時は相当大きなものでした。条例という自分たちの地域の「法律」も自分たちで作るし、自分たちの町をこうしていくという計画も自分たちで作る。そして自分たちで実践する。国・県・市町村が対等の関係になるという変化の真っ只中で、「自治とは何か」をものすごく考え、そして試行錯誤の中で実践してきたという原体験が、今のやさしいまちづくり総合研究所にも通底していると思います。
前神さん:
自慢じゃないけど、私たち県職員時代、つまり働き手としての成長期、全然寝てないんですよ(笑)24時間起きてたと言っても過言でないくらい。
なんでかって言ったら、現場に行ってたから。例えばケアマネの方がこういうことがしんどいとか、こんな目に遭って大変だとか、そういう現場の声を聞きに行っていたんです。私たち県職員の役目は、そういう困りごとを「仕組み」で変えることができないか、県の事業として何とかできないかを考えることにあると思っていたので。
中西さん:
私もALSの患者さんの、深夜の訪問看護に同行していた時期があるんですが、ALS患者さんが現実にこういう暮らし方をしていて、更にそれを支える人がいるという現場を実際に目の当たりにしたことで、自分の「まちづくり」に対するイメージ、もっと言えば仕事観や人生観も大きく変わりました。なんというか、今まで自分が携わってきた「街を盛り上げていこうぜ!」的なノリの施策が空虚というか、チャラいことやってたなと。それが決して悪いわけではないのですが、さっき前神さんが言ったような「現場」の声を置き去りにしてまちを盛り上げることなんてできないということに改めて気づかされました。
現場の声を聞くということで言うと、そういうことをしていたのは、私たち県職員だけでなく官僚の方も何人もいました。霞が関でそれこそ何日も徹夜しているような多忙を極める方でも、土日とかに自分の時間を使って現場に来てくれて、現場の人らと一緒にお酒飲みながら夜通し語ってくれたりするんですよ。その語り合いの場から政策が生まれていく。そういう瞬間を目の当たりにした経験も、「自治」や「まちづくり」を考え実行していく上での私たちの原体験になっていると思います。
やさまち総研と地域のこれから

―設立されて1年ということですが、今後こんなふうにしていきたいという願望はありますか?
中西さん:
私はまずこの「労働者協同組合」や「協同労働」という働き方をもっと世の中に知ってほしいと思っています。労協法第一条で、労働者協同組合の目的が「持続可能で活力ある地域社会づくりを目的とした事業を行うこと」と規定されています。これまで「働く」というと、会社とか職域ってイメージに直結していたと思うのですが、労働者協同組合という存在は「地域」と不可分に融合していて、そこで働くことが地域づくりに直結します。
なので、地域づくりの新しいツールとして労働者協同組合があるということ、そして自分たちで働き方のルールを決めることができる法人であることを、もっと広めて行けたらと思っています。
前神さん:
私、県庁を退職するまで県庁でしか働いたことがなかったんです。学生時代のアルバイトもしたことがなくて。だからこそ、興味のあること全部、何でもやってみたいと思っています。労働者派遣事業以外で、まちづくりに必要なことであれば、法人の定款上も何でもできるようにしてあるので。
一つあるのは、地域の人が誰でも集まってご飯を食べながら気軽におしゃべるできるような場所・コミュニティづくりをやりたいですね。今もフリーランスの活動の一環でコミュニティ・ナースをやってはいますけど、これは県職員時代の「現場の声を聞く」ことと似ていて、情報収集の側面が大きいんです。
なので、コミュニティづくりもやさまち総研の事業の一環として、他の事業と組み合わせたり、他の労協や団体とコラボレーションしたりしながら取り組んでみたいと思っています。
加藤さん:
私は自分たちの組織が労働者協同組合のモデルケースというか、パッケージみたいな感じで広がっていったらいいなと思っています。
我々3人とも、別に従事している仕事もありながらこの法人をやっているわけですが、そういう働き方に興味がある人は実際増えていると思うので、自分がこの法人で担当している事務的なこと、例えば会計処理や給与計算、ホームページの作成など、お手伝いできるんじゃないかと考えています。
前神さん:
加藤君が事務方を一手に引き受けていてくれるから、やさまち総研は法人として成り立っています。彼がいなかったら、法人の設立はもちろんのこと、運営もできていませんからね。
中西さん:
この労働者協同組合に期待されていることの一つに、「中小企業の事業承継」があるんです。背景にあるのが、地元のオーナー企業が後継者がいないがために廃業や倒産するケースが全国で増えていること。そういう企業の従業員さんと他のメンバーで労働者協同組合を作って、経営権を買い取って労働者協同組合として事業を継承していく。
これはワーカーズ・バイアウトと呼ばれる企業買収の一種で、欧米では先行事例も結構あるようです。日本ではまだこれからですが、町の豆腐屋さんを、労働者協同組合として障害のある人と一緒に事業承継したというような事例が、ぼちぼち出始めています。
自分らしい働き方を実現しながら、地域の資源も守っていけるということも起こり得るので、そういう点でも魅力的ですよね。
前神さん:
愛媛県内にも、地元では有名なお饅頭屋さんがあったんですけど、ご主人が高齢で閉店してしまったんです。でも、地元の人らが「やっぱりあの饅頭がないと」ということで、地元の他業種が製法を引き継いで、今は新商品を出すまでになっています。
他にも、地元を代表するお菓子を作っている和菓子屋さんがあるんですけど、ご主人が高齢でいつまで店をやれるか分からないということで、30代の子たちが事業承継するような動きもあります。これらの事例は労働者協同組合とは違いますが、町の人たち、市民の間ではこういった支え合うような動きが出てきているので、これからますます色んな可能性があると思っています。
中西さん:
中小企業ではないですが、労働者協同組合として経営している歯科医院もありますよ。
―歯医者さんですか!全然想像がつきませんが…
中西さん:
歯科治療は医療行為なので医師しかできませんが、この患者さんをどのように治療していったらいいだろうというのは事務職も含めてみんなで考えられるし、みんなで話し合う場を作りたいと。医療関係でもう一つ言うと、滋賀県内には「共同助産所」でみんなで産後ケアなどをやろうっていう動きもありますね。
―保育とか学童、福祉関係のイメージが強かったですが、そこに限らず本当に色んな業態があるというか、自由にやれるんですね。
中西さん:
そうですね。自由ではありますが、大前提として事業としてきちんと経営は成立させないといけません。そこは一般の企業と同じです。
先ほど、労働者協同組合は地域と融合していると言いましたが、労協に期待されていることの一つに「地域の中で仕事を興す」というのがあります。ただ、地域の中って結果的に隙間産業が多くなるので、採算の合う事業を行うのはなかなか難しいことではあるんです。自分のやりたいことだけではどうしても採算が合わないとなったとき、そこをどう補うか。これは結構みなさん悩まれるところだと思います。
前神さん:
だからこれからは「協業」スタイルが増えていくんじゃないですかね。自分たちだけでは採算が合わなくても、例えば他の労協と組むことで何とかなるかもしれないし、お互いができることを出し合うことによって、新たな可能性が生まれることは大いにあると思います。
―お話を伺って、労働者協同組合に大きな可能性を感じました。ありがとうございました。