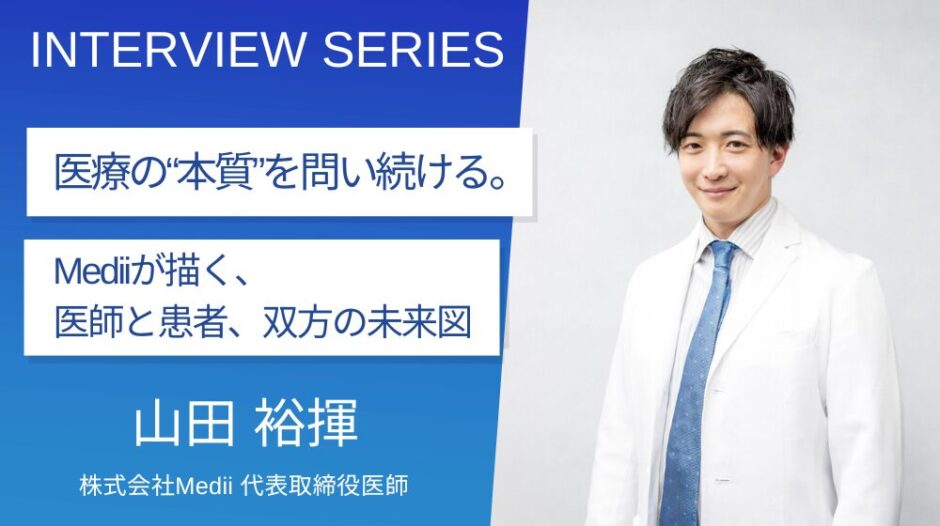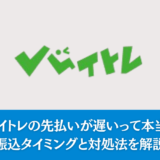Medii。希少疾患やがんなど、診断・治療の高度医療が急速に進歩している分野を中心に専門医の知見と経験をオンラインでシェアする医師向けサービスを展開している。代表の山田裕揮氏により2020年2月に設立された。
山田氏自身が「生涯治療継続が必要」と国が指定する、免疫系の難病を患っている。
難病・希少疾患は、日本でも世界でも人口の約5%が患っているとされる。疾患数は7000種類以上あると言われる。年々、新しい薬剤が開発されている。が現代医学をもってしても、一生治癒されないことが少なくない。
Mediiの存在をその事業展開の最前線に立つ山田氏を知った時、即座に取材を申し込んだ。幸い、快諾を得た。山田氏は「ご存知のところでは安倍晋三元首相。指定難病のひとつである潰瘍性大腸炎の再発・悪化を理由に辞任されました。プロレスラーのアントニオ猪木さんは、全身性アミロイドーシスで亡くなっています。そして未だ明確にされていない疾患が難病・希少疾患には少なくないのが現状です」と話す。76歳に至る今日まで羅患しなかった我が身の幸いを喜ぶのと同時に、人口の5%、600万人いるという決して少なくない羅患者にとり「Medii」の存在感を改めて痛感した。
目次 閉じる
山田氏のMedii設立のそもそも
山田氏は自宅から自転車で5分ほどの、和歌山県立医科大学医学部に学んだ。家系は医者とは何ら縁はなかった。言葉を借りれば「和歌山の温かい人たちや山や海の自然の中で、のほほんと育ってきた」。
と聞けば、医者への道程を知りたく成るのが人情というもの。山田氏は、こう話してくれた。
「自らの体験を通して実感した医療という、“尊い力”を自分も身につけたいと考えました。自分の入退院の経験や家族の死で大切な人が命の危機に陥った時に、直接役立てる医療への憧れを抱くようになりました。同時に医学に関する学術的な興味も湧いてきました」。
「医者になろうと心を決めたのは高校1年の時です。中学生の頃は、研究者としてノーベル賞を取りたい!と思っていたのですが・・・研究者が置かれる現実的な環境はというと、どんなに優秀でも研究結果や専門領域に“運”要素があったり、日本では予算が驚くほど限られている。現実的な医者の道を・・・に至ったのです」。正直に語った。
では山田青年は医学部生として敷かれたレールを、唯々諾々と歩いたのか。NO!・・・失礼ながらだからこそ、起業家の足跡は興味深く取材し書く価値がある。
壁というか、大きな疑問にぶち当たった。
「医学部のカリキュラムがオカシイと直感したんです。だってそうでしょう。医学部というのは患者を救う臨床医を育てることを、目的としているはずじゃないですか。それなのに患者を診る実習は当時5年生からだったんです。しかも、実際医師になった時に必要な診断プロセスや患者さんの心や人生にどう寄り添うか?という根源的に重要な内容も、自分の時にはほとんどと言っていいほどありませんでした。先輩達からも、いきなり臨床医として現場に出てもなかなか分からないことが多く苦労ばかり、と聞きました。海外留学で医学部の実態も知りましたが、ナーシング(看護師の仕事でできることからやってみようという、現場を知る機会が作られる枠組み)制度など、より臨床実習に主軸をおいていました。日本が明確に世界標準からズレていました」。
で、どうしたのか。
思い立ったが吉日だった・・・。「カリキュラムがオカシイ」と感じた瞬間から、「同感」を覚えていた仲間を巻き込んで必要な知見を得るために勉強会を開いた。最初は関西の12大学の医学部を中心に、最終的には当時全国にあった全80大学医学部の学生が集う取組となった。
と記してしまうのは簡単。現実問題として、そうそう右から左にことが容易に進むはずがない。そこには臭覚というか、山田氏独特のノウハウというかハウトゥがあった。「エキスパート。臨床医として希少な知見・経験を持つ先生方(医師・医学博士)に、いわば直談判です。是非お力をお借りしたい。ご理解の上、コミュニティ作りにご協力を賜りたい」と説きまわったのだった。快諾してくれた先生の元には「私と同様にカリキュラムがオカシイ、と感じていた医学部の学生が集ってきた」。
ことに臨んで当たり前に、頭/体が動く。医師で起業家の何人か取材したが、「思い立ったら即、行動」。山田氏もまさしく同様。共通していた。いま、こう振り返る。
「そうして出会った仲間たちや講師を引き受けてくださった先生方がいま、Medii Eコンサルのエキスパート回答医として同じビジョンを共有し事業展開を支えてくれています。Medii は本当にたくさんの人に支えられているんです」。
起業への道筋
希少疾患・難病との取り組みは、自らが患った免疫系難病の患者体験が入り口。具体的には専門医が乏しい、膠原病領域との対峙。
「卒業後は聖路加病院・慶応義塾大学病院等に勤務し、リウマチ膠原病の専門医になりました。かねてから興味があった研究でより多くの人を患者体験救うべく、大学院で医学博士号も取得しました。その上で地元の和歌山を中心に日々、診療に当たっていました。しかし徐々に自分のなかで、社会全体で観た時、自分ひとりで関われる範囲に限界があることを感じはじめるようになったんです。私一人で診ることができる患者さんの数や専門領域は限られている。地域的にも、全国で難病・希少疾患に苦しんでいるより多くの患者さんの課題を解決するためには、医療の仕組みから変えていかなくてはならない、という思いに辿りついたんです。どんな手段・枠組を取るべきなのか、徹底して調べ思いを巡らし、現在のMediiを起ち上げる道を選びました」。
山田氏との遣り取りで痛感した。幸い難病・希少疾患を羅患していない我々の対応が持つ、大きな意義を考えさせられた。
多くが幼少期に羅患する。そして40~50代の働き盛りでも、その重荷を背負い日々を過ごさざるをえない。その負担は非罹患者には体感できない。羅患者は身も心も追い込まれる。最悪のケースに至る場合もある。まわりのちょっとした気遣いが、如何に大切か。言うは易く行うは難い・・・。が、今回の取材でそのことを痛感した。
未だ途上とする理由

Medii Eコンサルはどのくらいの医師が活用しているのか。現状の実数は未公開。が2023年11月に、こんなタイトルのリリースを配信した。『日経メディカルと戦略的業務提携を締結』。「日本の医師総数の約6割が登録する日経メディカルOnline医師会員に対し、臨床疑問があった際にMediiのオンライン専門医相談サービス“E-コンサル”を利用頂ける環境を構築し“、両社で連携して希少疾患等のスペシャリティ領域における早期診断と最適治療の促進を加速させていきます」という内容。「実数」を推し測ることはできよう・・・。
起業、5年半余。前記のような立ち位置に身を置きながらも山田氏は、「未だ、拡充の途上」とする。
現在の医療現場では専門領域はますます細分化し、複雑になっている。患者に最新の知識を提供し続けることは、医師にとりますます負担が増している。医薬品の開発も進んでいる。山田氏の言葉を借りれば「レーシングカー。車の免許を持っていても最新のレーシングカーを乗りこなすのは難しいように、医師免許を持っていても革新的な新薬を活かすことは簡単ではない」。
取材で山田氏は、「寛解」という言葉を口にした。病院用語で検索した。「こんな誤解がある」という項が目にとまった。『病気が完治した状態だと誤解されやすい。一時的に症状が軽くなったり消えたりしているので、治ったわけではない。再発の可能性があることも伝える必要がある』。臨床医:山田氏に常に重くのしかかっているものを、改めて痛感した。
Mediiが目指しているのは限界に直面している希少疾患やがんなど、高度医療が急速に進歩している分野の診療におけるこの構造的な問題を、信頼できる専門医に相談し解決に導くことで克服すること。またその専門医が適切に評価されること。「適切な評価」でそうした専門医に心底からやる気を起こさせること。終わりのない旅、終着点がない旅。
Mediiはラテン語で『本質』を意味する。山田氏は改めて自らに言い聞かせるように、「本質的な医療の実現にはまだ途中ですが、道筋が見えてきたことから事業を急速に拡大するフェイズに入っています。新たな位相の実現には、更に一人でも多い世界観を共有できる仲間との出会いが肝要です」。
拡大期のフェイズ入りは、ベンチャーキャピタルをはじめとする金融資本の調達にも見て取れる。この延長線上には「上場」の二文字が待ち構えている。私の単なる推測ではない。「興味をもって見守っている」とするベンチャーキャピタリストの声を聞いた。