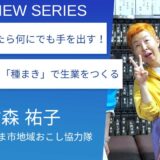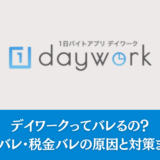兵庫県明石市出身の平石さんは、大学生時代を秋田県秋田市で過ごし、神戸市での会社員生活を経て、再度、秋田市へ移住されました。現在は移住先としても人気な地元・明石市や、都会の魅力が詰まった神戸市ではなく、あえて秋田市を選んだのは「運命」だったという平石さん。今回は地域おこし協力隊の移住コーディネーターでもある平石さんに、ご自身のキャリアと照らし合わせた移住の経緯や、秋田市の魅力、人口減少する地方の実情などについて伺いました。
(記事公開日:2025年10月1日)
コロナ禍を経て、学生時代の思い出の地・秋田へ
――ご出身は兵庫県明石市とのことですが、なぜ秋田市へ移住されたんですか。
私は生まれてから高校までずっと明石市に住んでいて、秋田の美術大学への進学をきっかけに、初めて秋田市に来ました。その後、秋田市にあるテレビ局にアシスタントディレクターとして就職しました。学生だった当時、社会人として働くイメージが全然できなかった時に、学生課の就職相談担当の人に、「君は情報発信が好きなんだったら、メディア関連とかどう?」って勧められたのがきっかけでした。
――県内に就職先があったんですね。
はい。でも秋田県で生まれ育った人たちの中では、大学進学から県外に出るということが多いです。私の大学の同級生も東北出身者が多いのですが、卒業後東京に出てそのまま結婚して都会で家を建てる子はいて、私の出身地の関西圏と違うなと感じます。京阪神には経済圏があるからか、割と関西への地元愛があって、東京に憧れることがあまりないんですよね。なので、秋田で感じた「東京に出るのが当たり前」という感覚は、カルチャーショックでした。
――やっぱり一度は都会の暮らしを知りたいと思うでしょうね。
私が一度秋田から出た理由も、同じ様なものでした。
卒業後も3年間はテレビ局のアシスタントディレクターの仕事で秋田に住み続けたんですが、その後神戸市にある通販の会社に2020年2月、経験者採用で入りました。
ところが、神戸でアーバンライフを楽しもうと思っていた矢先、コロナ禍になってしまい世の中が大きく変わってしまいました。私は自分の生活の大きな変化もあって体調を崩してしまい、働いていた3年間の間かなり休職しました。収入が不安定な上、神戸は家賃が秋田の倍なんです。働いても固定費として引かれるものが大きくて、秋田にいた時より収入は上がったのに、貯金は下がってしまいました。気持ちとしては、会社も同期も大好きだったので働き続けたかったのですが、心と体が思うように動かなくなってしまったんです。
そういうこともあって、一旦会社員の生活からスローダウンしたいと考えるようになりました。とりあえずアルバイトでもなんでもいいから、固定費を抑えて、ゆっくり自分のペースで体調を整えられる働き方に、シフトチェンジしようと思って。そこで、秋田での暮らしが良かったなと思い返して、秋田への再移住を考えていました。
そのタイミングで、通っていた大学の同級生からLINEがありました。その子は秋田市役所で務めているのですが「協力隊応募集してるよ」って教えてくれて。当時、秋田に住むことはもう決めていたので、じゃあチャレンジしてみようかなと応募しました。テレビ局勤務時代に3年間、市政番組に関わっていたこともあり、秋田市役所との繋がりも少しありました。行政が求めることへの理解もあったからか、面接はスムーズに進み、協力隊になることができました。
――それは、秋田に呼ばれましたね。
本当にそうだと思います。同級生からのLINEは、運命だと思ってますね。

田舎過ぎず都会過ぎない、ほどよい暮らし
――「都会に出るのが当たり前」という感覚の秋田へ戻られたわけですが、逆に、都会から秋田市に移住するメリットは、どう感じておられますか。
まず、パーソナルスペースが広いことです。都会のぎゅうぎゅう感は本当にストレスですよね。でも秋田市内では、スーパーで行列に並ぶことがない。ゆったり過ごせる田舎感と、都会の便利さのバランスが絶妙に取れている。都会に住んでいる方は、田舎暮らしに憧れているとはいっても、いきなり農村で暮らしたいわけではない方もいらっしゃいます。そんな方には、秋田市の様な地方の県庁所在地がちょうどいいかもしれません。空気がおいしいし、食べ物も充実しているし、空港や新幹線もあるのでたまには都会に行って刺激を受けることもできます。いきなり田舎に住むと、都会とのギャップで苦しむ人もいますので、移住を考える上でのファーストステップとしてもおすすめです。まずは地方都市に住み、そこから適した環境を探すのも良いと思います。
秋田市は仙台市に比べて都会感は薄いですが、山も海も川もあって、程よい自然の豊かさがあります。
また県内では都市としての役割を担っていますので、一次産業よりも三次産業が盛んです。海に面してはいるものの、漁業はあまり盛んではないですね。
秋田市は程よく都会なので、近所付き合いは割と希薄です。なので、村社会みたいなのが苦手っていう人にはぴったりだし、逆にもうちょっと温かみが欲しいという人には、もしかしたら冷たく感じるかもしれません。おまつりが盛んなので、関わると地域との距離はグッと縮まると思いますよ。
――全体的に5点満点で3点以上が多いような、バランスの良さが特徴なんしょうね。
そういうことです。100点満点の町なんてたぶんどこにもないですし、人の感覚にもよりますよね。

移住担当として感じる秋田の魅力
――協力隊の任務である、移住コーディネーターのお仕事について教えてください。
主な仕事が移住コーディネーターで、移住ツアーのアテンドをしています。移住ツアーは重要で、ツアーがきっかけで移住された方は多くいらっしゃいます。ヒアリングをしたり、アポイントメントを取ったり、丸2日間アテンドしたりと業務の量があるので、秋田市役所が協力隊を活用する理由かもしれません。
秋田市に来たことがあるなしに関わらず、移住希望者さんに対してはなぜ秋田市に来たいかを事前にヒアリングするのが重要ですね。「ビジネスをしたい」とか「農業をはじめたい」といった方には、起業や農業のサポートをしてくれる場所をご案内し、子育ての環境を見たい方には学校の見学や遊び場にお連れします。移住希望者さんがイメージしていたのと秋田市が異なることもありますが、そういう場合には「あなたが求めるものは秋田市では叶わないかもしれないよ」とお伝えすることもあります。単に移住件数を増やすよりは、長く住んでいただきたいし、お互いに気持ちよく同じ町に住む仲間として移住していただきたいと思っています。
移住ツアーをされた方は毎回概ね満足されていて、お礼のメールやお手紙をいただけると本当に嬉しいです。私自身もおもてなしの気持ちで、秋田市への理解を深めながら楽しんでやっているのでとてもやりがいのある仕事です。
ほかにも、移住傾向の調査として、「秋田市移住体験住宅」に宿泊された方にインタビューしに行く業務もあります。移住体験住宅は、民営の宿泊予約サイトで予約できます。インタビューを通して、どういう人がどんな理由で秋田市に移住したいと思っているかを調査しています。
移住を検討される方の傾向としては首都圏の方も多いですが、秋田県内出身の方も多いですね。例えば、出身は由利本荘市やにかほ市だけど、地元に帰るとなると就職口がないから秋田市を選んだという方が多いです。
移住体験住宅の方はライト層で、「秋田市を自分で見たい」という希望があるのに対し、ツアーを利用される方は、割と本気度が高い人かなと思います。その本気度が例えば50%だったら、それを60~70%に引き上げるのが、私たちの役割です。

――アテンドする中で、移住先としておすすめしている地域はありますか。
移住希望者さんの理想とする生活の中で譲れないものが何かによるので、特定のここがおすすめ!という場所は特にありません。
ただお伝えしているのは、秋田市は都会ではありますが車社会なんですよ。よく聞くのが、子どもたちの移動が不自由で、親がいないと移動ができないということです。大きいショッピングモールや習い事、部活動の大会が開かれる競技場など、子どもだけで公共交通機関で行ける範囲にない事が多く、大人が自家用車で連れていく必要があります。特に中高校生になると、不自由を感じるかもしれませんね。お子さんご自身での移動を希望される場合、あまり郊外に住むのはおすすめできません。中心市街地であれば本数は少ないながらもバスが1時間に1本はあります。
また、秋田市には積雪もあります。沿岸部と内陸・山間部では積雪量も大きく異なります。どこに住むとしても車を運転される場合は冬タイヤへの交換が必要で、自転車には乗れません。雪かきもあるので朝の出勤15~30分くらい前に外に出て、スコップで雪かきをしてから出なくちゃいけない。雪国で暮らすことの大変さもお伝えしています。

――大都会から家族で移住する人々には若干ハードルが高そうに聞こえます。平石さんは今後も秋田市に住まれるそうですが、相性が良かったんでしょうか。
瀬戸内海の海が広がる地元の風景も大好きですし、たまに帰ると「地元マジ最高やん」って思います。それなのに「なんで私は秋田に住んでいるんだろう」と考えた時、私は雪が好きなんだと気づきました。今は賃貸に住んでいるので、雪かきしなくていいし、車も持たずに徒歩・自転車・バスで移動しています。家から秋田駅まで歩いて40分以上かかるんですけど、冬は運動不足になりがちなので歩きます。雪の中を歩くのは景色も雪を踏む感覚も好きですね。

――季節感を感じつつも、それほど雪に煩わされることもない。そういった生き方も秋田市では可能ということですね。
秋田に長く住んでいる方にとっては車を持つことが当たり前なのですが、1人暮らしで車を持つことへのこだわりが無い場合は可能だと思います。ご家族やお子さんがいる場合はどうしても車は必要だと思います。中には車なしで子育てされる方もいらっしゃいますけど、市街地に近いライフラインが整った場所に住んでいらっしゃいます。私が今住んでいるところも市街地です。コンビニもスーパーも近いし、全国チェーン店が多いのでかなり便利な場所ですね。そんなに家の広さは必要なくて賃貸でも構わないという方や、車を持たずに暮らしたい方は市街地に住むのがおすすめです。逆にマイホームを建てたい方は車が必要なエリアに住むことになると思います。
協力隊卒業後について
――平石さんは秋田市案内のエキスパートですね。現在協力隊3年目とのことですが、卒業後はどのような活動をされるんですか。
卒業後のことはまだ進んでいないんですけど、独立してデザインとか動画制作とか、雑貨屋さんを同時にやりたいなって思っています。そうやって思えるようになったのも、秋田でフリーランスとして活躍している人との繋がりができたからこそですね。秋田はコミュニティが狭い分繋がりやすいし、その中で仕事が回りやすいのは、メリットだなと思います。フリーランスの方も都会に比べて母数が少ないから、イラストと言えばあの人、写真と言えばあの人、といったように顔が頭に浮かびやすい。少人数の中で、依頼に合わせてやりたいことやスタイルに応じて仕事が発注されていると思います。
協力隊活動の中で、協力隊のぽんぽん通信というものを2ヶ月に1回発行しています。手に取ってくれた方から、イラストとかコラムを書くお仕事をいただくこともあります。市民の人からも「いつも見てます」と声をいただくのがうれしくて、今後も発信活動は続けていきたいと思っています。

県のリーダー的都市としての課題
――人が少ないメリットもあるとのことですが、秋田県は、人口減少率が全国的にみても高い県ですよね。
そうですね。秋田県の人口減少率は12年連続、全国で最大です。秋田市は地域おこし協力隊を受け入れるには人口が多いのですが、減少スピードがめちゃくちゃ早いという理由で、国から条件付きで協力隊採用を認められています。
協力隊の業務として東京などで開催される移住フェアに出張に行くとか他県からの学びがあります。最近感じたのは、移住関連のことは県や県庁所在地の自治体が率先して進めなきゃいけないんだなと実感しました。他の自治体の出展ブースを見ると、移住・定住に対する熱の入れ方からすごくやる気を感じるのです。これは予想なのですが、おそらく県がトップに立って、市町村をまとめているんですよね。
たとえば、兵庫県北部の日本海沿いの自治体と、隣の鳥取県の自治体が、県をまたいで連携し、一丸となって移住者を誘致しているのは、すごいなと思いました。もし私が移住希望をする立場でお客さまとして会場にやってきた時に、ここの県はまとまりがあるとか、姿勢として統率を取って移住を促進してるんだって思えるだけで信頼度がアップしますよね。そういった意味での秋田県の自治体の連帯や横の繋がりはまだ弱いと感じます。
小さな自治体が、財政が厳しい中すごく頑張って移住フェアに出展しているのを見ると、県庁所在地である秋田市が率先してやらなくてはと責任感が芽生えました。
――確かに、もしも自分が小さな自治体の職員で移住フェアに頑張って出展していたとして、その時に県庁所在地の都市が余裕をかましていたら、「危機感ないな…」と思いそうです。県内一枚岩にはならないでしょうね。

自治体の限界が見えていても
一枚岩といえば、秋田県には、「協力隊ネットワーク」っていう、秋田県内の協力隊卒業生が運営する組織があるんですよ。秋田県内すべての自治体の協力隊によびかけて年に数回集まって協力隊の体験談を聞いたり、地方創生に関する講演を聞いたり交流をします。地域おこし協力隊は自治体ごとに、やることも役所との関係性も異なります。私は協力隊ネットワークで他の自治体の協力隊の話を聞けたことで、繋がりができ、秋田市役所に対して協力隊活動の交渉をできたのは助かりました。ネットワーク内で悩み相談もできるので、秋田市のような協力隊の採用人数が少ない場合はとてもありがたいです。全国の協力隊でも、孤立するという問題をよく聞くので、秋田に協力隊ネットワークがあるのは本当に良かったなと思いました。
――平石さんのインタビュー記事をどこかで読みましたが、「協力隊は実態が見えない」というようなことを最初、感じていらっしゃったとか。
ずっと、「協力隊ってなんなんだろう」って考えながら活動していますね。すごく引きの目で見ると移住定住そのものにも疑問はあります。地方の移住フェアに行けば、人口を地方同士で取り合って、「日本の未来はどこに向かってるんだろう」って、切ない気持ちになります。それに、自治体単独で移住促進をすることに限界が来てるのではとも感じます。東京一極集中を分散させなくちゃいけないのは分かるけど、それを地方自治体に任せっきりでいいのだろうか。しかし地方としても、「できることをやる」っていう姿勢を見せるのはやっぱり大事だとも思います。もし国が何か政策を打つとしてもまかせっきりではなく、「うちの地域はすごく楽しく、安心して暮らせるよ。移住を歓迎します!」とPRすることは、この先状況がどう変わろうとも必要だなって思います。
――私たちもいろんな地域のインタビューをしていますが、結局は将来的に人口減で消滅する自治体も確実にあるんだよな、と感じるたびに、切ないですね。
そうですよね。秋田県にもそういう地域がたくさんあります。現実的にインフラの維持などを考えると、コンパクトシティになるしかないんですが、昔から人々が愛した地域や伝統文化が無くなることはとても寂しい。でもこういうことは会社員だった時には何にも意識してなかったことで。当たり前のように自分の住みたい場所に住んできたから気づかなかったことでした。協力隊になってから、町を見る視点や人の人生を見る視点が変わりましたね。

――地方の実情が経験として身になったわけですね。そういう方がもうちょっと政治に関われたらいいですよね。
協力隊が終わってから役所の会計年度任用職員になる人はいます。ずっとその環境にいる職員が気づかないことも、外から来た協力隊だといろんなところが目につくので、そういう視点で必要とされると思います。
政治の関わり方については人口の少ない自治体の方が政治家との距離も近く、投票も1票が重いです。ここ数年は投票率も上がってきていますし政治に対する市民の意識も高まっているように感じています。秋田県が運営するSNS「あきたの声と夢が集まるアカウント」@akitanokoe_seisaku では若い人の意見をくみ取る活動もされています。
人口減少でネガティブなイメージも多いのですが、住んでみると周りには魅力的な人が本当にたくさんいます。自分たちの住む地域をもっと良くしたいという活発な流れが見られてとても楽しいです。地域貢献って献身的なものだけではなく、住んでいる人がしあわせを感じる瞬間がたくさんあることにも直結すると私は考えています。
――平石さんの様な方が地方に存在することに一縷の望みがあると思います。協力隊の活動内容だけでなく、地方自治に関するお話まで、ありがとうございました。