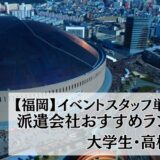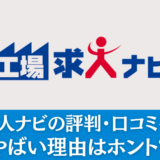メディアやSNSなどを通じて話題となり、爆発的なヒットを記録した、質問に答えていくだけで出身地を当ててしまうwebサービス「出身地鑑定!!方言チャート」。このサービスの開発を行っているのが東京女子大学の篠崎ゼミです。現代教養学部人文学科の篠崎晃一教授の指導の下、これまでに200人以上の学生が開発に携わっています。
篠崎先生ご自身は、方言学、社会言語学を研究されている言葉の専門家。著書の執筆やテレビ番組へのご出演など、マルチにご活躍されています。
今回のインタビューでは、方言研究のお話や時代と共に変容する言葉についてお話を伺いました。

篠崎 晃一先生
東京女子大学 教授
研究分野は社会言語学 / 方言学。
方言も含めた現代日本語のバラエティや、各地の言語変化の動向について研究している。
最近は、言語行動やコミュニケーション場面の地域差にも注目している。
【書籍等出版物(単著・共著)】
『出身地(イナカ)がわかる方言』(共著、幻冬舎、2011年
『それいけ!方言探偵団』(単著、平凡社、2021年)
『例解新国語辞典 第十版』(共編著、三省堂、2021年)
『東京のきつねが大阪でたぬきにばける 誤解されやすい方言小辞典』(単著、三省堂、2017年)
方言の成り立ちと変容

――先生がそもそも方言にご関心をお持ちになったきっかけを教えてください。
最初に興味を持ったのは、学生の時に参加した方言調査ですね。同じものを表すのに、いろんな言葉のバリエーションがあるということに興味が湧きました。
その後、大学院に進学して、はじめは文法でもやろうかなと思っていたんです。ところが、周りは全国から集まった方言研究をしたいという若者ばかり。あとから知ったのですが、当時、東京都立大学の大学院というところは、方言研究の中心的な学術機関だったんです。そこから専門的な勉強をしていき、興味が深まったということですね。偶然もあったのですが、現在は大学で方言学を教えているのですから、何がどう転ぶかわからないものですね。
――昔は日本全国で言葉が統一されていたのでしょうか。
かつては都が近畿圏にありましたよね。都で使われていた言葉が全国に広がっていき、それが今、方言として残っているケースが多いですね。
――蝸牛考(※1)で柳田國男が提唱した「方言周圏論」ですね。
そう、そういうことです。ですから、それぞれの地域で突然変異的に生まれるわけでもないんです。中央から広がっていった言葉に、地域特有の音声変化の規則が適用されて、形が変わっていくということですね。
前に流行った「じぇじぇじぇ」という言葉。室町時代には都で驚いた時に「じゃ」というように言っていたんです。それが広がって、岩手の海岸部では「じぇ」という形に変わったんですよ。
あと、東北弁では可愛いことを「めんこい」と言いますね。あれも万葉集に「めぐし」という言葉が出てきて、それが広がって「めんこい」とか「めごい」という形に変わっているんです。 ただ、例えば雪の多い地域だと、雪の降り方に応じていろんな細かい言い方が生まれたりする。その地域の環境や文化などの背景によって、他とはまた違った言葉が生じる、ということもあるんです。
※1 民俗学者の柳田國男が、日本各地の蝸牛(カタツムリ)の呼び名を調査した論文。この調査をもとに、方言というものは、京都で使われていた語が地方に向かって同心円状に伝播していき方言分布が形成されたのではないか、という解釈を提唱した。
――現代の「共通語」というのは、元々は方言がごちゃ混ぜになってできたものなのでしょうか。
今の東京といわれるエリアで元々話されていたのは、江戸語と言われているものです。江戸時代、名古屋をはじめとした西の方から徳川の武士団が入ってくるわけですが、そういう武士階級の人たちがいわゆる山の手というところで生活するようになります。元から江戸にいた人たちの住まいは下町と言われるところ、というように住み分けが生じるんですが、商売などで交流は生まれるわけです。元々の江戸語と、西の方から入ってきた言葉が混ざり合って、それが洗練されて今の東京語の基盤ができ、共通語になっていったんです。
――東京語が全国で共通語になったのは、テレビなどの普及が背景にあるのでしょうか。
1960年前後に全国調査した「日本言語地図」というものがあるんですけども、そこに記述されている方言の分布は、江戸時代中頃に編纂された「物類称呼」という我が国初の全国規模の方言集の内容とかなり一致しているんですよ。だから200年以上の間、方言の分布状況が変わってなかったことがわかります。
けれどもそれ以降、東京で初めてのオリンピックが開かれたりして、日本中にテレビが普及していくわけです。そうすると、急速に共通語が全国に広がっていって、方言が衰退していくことになりました。
――今ある方言も、いずれはなくなってしまうという危惧はあるのでしょうか。
方言でしか表現できない状況というものはありますので、置き換えがきかない言葉は残ると思うんです。
それに、若い人たちは割と方言に興味があると思います。特に全国的に認知度の高い方言、例えば博多弁なんかは、「博多弁可愛い」なんて言われますよね。そうすると若い子も意識して使うようになる。
――あえて方言を使う若い方も多いと。
そうですね。ただ、用法が変わってきているわけです。
「〇〇しとうと?」っていう博多弁がありますが、本来「~と」は活用する語にしかつかないんですよね。だから「明日雨と?」なんて言い方はしないんですが、若い人はそういう使い方をするんです。本来の用法ではなく、若い人たちが新たな用法を生み出して使っている。だから、「あんた学生と?」みたいな使い方が生まれています。
――福岡市出身の私からすると、すごく違和感があります。
でも、知らない人から見ると、博多弁使ってるんだ、と思いますよね。そうやって方言が変容してきているという状況があるので、完全に方言が0になるってことではないと思うんです。あるいは、方言と共通語がミックスして、新しい方言が生まれることもありえます。
――地域の中でも職業などによって言葉が違うことがありますが、それも何か背景があるのでしょうか。
習慣的なものが違うので、同じではないかもしれないですね。
農家であれば農具の呼び方だとか、漁業関係では、風の呼び方とか、微妙な方角の違いに呼び名があったりとか。まさにそういうのは共通語には訳せない言葉でしょうね。
方言調査から生まれた「方言チャート」

――先生はどのように方言調査をされていますか。
基本はフィールドワークです。やっぱり方言というのは音声言語なので、文字面だけではなかなか捉えきれない。その地元に行って、どんな風土で、どんな人が、どんな喋り方をしているのか、肌で感じることが大事だと思うんですね。もちろん学生もフィールドワークへ連れて行っています。
――例えば、私は津軽弁はほとんど聞き取れないんですけれども、先生ともなると簡単に聞き取れるものですか。
いやいや、聞き取れないですね。山形の庄内地方とはフィールドワークで30年近い付き合いがありますが、私も未だに全部は分からないです。特に電話だと聞き取れないですね。
――東京女子大学は首都圏出身の学生さんが多いと思うのですが、どのようにフィールドワークを進めていくのですか。
もう町とは長い付き合いがあるので、役場が協力者を探してくれたりしますし、地方の人たちも調査に慣れているので、逆に学生は調査しやすいと思うんですよ。
学生にはとにかく発音を録音させて、なるべくそれに近い仮名で記述させていきます。仮名の表記がおかしくないかは、もう一度私と発音を聞きながら確認して、間違いがあれば指摘して直していきますね。
――篠崎ゼミが開発した「方言チャート」もフィールドワークを通して出来上がったわけですか。
全国各地全てをフィードワークできるわけではないので、情報を集めて、地元の人に本当にそういう言い方をするのか確認する、という作業の積み重ねで方言チャートは作り上げています。
利用者は延べ1,000万を超えていますが、判定の最後にはフィードバックを得られるようにしているので、いろんな情報が集まってくるんです。それを分析していくと、今まで我々が把握していた地理的な広がりよりも広かった・狭かった、とか、 意外とこの県ではこの方言を使っていなかった、ということが分かっていくんです。そのデータを使ってさらに精度を上げていっています。47都道府県バージョンもアップデートして最新版を出していますのでぜひやってみてください。あとはもう1つ、「県人度判定」というアプリもリリースしています。
――これらの企画はどのような経緯で開発が始まったのですか。
方言の研究は調査が大事なんです。ただ、調査をやりっぱなし、データだけ集めてやりっぱなしっていうのは一番よろしくないので、どういう成果が得られたかを必ず還元するようにと学生には伝えています。卒論で方言の調査をしても、必ず還元作業をするように指示しているんですよ。
ただ、調査の成果を報告書にしたところで読まれないかもしれない。もっと「何か楽しめるようなもので還元できたら」という想いから開発がスタートしました。
――大変話題となった方言チャートですが、リリース当時宣伝などされたのですか。
最初に私のゼミを取材しに来た新聞社があったので、まずそこにだけ公開情報を流したんです。その新聞社が記事にしたところ、各社後追いで取材が殺到しまして。 もうどんどん拡散されて大変なことになりましたね。
言葉の移り変わりは「誤用」ではなく「変化」

――先生がこれまで研究をされてきた中で、言葉はどのような影響によって変容していくものだと思われますか。
いろんなパターンがあると思うんですが、一つは「音(おん)」の位置が変わったりする。例えば、「新しい」という言葉は「あたらしい」と言っていますが、昔は「あらたし」だったんです。そういう音が出てきた時はおそらく「誤用だ」と言われたのかもしれないけど、今は「あたらしい」が普通ですよね。「だらしない」は、昔「しだらなし」という形で出てきたりね。他にも、植物のサザンカは漢字で山茶花って書きますよね。元は「サンザカ」だったからその字が当てられている。音の位置が変わって、それが定着していくというケースです。
あるいは、例えば「気の置けない人」なんていうのは、昔は「気を許せる人」という意味だったのが、今は「気を許せない人」と逆の意味で使う人の方が圧倒的に多いんです。「ない」という打ち消し的な部分にひっぱられて、マイナスの意味が強くなって広がっている。
いろんな変容の要因があるので、私はあんまり誤用っていう表現は使わないようにして、変化だという風に言っています。
――「正しい日本語」というテーマでメディアの特集が組まれたりしますが、誤用ではないと。
私も「正しい日本語」をテーマに講演してくれと頼まれますけど、「正しい日本語はない」というテーマならやります、と回答していますね。
誤用と言われる使い方を8割の人がして、本来の使い方は2割の人しかしない時に、本当にそれを誤用と言えるのか。言葉というのは、コミュニケーションを取り合うための道具なので、8割の人が使っている誤用と言われる用法の方がコミュニケーションを取れるのであれば、それはもう言葉の機能を果たしていると考えますね。
――昔からの言葉の定義が常に正しいということではなくて、その時代の人々が正しいと感じているものも用法として受け入れると。
私が編集代表している国語辞典は、誤用と言われている意味や用法も語釈として採用しています。そこに注意書きとして、本来はこっちの意味だったけれど、今はこの意味で使う人が増えている、と添えるようにしてね。
国語辞典というものは、言葉の実態をリアルタイムで反映していくという責任があると思っているんですよね。
――それでは、若者言葉に目くじらを立てたりするのは非常に無粋な行為かもしれないですね。
そう思います。例えば、若い人の間で「タメ口」という言葉があるけれど、じゃあ「タメ口」という言い方を使わなかったら、なんて言えばいいのか、他に一言で表現できる言葉はないんですよね。一語で表現できるというのは、やはり便利なんですよ。機能的であるという意味では、もうそれは言葉の役割を果たしていますからね。