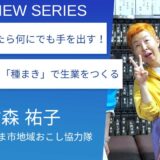管理栄養士。それは専門的な知識・技術を持ち、病院や福祉施設や学校などで栄養指導や栄養管理を行う仕事です。国家資格のため、大学や専門学校の課程で学び、国家試験に合格して資格を取得する必要があります。
今回は、そんな学校の一つである長野県立大学健康発達学部食健康学科の中澤弥子教授にお話を伺いました。管理栄養士を養成するコースでありながら、中澤先生のゼミでは郷土食の調理や農作業体験を通じて、食文化の豊かさや食べ物の命について学んでいるそうです。そんなゼミに込めた想いや、管理栄養士教育に対する疑問感など、幅広いお話をお聴きしました。

中澤 弥子 先生
長野県立大学 健康発達学部 食健康学科科 教授
専門分野:食文化研究、調理科学、食育
研究テーマ:生活文化も含めて日本を含む世界の食文化の特徴やその形成や変容について明らかにすること。
・お茶の水女子大学家政学部卒業
・お茶の水女子大学大学院家政学研究科修士課程修了
・東京大学大学院医学系研究科博士課程修了
長崎短期大学専任講師、長野県短期大学専任講師、助教授、准教授、教授を経て、2020年3月まで兼務。2018年4月より長野県立大学健康発達学部食健康学科 教授。
共著として「食材と調理」「くらしと安全 身近な生活環境における安全とリスク」。
長野県の食は豊か
――中澤先生は、食文化に重きを置いた教育を実践されているとのことですが、日頃その題材とされている長野県の食文化について、特徴を教えていただけますか。
中澤先生:長野県には海はありませんし、作物が栽培できない冬の期間が長いです。しかし「あるものを工夫しておいしく食べる」という手間を惜しまない技術の蓄積が、長野県にはあるなと感じています。私自身は熊本の出身で、仕事で長野県に住むようになって28年になりますが、たとえば発酵を利用した保存食作りという素晴らしい技を、皆さんが持っていらっしゃる。長い冬を超えて現れる山菜に対しての向き合い方も、他県のそれと違うように思います。夏場は畑で収穫したものをたっぷり食べ、それをまた冬に向けて工夫して保存する。昔はそうしなければ食べるものが不足したと思いますが、今でもそれを続けて大事にやっていらっしゃるのが長野県の食の豊かなところだなと感じています。

美味しさと効率のバランスを見極めることが肝要
――なるほど、たしかにそう言われれば漬物や味噌などは、長野県の気候や文化の中で育まれていったものだとわかります。中澤先生のゼミではそんな豊かな長野県の食文化について学んでいらっしゃるのですね。
中澤先生:はい。本コースは管理栄養士養成コースなのですが、管理栄養士が食文化を理解しておくことは重要だと思うのです。普通の管理栄養士を養成するための学校では、食文化を必修科目で配している所は少なく、海外プログラムでの食文化の学びも合わせると食文化を専門的に学べる大学は他にないと言っていいと思いますね。
なぜそこまで食文化を重視しているかと言いますと、栄養的観点やコストだけで食を切り取ってしまうと、人が口にしたいものとの乖離が出てきてしまうからです。食文化の知識があれば、より相手の心や身体が欲しているものを提供でき、完食して結果的に望まれる栄養摂取につながると思います。
季節感を大切にしてほしいです。また、長野県産のものがあればなるべくそれを使うようにしています。海外産の食品や冷凍食品についても、それ自体がすごく悪いという訳ではありませんが、地元の農産物を食べることは地域の農業や自然環境を守ることに繋がることを意識し感謝して使いたいと思っています。冷凍食品は一番いい時期に収穫したものを使っているから、品質が悪い訳ではありませんが、地元の旬の採れたてのものを使った料理と比べると味が全然違いますよね。
学生たちには栄養の数値とコストばかりを気にするのではなく、食文化や食べ物、さらには食べ物を育む地元の自然環境を大切にできる管理栄養士になってほしいんですね。

料理コンテストから地域でのフィールドワークまで。多岐にわたるゼミ活動
――食文化の知識を持つ管理栄養士を育てるために、熱心に活動されているのですね。中澤先生のゼミでは具体的にどのようなことをしていらっしゃるのですか。
中澤先生:郷土料理に関する料理コンテストに応募したり、地域で食育活動を行ったり、名人を尋ねて郷土料理の作り方を教わったりと様々ですが、なるべく人と会ったり出かけたりするようにして、刺激をもらうようにしています。
たとえば毎年3年生には日本うま味調味料協会が開催している「おいしく減塩 郷土料理コンテスト」に応募してもらっています。うま味調味料の性質を利用して、減塩に取り組むコンテストで、郷土料理をおいしく減塩する方法を検討する中で、学生が基本的な調味料の使い方を理解し、使いこなせるようになることが大事だと考えています。
それに、だからといって学生たちがうま味調味料をものすごく使うようになるかといえば、そうではないですね。素材の味がおいしければ、余計なものは入れないので。そういう訳でコンテストに出てもらうんですが、全員で協力して1つの郷土料理をテーマとして、塩分を約2分の1に減らすことを目標に減塩します。これまで諏訪の「のたもち(半搗きにした餅米の上に枝豆で作った餡をかけたもの)」や佐久の「鯉こく(鯉を味噌で煮たもの)」などをテーマに取り組みました。現在、愛知県出身の学生を中心に、「味噌煮込みうどん」の減塩にチャレンジしています。おいしく減塩するため、うま味調味料などでどう補ったら良いか、実験を繰り返すんです。そうすると学生同士で協力する機会にもなりますし、味の相互作用などについての勉強にもなります。
調理実習では学生が失敗してもいいよう、時間に余裕を持たせることを意識しています。時間をかけて多少失敗しても見守れるように。こうして失敗やおいしく料理を作ってみんなで一緒に食べることの楽しさを経験しながら、食品の調理性や調理技術に加え、創造性などを身に着けてもらいます。


のたもち(画像引用元:JA長野県)
それから地域との活動も精力的に行なっています。今年は王滝村で年4〜6回ほど、自治体と一緒になって四季折々のレシピを考えるということをやっています。王滝村は長野県内でも昔ながらの料理や調理技術が残っている地域だと聞いていたのですが、そうした文化をしっかり後世に伝えていくために、学生と地域の方が一緒に郷土料理を作るイベントを開催したり、小学生が「すんき(赤かぶの葉を塩を使わず乳酸醗酵させた漬物)」を使ったレシピでコンテストに応募したり。小さな村ですから郷土料理を作る人も売る人も限られていて産業化はなかなか難しいようですが、村の豊かな暮らしのために活動されていて、すごいなと思いますね。

また、夏休みの間には子どもたちを対象とした料理教室も学生たちと一緒に開催しています。こうした体験をすることによって色々な気づきを得る機会になるのではと思っています。私も学生時代、周りの方からチャンスをいただいて色々な体験をしてきました。だから学生たちにも色々な体験をさせたいと思います。「行ってよかったな」「面白かったな」と思えて、何か気づきを得る良い体験になればいいなと。私もゼミ生と一緒に体験するから見えることも多いです。
他にも、先日は郷土料理研究家の横山タカ子先生をお招きして、お漬物を教わりました。ゼミは少人数ですので、一人一人が先生とお話しすることができ、先生のエッセンスを学べました。先生も「時間は調味料の一つ」とおっしゃっていましたね。昨今どうしてもコスパ、タイパと言うけれど、時間というのは料理の中では調味料になるよね、とお話をされていました。いいことを学生にお伝えくださったなと。やはり効率だけでは料理はできないと、実感することができました。
普段はこうして集団での学びを大事にしているのですが、卒業論文は個人で研究をさせるようにしています。2人でやるとしても、それぞれ一つテーマを持つように。たとえば長野県のお盆がテーマだったら、一人は北信地方と東信地方について、一人は中信地方と南信地方について調べるとか。私のゼミでは『長野県史』民俗編を資料としており、載っている料理を調べて作ってみるなどしましたね。
あとはゼミではないのですが、サークルでおやきの新しい具のアイデアを考える取り組みなんかもしています。おやき製造会社からの依頼で受託研究を行っていて、おやき工場の見学からやっているんですよ。
ゼミだけでなくこういった活動もしながら、学生の食に対する関心を少しずつ高めるようにしています。

実践的な教育を目指して
――郷土料理に関する活動を中心に、精力的に地域に出て学ばれているのですね。そんな学生さん達は、その後どういった進路に進まれるのですか。
中澤先生:栄養士の資格を取って、6割近くが食品会社などの食品関係に進みます。2割程度が病院や福祉施設、残りの2割が保健所や栄養教諭ですね。色々な道に進む学生たちですが、私は学生たちが料理を嫌いにならないようにすることが教える上で一番大切だと思っています。日々様々なことが起こり、大変なこともたくさんあると思いますが、結局自分で料理することが美味しくて安くて安全だということ。今すぐはそのことがわからなくても、そのうち感じてくれればいいなと思って教えています。
管理栄養士養成コースなので管理栄養士の資格を取ることがゴールではあるのですが、日々の授業にしてもゼミにしても、資格試験に合格することだけが目的になってはいけないと思うんです。もちろん一定の知識を学生たちは身につけなければいけませんが、なるべく自分たちの生活に関係のあることを考える時間を取るようにして、学びを身近なものにするよう努めています。調理実習室で食べたり舐めたり匂いを嗅いだりして。やっぱり食べることが絡んでくるからこそ、すごく楽しく学べると思いますね。
――管理栄養士の資格を取るためだけの学びにさせない、そんな中澤先生の強い想いが伝わってきました。ありがとうございました。