気候変動が農業に与える影響が日本でも顕著になっている中、地域特産品の栽培地では、品質の維持や収量の安定化が大きな課題となっています。その一例が、茨城県笠間市で栽培されている栗です。近年の気温上昇によって栗の生育や品質にも深刻な影響が及んでいるとされ、地域農業の将来に不安を抱える声が生産者より挙がっています。
このような状況に対応するため、茨城大学 農学部の井上栄一教授が取り組んでいるのが「気候変動に対応した笠間産『栗』の品質安定化プロジェクト」です。井上教授は果樹園芸学の専門家として、栗の栽培環境や品種間の交配特性を科学的に解明することで、地域農業の課題解決に取り組んでいます。
このプロジェクトでは、地域の生産者や行政との連携を通じながら気候変動が笠間産の栗の栽培へ与える影響を詳細に調査し、品質の向上と安定化を目指しています。プロジェクトの過程と展望を井上教授にお聞きし、気候変動の時代における農業の可能性を探ります。
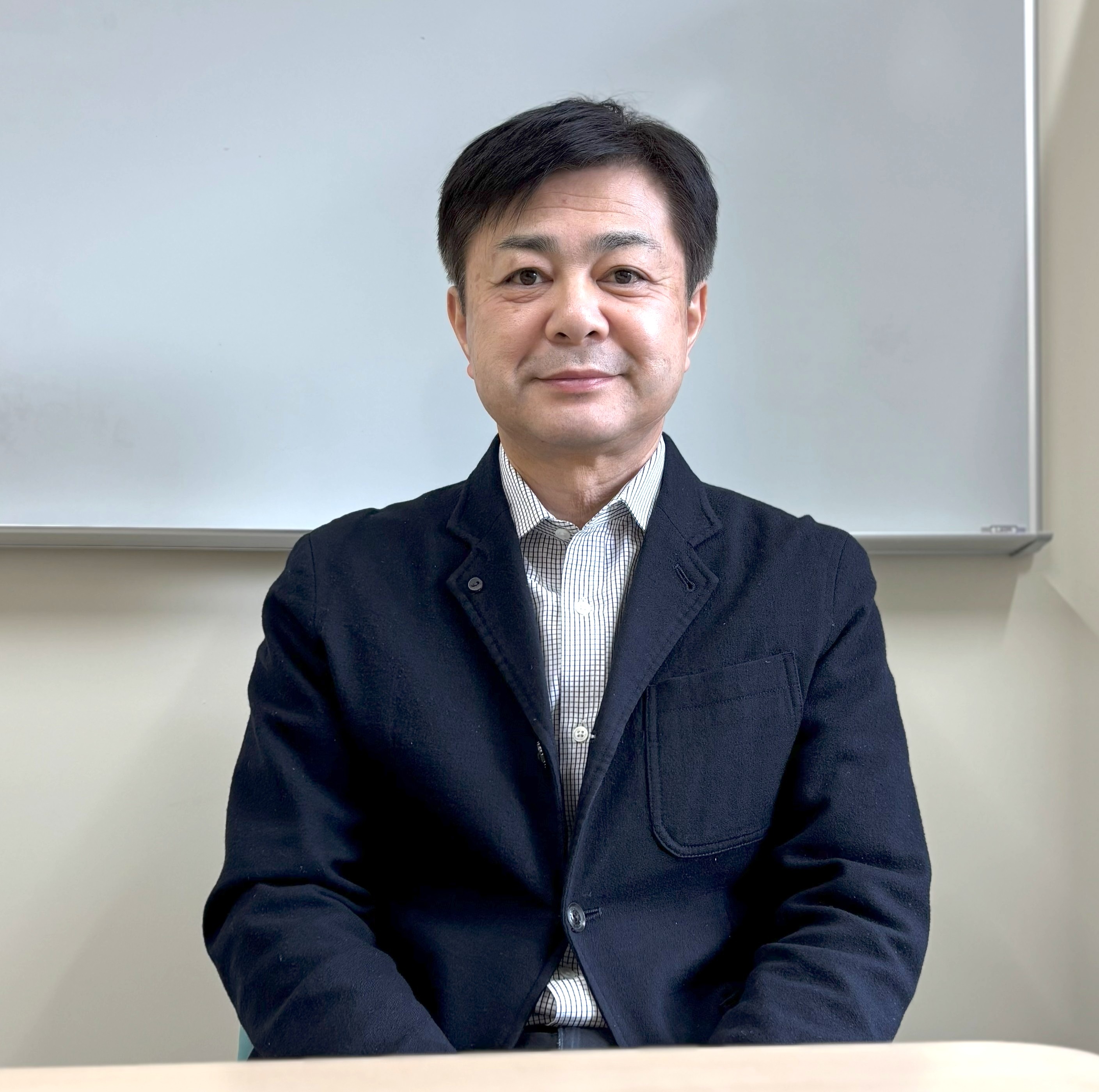
井上 栄一 先生
茨城大学 学術研究院 応用自然科学野 教授
担当は農学部・大学院農学研究科。専門は園芸科学。東京農工大学大学院 連合農学研究科 博士課程修了。博士(農学)。2007年、茨城大学に農学部准教授として着任。2016年より教授。東京農工大学大学院連合農学研究科教授を併任。主に果実や野菜の品質向上や利用価値の推進を目指し、クリやナシといった果樹などを対象に研究を進めている。
茨城県特産でもある栗という果実の特徴

私は大学教員として、これまで一貫して園芸学を専門に研究してきました。特に果樹園芸学、つまり果実を生産する樹木を対象とした分野を中心に取り組んでいます。
茨城県において、栗は梨と並ぶ主要な果実であり、中でも笠間市は県内有数の栗の産地となっています。過去の市町村合併により、同じく栗の産地である岩間町と一つの市となったことで、現在の笠間市はさらに大規模な栗の産地として知られています。
栗の生育は、光合成だけでなく、日中に作られたデンプンを夜間に蓄積する過程が重要です。しかし、気温の高い環境下ではこのプロセスが阻害され、果実の発育が順調に進まなくなってしまいます。特に、夜間の気温が下がらない環境はデンプンの蓄積を妨げ、栗の品質低下の一因となっているのです。
これは、気温の変化がお米の味に大きく影響することにも近しい現象です。例えば、新潟県の良食味米が美味しいとされる理由の一つに、昼夜の温度差が大きいことが挙げられます。しかし、近年は夜間の気温が下がらない状況が増え、米の味が低下していることが指摘されています。
とはいえ、必ずしも気温が低い地域が栗の栽培に適しているかと言うと、そう単純なことではありません。寒さが厳しい土地では、冬場に凍害が発生し、幹が一度でも傷つけば病気を引き起こしてしまう可能性があるためです。
特に、植えたばかりの若木は寒さの影響を受けやすく、初期の成長が阻害されることがあります。このように、気温が低すぎる地域を栗の適地とすることは難しいと考えられます。
反対に、暖かい地域が適地になるとも言い切れません。栗のような落葉樹が正常に発育するためには、ある程度の低温環境も必要となるため、沖縄のような温暖な気候も育ちにくいのです。そのような理由から、西日本では熊本に標高を活かした栗の産地がありますね。
現在、私が栗の研究に取り組んでいる笠間市は関東平野の一部にあり、標高は低いものの、同じ関東平野に属する千葉県や埼玉県よりも緯度が高く、また、茨城県周辺の平均気温は13度から15度と、栗の生育に適した条件が整っているのです。
栗の品質低下と気温上昇。課題解決に向けプロジェクトが発足

しかし、近年の気候変動により、夏場の高温が続く年には気温上昇の影響だと考えられる栗の品質低下が、笠間市だけでなく全国各地で生じています。
ここで言う「品質低下」とは、食味や大きさの均質性をはじめとする生育全体の状況が悪い方向へ変化していることを指します。ただし、これらの変化のすべてが気温上昇のせいであると断定することは難しく、慎重な分析が求められています。
その理由として、栗は収穫後に低温貯蔵し、糖度を高めてから味を測ること、更に、栗は生で食される果実ではなく、収穫後に何らかの加工をされることが挙げられます。梨やリンゴのように収穫後すぐに食味を確認する果物とは異なるのです。
そのため、食味評価には一定のバイアスが含まれている可能性を否定できないものの、現場では「温暖化の影響で作況が悪化し、味も落ちてきている印象がある」という声が多く聞かれます。確かに、栗は初夏から夏にかけて生育が最も進むため、この時期に光合成がしっかりと行われず、実が充実しなければ品質低下に直結するだろうということは想像に難くありません。
このような背景から、「令和6年度茨城大学社会連携センター地域支援プロジェクト」の一つとして「気候変動に対応した笠間産『栗』の品質安定化プロジェクト」が立ち上げられ、笠間市を拠点に取り組みが進められることになりました。
当初は生産者の方からの「高温耐性の品種を作りたい」というご相談があったのですが、まずは市内で育成されている栗の主要品種に高温耐性の遺伝子型が存在するのかを調査する必要がありました。品種改良を進めるにしても、栗の育成において高温がどのように影響するのかのメカニズムを明らかにすることが重要です。
この検討過程で私たちが注目したのが、栗の結実には他家受精(たかじゅせい)が必要である点でした。栗は、自らとは異なる個体の花粉を受粉しなければ実が成りません。その上、栗の果実は種子の子葉の部分であり、1粒ずつが実は異なる遺伝子型を持っています。これは、受粉に使われた父親品種の影響を少なからず受けているためです。栗の果実における遺伝子の組み合わせが品質にどのような影響を与えるのか、そして交配する栗によって遺伝子型にどのような違いが生まれるのかということが、研究を進める上での重要な視点となっています。
花粉の組み合わせが栗の品質を左右する?最新の取り組みとは



栗は1粒ずつ遺伝子型が異なるという特徴を踏まえ、次に私たちが着目したのは、気候変動によって栗の開花時期が変化してきている点でした。
例えば、これまで品種Aと品種Bは開花時期が一致しており、確実に受粉が行われていたとします。しかし、温暖化の影響によって開花時期がA、Bより遅かったはずの品種Cが早く咲き始め、同時期に開花している可能性がある、という仮説を立てました。
つまり、温暖化による開花時期のズレがそれまでとは異なる品種との交配を引き起こし、それが栗の品質変化の一因となっているのではないかということに着目したのです。
現代の遺伝子解析技術では、どの花粉が受粉に関与したのかを簡単に特定できます。そこで、各品種が植えられている位置関係を考慮しつつ、交配の可能性のある組み合わせについて品質の比較評価を行う試験を進めています。
この解析結果に基づき、品種間の相性と品質の関連性を調べることが、今回の研究目的です。具体的には、特定の組み合わせで受粉した栗の食味、大きさ、外観などを詳細に比較し、品質にどのような影響が出ているのかを明らかにします。
今年(※取材時2024年)の秋に収穫が終了し、1ヶ月間の貯蔵期間を経て、現在は実際に品質調査を進めています。まだ具体的な結果をお伝えすることはできませんが、一部の果実において「不適切」と判断される品質の低い栗が確認されました。
従来であれば、販売に適さないとされる果実は全体の数パーセントに留まることがほとんどでした。しかし、特定の花粉の組み合わせでは、その割合が数十パーセントに増加するケースが確認されつつあります。
更に、不適切な状態を引き起こす可能性が高い品種間の組み合わせも、徐々に明らかになってきました。この研究が順調に進めば、栗の品質向上や生産者支援に繋がる、新たな知見を得る大きな一歩となるかもしれません。
研究成果がもたらす、栗産業の革新への期待

今後、さらに研究が進み、品質低下の要因や高温環境に耐えうる遺伝子型などが明確になれば、さまざまな対策が考えられます。例えば、新しい栗園を開園する際は必ず交配する相手品種を一緒に植えることが求められますが、適さない品種同士の組み合わせを低減させることが可能になるだろうと考えています。
特に期待しているのは、いわゆる「最高の栗」を生む品種の組み合わせが見つかることです。たとえば、糖度が著しく高くなったり、果実重量が最大化したりする組み合わせが見つかれば、生産現場や産業界に大きく貢献できるでしょう。高品質な栗の生産性が上がるだけでなく、ブランド力向上にも寄与することを期待しています。
また、高温の影響を受けづらい品種を育てられる可能性もあります。そのようなことが明らかになれば、生産者にとって非常に有益な情報となり、現場の栽培方法にも革新をもたらすのではないでしょうか。
一方で、栗の研究者は非常に少ないのが現状です。日本において、栗は古くから栽培されているものの、梨やリンゴ、ブドウに比べると、研究の歴史が浅い果実なのです。
その背景には、栗がこれまで産業的な集約栽培の対象ではなかったことがあります。かつては山野や田畑の境界に植えられることが多く、大規模な栗園として育てる文化があまり発展してきませんでした。そのため、他の果実に比べて研究者の数も少なく、研究自体が進みにくい状況がありました。また、単価の面でも、栗はリンゴや梨、ブドウなどの専売品目と比べて高いわけではありませんでした。
しかし近年、栗の市場価値は大きく変わりつつあります。リンゴや梨などの果実は単価が下落傾向にある一方で、栗は上昇しているのです。この理由の一つに、収穫後の貯蔵技術の進化や加工用途の拡大が挙げられます。デンプン系の作物である栗は、収穫後の保存や加工によりさらに価値を高めることが可能です。このような点から、栗の活用や産業としての発展は良い方向へ進んでいると感じています。それに伴って栗の研究者も増えてきてくれることを願います。
笠間産「栗」の未来へ向けて 地域と共に歩む挑戦

大学で果物の研究をしていると、時折「この果物の研究をしたいです」と明確な目的を持って入学してくる学生もいます。今年度は「将来は栗農家になりたい」という学生も入学するなど、学問を修めながら生産者を目指すという熱心な若者が増えてきたのは大変喜ばしいことです。
彼らもプロジェクトに参加し、一緒に調査に取り組んでいます。たとえば、笠間市の方からご紹介いただいた栗園で育てられている栗を品種ごとにマッピングし、特定の品種が交配している可能性が高いエリアを選び、収穫調査を行っています。
栗の交配は風媒が基本とされ、一部は虫媒も関与しています。ただし、孤立した1本の栗の木では果実がつかないことが報告されているように、長距離を花粉が飛ぶことは稀だと考えられることから、近隣の栗の木が交配に強く影響している可能性は高いと言えます。この仮説に基づき、収集した栗の一部を大学に持ち帰り、遺伝子解析を通じて詳細な調査を進めています。
生産者の方々も、このプロジェクトに興味を持ってくださっていると感じます。特に積極的にご協力いただいている生産者の深澤さんは、当地における栗栽培のリーダーのような存在です。こうした現場の方の知見やご協力があるおかげで、研究を進められています。生産者の方々との連携は、研究成果を現場に還元する上で非常に重要です。
他には、公的機関とも連携し、交配時期の予測や品種選定に役立つ栗の開花データを多くの品種で詳細に記録するなど、多方面の方々のご協力をいただきながらプロジェクトを進めています。特に、笠間市の「栗ブランド戦略室」とは連携を密にしています。他にも、笠間地域の農業改良普及センター、茨城県農業総合センター園芸研究所とも関わりを持っています。多くのご協力をいただくことで研究の幅が広がり、より多角的な視点から課題に取り組むことができています。
こうした研究は、1年だけでは充分な結果を得ることが難しい場合があります。その年の気象条件や環境の影響を受けやすく、「たまたまその年だけで得られた結果ではないか」と疑う余地があるためです。2年から3年程度を一区切りとし、中長期的かつ継続的な取り組みを通じてより信頼性の高い結論を導き出すことが、引き続き必要だと考えています。
栗の育成にはコストも時間もかかるため、短期間のプロジェクトで成果を出すことは容易ではありません。しかし、このプロジェクトを通じて研究が進めば、将来的には栗の栽培業界に対して有益な提言を行える可能性があります。生産者の方々にも研究成果が役立つことを目指し、今後も取り組んでいきたいです。
更に、品質向上による差別化が進めば、栗の単価も上がっていくことが考えられます。中でも特に注目されているのが、栗の加工です。元々の良質な素材を生かし、加工品として付加価値を高めることで、品質だけでなく収益性も向上することが期待されます。
また、如何に品質の高い栗を作るかに加え、それをどのように売るかという経営戦略も、今後の発展においては同じくらい重要です。この2つの視点が揃わなければ、産業としての持続性や収益性を確保することは難しいでしょう。
このプロジェクトを通じて、笠間市をはじめ茨城県における栗栽培の品質が向上し、他ブランドとの差別化ができるようになればと思っています。



