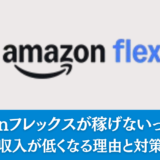中山間地域の人口減少やライフスタイルの変化によって、山に住む生き物たちと人間との関係性は移り変わってきました。中でも食べ物を求めて鹿や猪が里山の畑を荒らす「獣害」は、近年深刻な問題となっています。獣害の解決が難しい要因の一つとして挙げられるのが、猟師の減少です。罠や銃で害獣を捕獲する猟師の世界では高齢化が進んでおり、若者の参入も多くありません。猟師になるには専門的な知識や資格が必要不可欠である一方、生業として成立させることもまた難しい現状もあります。知識や人脈のない状態から飛び込むことは、かなり難しい業界だと言えるでしょう。
そんな中、三重大学の狩猟サークル「トラッパーズ」が話題を呼んでいます。このサークルではなんと学生たちが現役の猟師に教わりながら狩猟活動を行っています。いったいなぜ狩猟活動を行うサークルを結成したのか、またどんな学生が活動しているのか。全国的にも珍しいこのサークル活動にまつわるお話を、部長であり三重大学生物資源学部生物圏生命化学科に所属する奥村亮介さんに伺いました。
コロナ禍で一度解散したものの、再結成
奥村さんが通う三重大学には、元々上ノ村(津市白山町)で活動する「地域貢献サークル Meiku」がありました。その中から、上ノ村の集落内で獣害対策に関わっていたメンバーによって平成28年に結成されたのが「狩猟サークル トラッパーズ」です。トラッパーズは害獣を駆除・捕獲し、獣害被害を削減するために立ち上げられました。上ノ村の猟師に指導を受けながら狩猟活動を行い、集落内にある侵入防止柵の点検・補修など害獣被害削減に奔走していたそうです。
ところが令和2年、新型コロナウイルスの影響で後輩への引き継ぎを十分に行うことが出来ず、一度解散。再び令和3年度に狩猟や獣害対策に興味のあるMeikuメンバーらによって、現在のトラッパーズが結成されました。一度途絶えてしまったことで狩猟や行事のノウハウが失われたものの、もう一度上ノ村の猟師に教わりながら獣害被害の減少のために活動しています。
「初代のトラッパーズが結成されたのは私が入学する前でしたが、大学のホームページで見ていたのでサークルのことは知っていました。」と話す奥村さん。三重県出身で元々生物に興味があり、大学では生物について学びたいと考えていたそうです。そこで見つけたトラッパーズ。何かしらの形で生物に関わっていたいと思っていた奥村さんは、入部をすることに決めました。獣害被害が三重県内で深刻だということも知っていました。以前調べたところによると、平成30年には約2億3300万円もの被害があったそうです。
県内で広がる獣害被害をなんとかしたい。そんな想いもあったのでしょう。

獣を捕獲し、ジビエ肉や毛皮として活用
トラッパーズの活動内容は主に狩猟です。令和6年度は1年を通して三重大学内の農場を中心に有害鳥獣捕獲を行いました。令和7年度以降は、農場内での活動を引き継ぐことができるように手続きをしているところだといいます。
「大学の農場で活動をさせてもらえることは、とてもありがたいと思っています。」と奥村さん。狩猟期間である11月から翌年2月は上ノ村でも狩猟活動をしているそうですが、他の季節には狩猟が行えません。年間を通して狩猟に関わりたいトラッパーズと獣害に苦しむ三重大学とは、良き協力関係のようです。
とは言え主な勉強の場は上ノ村です。猟師に教えを請いながら罠を設置し、動物がかかっていればとどめを刺します。罠設置中は基本的に毎日見回りを行うそう。銃を持って山に分け入り獣を仕留めるイメージが強い狩猟の世界ですが、実際のところはかなり地道で大変な活動のようです。
捕獲した獣は解体し、ジビエ肉を部員で分けて食べているそう。皮はなめして毛皮に加工し、角や骨はキーホルダーやアクセサリーに。獣を退治して終わりではなく、無駄なく活用する方法を探ります。「中には剥製や骨格標本まで作る部員もいます。」と奥村さん。



罠資格の取得を目指して
サークルで行う狩猟活動は、罠猟が中心です。2025年4月現在、部員7人のうち3名が罠資格を持っているそう。罠猟では餌を仕掛け、罠に踏み入った獣の足を締め付けて捕らえます。
罠資格取得にも積極的に取り組むトラッパーズでは、学生自ら狩猟免許試験の対策講習会を行います。各都道府県の猟友会が開催する講習会への参加も推奨しているそうですが、サークル主催の講習会への参加のみで試験に合格する強者もいるのだとか。
また、県内で開催される獣害対策講習会や獣害フォーラムなどに参加するのも大事な活動の一つです。狩猟技術や獣に関する知識の向上のため、部員たちは日々励んでいます。


狩猟に興味のある若者は少なくない
資格のための勉強など日々の見回りなど、楽しいだけではないように思われる活動の数々。いったいどんな学生たちが入部しているのでしょうか。
「やはり生き物に強い関心がある人や、実家の農家での獣害問題を解決したいという想いを抱いている人もいます。でも中には獣害問題そのものに興味があるというより、単にジビエを食べたいと思って入部してくる人もいます。」と奥村さん。
理由は人それぞれですが、狩猟に興味を持つ若者は少なくないと感じているそうです。
地域の活性化にも繋がる


トラッパーズの活動は、単に狩猟を行うことだけが目的ではありません。そこには地方の行く先を見据えた想いがありました。
「猪や鹿による被害が深刻化している背景には、やはり狩猟従事者の減少や高齢化があると考えています。狩猟業界の存続には若者の参入が必要不可欠です。だからトラッパーズが若者と狩猟活動を繋げる役割になれたらいいなと思い、活動しています。そしてトラッパーズで狩猟技術を身に着けた学生が、卒業後も狩猟活動を続けるために獣害被害のある地域に移住すれば、地域の活性化にも繋がります。」
実際に初代トラッパーズのメンバーの中には上ノ村に移住した人もいるそう。着実にサークルの存在が地域に良い影響をもたらしています。
狩猟活動をする上で農場職員や地域住民との関わりも大切だといいます。
「トラッパーズの目的は、獣害被害の削減はもちろんのこと、『集落と連携した獣害対策による地域貢献』や『安全狩猟術の向上』にもあります。罠の設置状況や捕獲の報告を定期的にして注意喚起を行い、職員や住民の方からは被害・目撃情報を教えていただくことが大事です。」
それは、必然的に被害を受ける立場と狩猟する立場とが協力しあい、獣害対策を行っているということ。卒業後の移住は人口増加に繋がるだけではなく、団結して獣害対策を行うことで地域住民の結びつきを強めることにもなるかもしれません。
ただ、猟師を本業にするのではなく趣味で続ける人が多いのだとか。やはり捕獲量の不安定さや狩猟にまつわる様々な制限が原因としてあるようです。
奥村さんも卒業後は県内での就職を考えているといいます。
「しかし何かしらの形で狩猟を続け、地域に貢献していきたいです。他の部員たちもどういう形かはわかりませんが、狩猟に関わり続けるのではないかと思っています。」
最後に、トラッパーズに対する奥村さんの想いを伺いました。
「狩猟活動に興味を持っていたとしても、専門的な知識や猟師さんとの繋がりが必要なため、一人で狩猟を始めるのは非常に難しいことです。また、私が先輩から狩猟を学び、先輩が上ノ村の猟師さんから学んだように、狩猟活動を行う上で教え手の存在はとても重要です。
だから、自分自身が狩猟活動を人に教えられるようになること、そして学生と狩猟活動を繋げる場としてトラッパーズを続けていくことに力を入れて行きたいと思っています。必ず次の世代に繋いでいきたいですね。」
淡々と語ってくれた奥村さん。静かに、しかし確かに、今後の中山間地域にとって大切な役割を担っています。