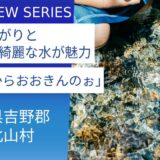「紀」伊の「北」と書いて紀北町。三重県にありながら、古くは紀伊の国の東北端に位置する町です。面積の9割が森におおわれ、伊勢から熊野三山につづく道中にあることから、熊野古道のまちとしても知られています。
紀北町地域おこし協力隊として活躍する東谷和秀さんは、京都府京都市から三重県紀北町に移られて今年で3年目。移住定住コーディネーター、空き家バンクの運営管理をされています。東谷さんがまもなく退任を迎えるというタイミングで、田舎暮らしに憧れて紀北町への移住に至った経緯や、メインの活動となる空き家バンク運営に携わったきっかけなどを伺いました。
田舎暮らしに憧れ、単身紀北町へ

――以前、紀北町を含む東紀州のあたりを、自転車で旅したことがあるんですけども。海がめちゃめちゃ綺麗なとこですよね。
そうですね。海は東紀州エリア全体的に綺麗ですね。
紀北町や尾鷲市は崖っぽい地形で。熊野市から和歌山よりは比較的、砂利の浜が続いています。
――はい、思い出しました。その海に惹かれて移住されたのですか?
というより、妻の実家が熊野市だったので。全然知らない土地ではなく、多少馴染みがありました。
――お育ちは大阪府高槻市ですね。京都と大阪の間ぐらいに位置する高槻市は、現在いわゆるベッドタウンとして知られていますが、東谷さんが育った頃はどんな様子でしたか。
風景は随分変わりましたね。現在はビルやマンションが多いですが、僕が小さいころは阪急電鉄の駅高架は工事もしていませんでした。
淀川に近いとこに住んでいたのですが、小さい頃は田んぼもたくさんあったと思います。田んぼはもう今となっては減って、住宅がどんどん建っていきました。その割には、最近になったらそのエリアも「ちょっと空き家増えてきたな」っていう感じもあって。
27歳で結婚するとき、京都市伏見区に移りました。結婚して住まい探した時に、たまたま見つけた物件が伏見区にあって。また引っ越してもいいかなって言いながらも、結局結婚してからはずっと京都にいました。
今は大学生の子ども2人と妻は京都にいて、単身赴任的な感じです。
――奥さんとお子さんは京都で、東谷さんは紀北町に。そういう形式を選択されたのはなぜですか?
子どもたちは大学卒業後、次のステージでどういう生活になるかわからないし。自分も子どもが卒業してから動いていたら、もう年も年だから。もともと田舎暮らしに憧れていたので、地域おこし協力隊っていう制度をうまく活用しながら、次のステージに向けた準備期間というつもりでした。
――高槻市と京都市は、いわゆる大都市圏ですよね。田舎暮らしへの憧れを今実現しているということですか?
そうですね。妻の実家が熊野だったのいうのもありますが、よくよく考えてみると、子どものころ、自分も父親が住んでいた奈良だとか、母方の広島の田舎に行ったりしていました。日常でも父親とよく山とか川とか、登山とか釣りとかに行っていました。その辺から田舎に馴染みがあったというか、「いつかは自分も」って思っていたのかもしれません。
あと、性格的にも都会の空気より田舎の空気の方があっていると思います。住み始めたら余計にそう思うようになりました。
紀北町は山も海もあって、自然環境はもちろんいいです。あとはなんというか、都会よりも自分の時間がちゃんと作れるというか、雑音が少ないというか、そんな感じがありますね。

――自分と向き合うにあたって、余計なものが少ないということでしょうか。都会と田舎では、全然情報量が違いますよね。
そうそう。都会では、僕が取りに行かなくても勝手に入ってくる情報がたくさんあったんですけど、田舎ではこっちから取りに行かないと情報が手に入らない。逆にそういう方が自分には合っていて、選択肢が多すぎるとしんどいと感じてしまいます。
――移住してから、どういう情報を取りに行く傾向がありますか?
地域おこし協力隊としての活動のミッションである移住・定住とか、空き家バンクの運営管理の情報ですね。その中でも空き家の利活用に携わっていきたいので、紀北町を中心とした東紀州で、空き家を活用したワークショップや、それに関するイベントなどの情報があれば、取りに行っています。
移住・定住というテーマは幅広く、地域との繋がりが大事になってくるので、「地元の人といっぱい出会えるんちゃう?」とか「異業種の人と会えそうやな」と思ったら積極的に参加しています。
地震がきっかけになった、空き家への関心

――大阪でも元々建築関係のお仕事をされていたそうですが、そのころから空き家への関心があったんですか?
そうですね。高槻では創業50年は超えた地元の工務店にいました。その工務店ではリフォームもリノベーションも新築もしましたが、2018年に、大阪府北部地震があったんです。地震をきっかけに、既存住宅の耐震診断とか、耐震改修の件数が一気に増えました。2015年に空き家対策特別措置法が全面施行になったニュースから空き家に関心はありましたが、耐震診断の調査に出かける機会が増える中で、既存住宅や空き家の現状を知って。そこから特に気になり出しました。
――都会の空き家事情で、田舎と違うところはありますか?
正確にはわかりませんが、危険な空き家の件数だけで言ったら、田舎の方が多い気がします。「なんでこんなになるまでほっとったんやろう」ってとこもあります。だからといって、すぐ所有者を見つけて連絡するということが、スピーディーにできない点が、もどかしいところです。
――所有者不明だったり、親御さんが亡くなって息子などに継がれたけれども、都会に住んでいて連絡取れなかったりという話は、よく聞きますね。紀北町内の空き家の数は今、どのくらいですか?
多いですよ。だいぶ前に行った調査では、多分まだ4桁まではいってないぐらいの数ですね。ただ、その割には空き家バンクに登録している物件が少ない。物件が所有者さんの意識から完全に消えている可能性もあります。
そこで地域おこし協力隊として1年目の後半あたりに、紀北町内の店舗やガソリンスタンドなどに、所有者さん向けにポスターを飾らせてもらいました。あとは、固定資産税の納税通知の中に、市からチラシが入るんですけど、そこに一文足してもらうとか。所有者さん向けに登録促進を促す動きはしていますね。
登録件数で言うと、去年度と比べて今年度は1.7倍ぐらいになりました。ポスターの効果か、チラシの効果か、もしくは相続登記の義務化などの理由も考えられますが、今年度は登録の動きで忙しかったです。
――登録件数が増えたのは、町としては良かったですよね。
そうですね。物件が入っては売れ、というのはいい傾向だと思いますね。
子育て世代の田舎暮らしを増やしたい
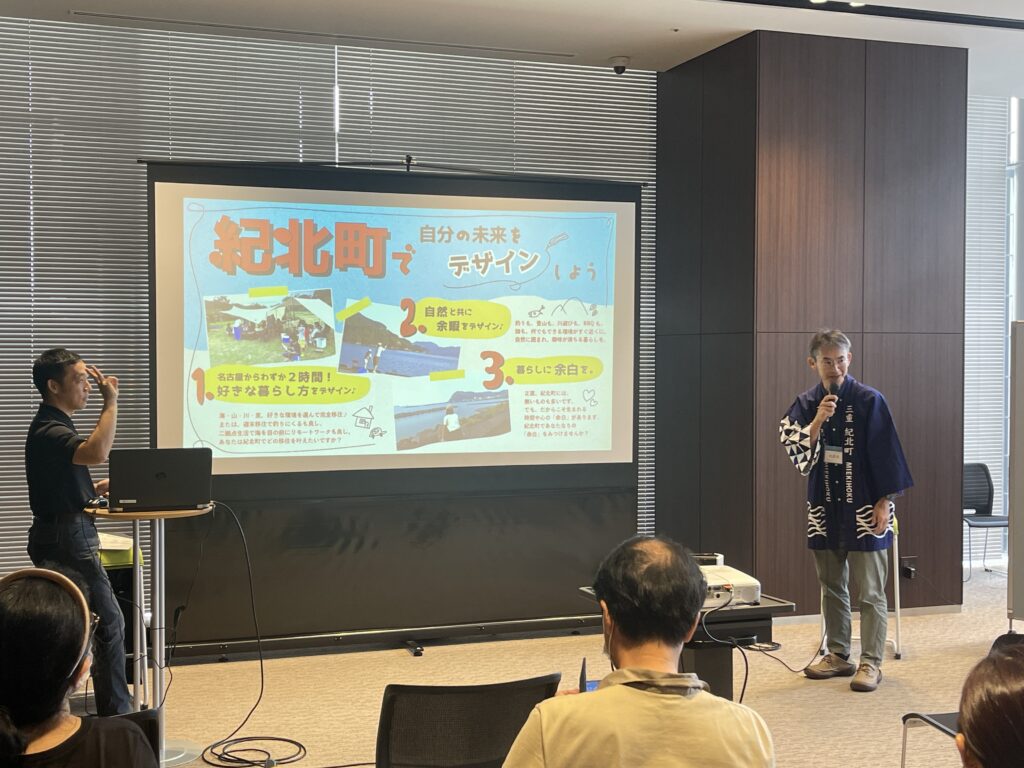
――売れていく空き家はどういう物件が多いですか?
やっぱり見る人は目が肥えているので、立地・価格・建物の状態がそれぞれいい空き家は、情報が出たらすぐ売れます。ただ、紀北町は公共下水がないので、トイレは汲み取り式か浄化槽になるのですが、物件によっては浄化槽にすら変えられない物件があります。ほかにも、漁港に近い地域には、駐車場がない物件もすごく多い。そういう物件は安くても残りがちですね。
――条件が合えば売れるということは、田舎暮らししたい人はずっと一定数いるということですね。
はい。ただ、引退して余生を過ごそうという年配の人は多いですが、もう少し年齢層的に子育て世代が来てくれると嬉しいですね。でもそこは、本人の気づき次第です。都会が好きな人はいいけれど、都会でしんどい思いをしている人に田舎の魅力に気づいてもらうために、今後は情報発信が大切になってくると思います。
とはいえ、毎日忙しく都会の職場で働いている人に、田舎で暮らす選択肢があることを気づかせるのも、なかなか難しいとは思います。ただ国も、これから二地域居住などを進めていこうという動きもあるから、情報の出方も変わっていくのではと期待しています。

――東谷さん自身は、都会で忙しく働く生活から180度転換しましたが、それは思い切った大きな決断というわけではないのでしょうか?
大きな決断ではあったんですが、心の中では3、4年ぐらい前からタイミングを伺っていました。こんな年で移住してもいいのかなという葛藤があっても、人生1度きりと思ったら、とりあえず動いてみようみたいな感じで、思い切って出てきましたね。
前の会社でも、同僚が田舎に家を買った話などを聞きました。そういう会話の中で、「自分も田舎に住みたいんだったな」っていうのは、前職の同僚に気づかせてもらいました。ただこれは今言ってもしょうがないことですけど、もっと子どもが小さい時に田舎に移住していたら、もうちょっと違ったかなと思いますね。
――お子さんは好みとしては都会派ですか。田舎派ですか?
今はがっつり都会派ですね。自分から呼び寄せても絶対嫌がるから、本人次第で「田舎もありやな」って言わない限り、こっちからは誘わないようにしています。今は普通に大学に行ってますけど、地方の企業への就職とか地方で起業するとかっていう頭は全然ないと思います。
――奥さんはどうですか?
妻はね、移住に100パーセント賛成してなかったですね。ただ、今協力隊3年目に入って、なんとなく「また私、田舎に戻るとは思ってもみなかった」って、そういう言葉を帰省した時にぽろっと言うのを聞くと、ちょっとずつ認めてくれている気がします。
協力隊で広がった視野で、また別の世界へ

――東谷さんが地域おこし協力隊でやり残したことがあるとしたら、何ですか?
自分はずっと建築畑でしたけど、仕事をする中で地域創生とか活性化とか、建築業じゃないいろんな方と繋がっていく中で、仕事の幅っていうか視野みたいなのが、ぱっと開けた感じがしたんですよね。ずっと建築業で狭いとこにいたのが、こっちに来て一気に広がって、いろんな人と会って、いろんな考え方聞いて。視野が広がったことはすごい自分にはプラスかなと思っています。
だから、建築業や空き家の件でやり残したことがあるかはわからないですが、退任後も移住・定住とか空き家利活用に絡んでいくほか、紀北町に来る時は想像もしていなかった農業にも、ちょっと携わる予定になっています。協力隊3人で、森農人(mori nous hito)という任意団体を作りました。そこで、休耕田になっている土地の復活を試してみる予定です。米農家さんの全面協力で、稲作をやります。あと、紀北町でしか作っていない郷土料理の漬物であるくき漬けを作ります。田んぼだった場所を畑に変えて、くき漬けのもととなる八ツ頭を栽培するという挑戦です。こちらもくき漬けを作っている農家さんにご指導等で大変お世話になっています。これらの挑戦はインスタグラムで配信していますので、フォローいただけると嬉しいです。(https://www.instagram.com/mori_nous_hito/)

――都会より田舎に来た方が、世界が広がるって面白いですね。
いや、でも、実際そうです。人口も高槻市と比べたら20分の1以下ぐらいなので、やっぱり田舎の繋がりは深く、太いと思います。それに、視野を広げないと、仕事的にも広がっていかない。例えば建築設計事務所の仕事だけでは、田舎で暮らせるわけがないっていうのは、自分でも来る前からわかっていました。だから、その他に何の仕事ができるかをいろいろ探せるかは、重要です。紀北町には一次産業があって、ちょっとした季節労働、マルチワーク的な働き方があります。お金持ちにはならなくても、普通に暮らせる基盤は築かないといけないですよね。
退任以降どこまで安定した収入が見込めるかなど、不安要素はまだまだありますが、退任までの期間でできるだけのことはしたいと思っています。
――この後も紀北町で暮らされるのですか?
一応こっちで暮らす予定にしています。ただ逆に退任後であれば、紀北町に囚われなくてもいい面もあります。東紀州の人との繋がりが多いので、東紀州中心になっていくのかなと思いますけど、三重県全域の地域おこし協力隊とも繋がりがあるので。ちょっと北の方の大台町、大紀町とか、伊勢の手前ぐらいとか、三重県全域まで広がっていくかもしれません。
また、カフェとかやりたいと思ったときにいつでもできるように、食品衛生責任者養成講習会を受講しました。紀北町で言えば、ゲストハウスとかコワーキングスペースとか、若者が集まるとか、地元の人と移住希望者が集まる場所とか、そういうのがまだまだ少ないんですよ。だから、紀北町内でも増やしていきたいなと思っています。
――東谷さん、ありがとうございました。