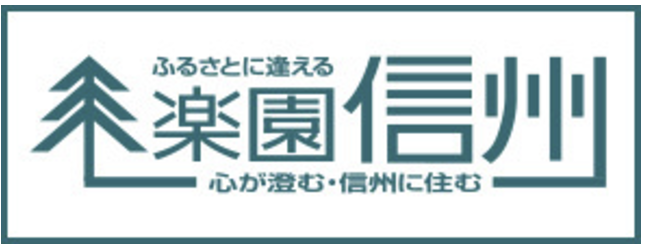「移住したい県ランキング」で常に上位に入る長野県ですが、若者を大都市圏に吸い取られ、高齢者はどんどん亡くなっていくという形での人口減は止まらず、2024年、およそ50年ぶりに人口200万人を割りました。
そうした状況で、行政としてどのように県下の産業と雇用の維持・発展に関わっていくのか。
長野県産業労働部 産業人材育成課 人材育成支援係長の瀧澤貴之さんと、同部 労働雇用課 雇用対策係長の岩下裕昭さんにお話を伺いました。

長野県の産業構造

瀧澤貴之さん(以下、瀧澤):
長野県の産業構造ですが、製造業が中心となっています。その中でも、情報機器や電子部品など、加工組立型産業に特化しています。
売上高で見ても、製造業が全産業の約35%と最も比率が高くなっています。その後に卸売業・小売業、建設業と続き、それらと製造業を合わせて、県内全産業の売上高の約70%を占めています。
綺麗な水が豊富にあるという背景から、製造業の比率が高くなっているものと考えられます。
県としてリスキリングを推進

人材育成支援係長 瀧澤貴之さん
瀧澤:
人口減少社会が本格化し、特に生産年齢人口が大幅に減っていく中で、やはり色々な産業で人手不足が深刻化していくことが予想されます。
今から人口を増やしていくのはなかなか難しいですが、それでも持続的に産業発展を図っていくためには、1人1人が職業能力を高めて生産性を向上させていくことが重要でしょう。限られた人材を有効に活用していくためには、企画系の仕事や、その人にしかできない高付加価値の業務に集中させる必要があると思います。
現在、国の方でもリスキリングには力を入れていますが、そういった社会人の学びによって、新しい分野のスキルや知識を身に付けたり、現在持っているスキルを高めていくということが重要になってきています。
特に最近だと、技術革新が進んでDXが進展している中で、これまでとは異なった働き方も求められています。
そこで、長野県としては令和4年度から「デジチャレ信州」というものを実施しており、主に求職者の方を対象に、デジタル分野のスキル習得と就職支援を一体的に行っています。
その中では、若者を対象とした正社員就職を目指すコースや、育児・介護などの事情がある方向けの短時間訓練コース、女性を対象にした企業でのインターンシップを経験できるコースの計3つのコースを用意しております。 参加された方からは、「未経験で成長分野であるIT業界へ就職するチャンスを得られて役に立った」といった感想を頂いています。
また、中小企業の在職者の方に対しては、技術や技能の向上、若手技術者の育成支援を目的に、工科短期大学校、技術専門校などでのスキルアップ講座を実施しています。
中小企業からは、やはり先ほど申し上げたような人手不足の状況で、「コスト面においてもなかなか社員のリスキリング推進はしにくい」というお話も伺っています。
なので、「なぜ、今リスキリングに取り組む必要があるのか」という部分を、講座の開催だけに留まらず、企業側の理解の促進もしていかなければならないと考えております。
雇用・就労面の課題

雇用対策係長 岩下裕昭さん
岩下裕昭さん(以下、岩下):
私からは、県内の雇用と就労の面についてお話しします。
瀧澤がお話ししたことと重なる部分もありますが、長野県における雇用・就労面の課題は大きく3つあると考えております。
1つ目は、若年人口の流出です。
長野県は非常に首都圏から近いということもあり、進学や就職で、10代後半から20代前半の若者が流出してしまっています。20代後半以降については転出よりも転入の方が多いのですが、やはり10代後半・20代前半の流出した人口については取り戻せていないという実態があります。
2つ目は、全県的な人手不足です。
有効求人倍率が全国平均よりも40ヶ月以上ずっと上回っている状態で、景気に関わらず1.3倍程度で常に推移しています。有効求人倍率の全国順位でいうと、大体いつも15位くらいに位置しております。人手不足の状態がずっと続いている状況です。
3つ目は、雇用のミスマッチです。
有効求人倍率は高いものの、一定して求職者が3万人を超えるような状態で推移しています。「希望する職種がない」とおっしゃる求職者の方がいる一方で、求人を出す企業側からも「なかなか良い人材が獲得できない」という声が聞かれます。
若年人口の流出に象徴されるような人手不足と、雇用のミスマッチ。これが長野県の雇用・就労面の課題として存在しております。
雇用のミスマッチ解消へ向けて

岩下:
雇用のミスマッチ部分の一例を挙げますと、やはり事務系の職種を希望される方が多いんですね。ところが、事務系の有効求人倍率は0.5倍程度で、求職者側がどれだけ希望しても、その半分くらいしか仕事がないという状態です。
その一方で、専門的な技術職であったり、建設であったり、警備などは有効求人倍率がずっと高止まりしています。
ですので、そういったミスマッチの解消を目指した施策も展開しております。
「地域就労支援センター」という長野県の総合的な就労支援の事業があるのですが、マッチングの強化ということで、特に障害者や高齢者、子育て中の女性といった就職困難者と呼ばれる方々に伴走支援をしています。
キャリアカウンセリングや面接の練習を実施し、就職がうまくいってからもアフターフォローをしております。
また、企業側には、「必ずしも本業フルタイムで人を雇うのではなくて、『短時間であっても働きたい』という方々に向けて業務を切り出すという手段もありますよ」という働きかけをして、ミスマッチを解消できるように取り組んでおります。
あとは、求職者側から「選ばれる企業」を増やす必要があります。
そのためには、まずは賃上げが非常に重要になってきますので、県としても賃上げに関する補助金を実施しております。
また、就職困難者の就業や社員の子育てを支援するなど、多様な働き方の受け入れ制度を整えている企業を県として認証する「職場いきいきアドバンスカンパニー制度」を設けております。
こういった認証を通じて、働きやすい職場づくりに努めている企業を見える化することで、求職者の方もそれまで希望していなかった職種であっても就職先として検討する可能性が出てくると思います。 今、認証企業は300社を超えていますが、これからも増やしていきたいと考えております。
多様な人材の労働参加と産業振興

岩下:
これまでは本業フルタイムという形での雇用が中心ではあったと思いますが、やはり働きたくても働けないような方がまだ一定数いらっしゃるということで、多様な人材の労働参加が求められています。
ますます人手不足が深刻化していく中では、やはりこれまでとは違った働き方を創出していくことで人手不足を解消していかなければならないでしょう。
また、それと合わせて、人手不足を補うにはどうしても企業の業務効率化、自動化であったり機械化であったりを同時に進めていかなければなりません。
さらに、職場の処遇改善、労働環境の改善も必要だと思います。 これらを同時に進めていく必要があると考えています。
瀧澤:
県として、そういった働き方や職場の改善に加え、産業振興の新たな展望も持っております。
今、県では令和5年度から9年度までの5年間を計画期間とした「長野県産業振興プラン」を策定しております。
その中では、「グローカルな視点で社会の変化に柔軟に対応しながら、産業イノベーションに取り組む企業を集積させていく」ということを長野県の目指すべき姿として掲げております。
重点施策としては、新たな価値の創出と産業DXの推進、デジタル人材・高度人材の育成・確保、本社機能や研究開発拠点の誘致とスタートアップ育成といったものがあります。
さらに、海外展開を見据えた持続可能な経営の展開も重要視しております。 こうした取り組みを県としても支援し、グローバル競争が激化する中でも新しい価値を生み出し、世界で稼げる・世界で通用する産業の創出と振興を図っていく所存です。
身近な自然も魅力

岩下:
やはり働くことだけが人の生きる意味ではないと思います。長野県の場合は働くことと暮らすこと、この2つの魅力があると思っています。
私も東京から長野県へUターン就職した人間ではあるんですけれども、やはりこれだけ自然が身近にあるような県はなかなかないんだろうなということを感じますし、首都圏に対するアクセスの良さも強みですよね。
少し車を走らせれば観光地にも近いということで、働くことだけではなく暮らすことの魅力もやはり長野県にあると思っています。長野県で働くことと暮らすこと、この2つの魅力を同時に発信していければ色々な方に集まってもらえると思います。
瀧澤:
そうですね、岩下の申し上げた通り、住みやすい環境があり、少し移動すれば素晴らしい自然があるといったことが長野県の魅力かなと思います。仕事をする上で、仕事以外の部分が充実していることも大切でしょうから。