「人間性を回復する組織」――労働者協同組合についてそう語るのは、駒澤大学 経済学部 現代応用経済学科で教授を務める松本典子先生。研究者として現場の調査を行う一方、自らも静岡県磐田市に拠点を置く「労働者協同組合いわたツナガル居場所ネットワーク(以下、ツナガル居場所)」の理事の1人として、不登校の子どもたちやその親御さんが安心して過ごせる居場所づくりに取り組んでいます。
労働者協同組合法は2022年に施行されたばかり。市場経済の中で自立した経営を続けていくには、多くの課題も見えてきています。それでも松本先生は、働くことと生きることが結びつくこの仕組みに、人が本来の自分を取り戻す力があると語ります。「自分が自分であれる場所」としての労働者協同組合について、松本先生の研究と実践のお話を含めて伺いました。
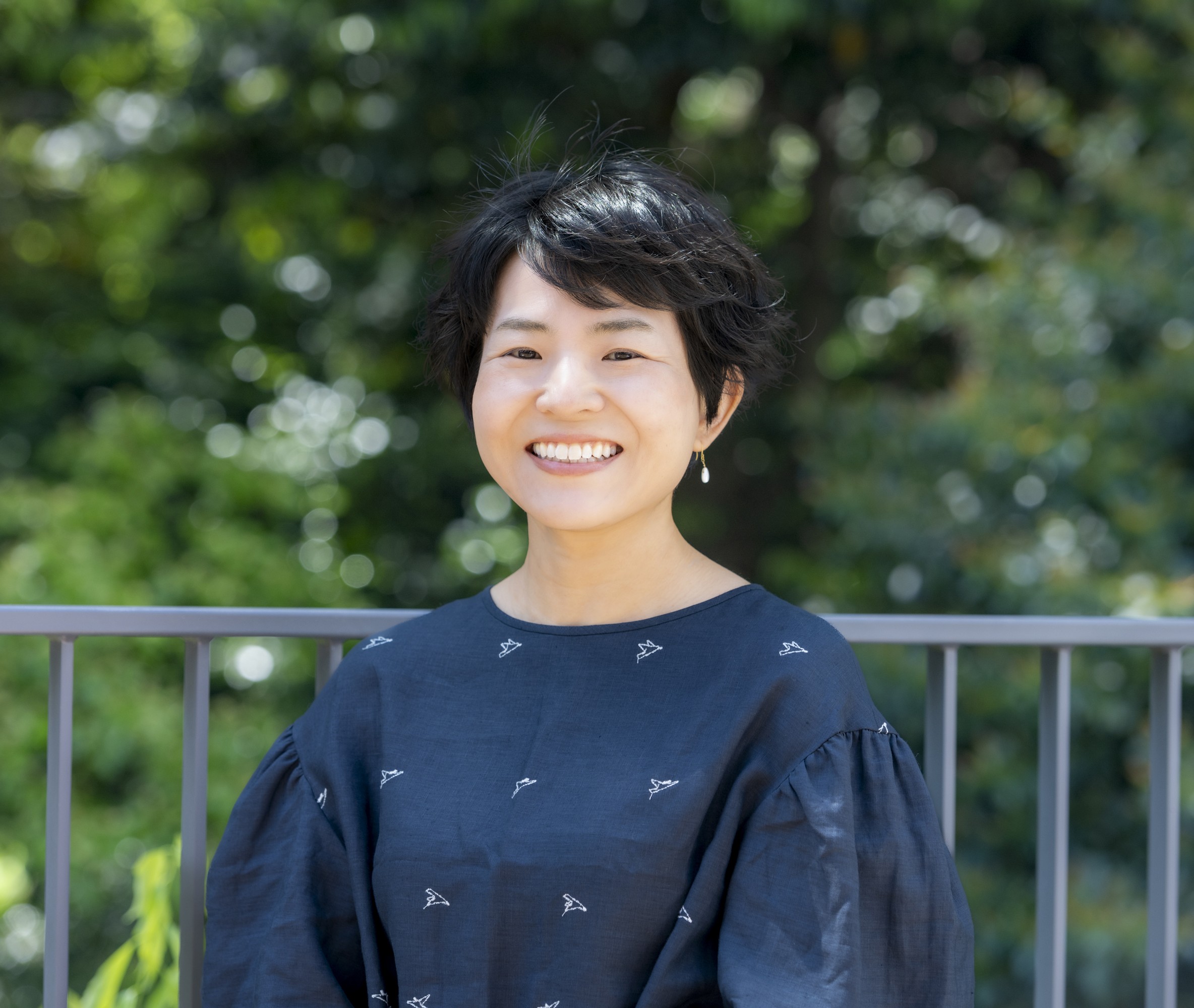
松本 典子 先生
駒澤大学 経済学部 現代応用経済学科 教授
研究テーマはNPOや協同組合の経営学。
1980年東京都生まれ。
駒澤大学大学院商学研究科にて、博士(商学)を取得。
2007年に駒澤大学経済学部現代応用経済学科に着任。
日本NPO学会副会長、日本協同組合学会常任理事、一般社団法人協同総合研究所常任理事、駒澤大学経済学部現代応用経済学科ラボラトリ所長、労働者協同組合いわたツナガル居場所ネットワーク理事。
2025年2月に『労働者協同組合とは何か』を中央経済社から出版。
問題意識を共有したことで生まれた労働者協同組合
――まず、先生が労働者協同組合を設立するに至った経緯を伺いたいと思います。どのような問題意識をお持ちだったのか、メンバーはどのように集まったのかなど教えていただけますか?
松本先生:
子どもが生まれて自分が子育てをするようになると、子育て支援制度を調べますよね。その中で「これはちょっとどうなの?」と思ったことがありました。
一つは、子どもが保育園に通っていたときに病児保育がうまく利用できなかったことです。今、磐田市には病後児保育が7つありますが、病児保育は2つしかないのでもっと増えると良いなと思います。
もう一つは、小学校に上がったときの学童保育(放課後児童クラブ)ですね。
――学童は、親が働きに出ている小学生の放課後の居場所みたいなものですよね。学校の授業が終わってから、保護者が仕事から帰るまでの間に過ごせる場所。
松本先生:
そうです。公立のものから、私立の保育園に併設しているものまでパターンはさまざまです。数年前、公立の学童を見学したことがきっかけで、子どもにとっての「居場所」を親も意外と知らないものだなと気づいて、実際、子どもの居場所ってどうなっているんだろう?と興味が湧きました。その後、お隣の浜松市で学童を運営されている方や大学の先生にお話を伺ったり、ワークピア磐田という施設で情報を得て、子どもの居場所づくりやその支援をされている方にいろいろとお話を聞きに行きました。
ただ、当時はなかなか自分がやりたいと思えるところまでは踏み切れませんでした。でも、コロナ禍を経て、2023年に磐田市長とのご縁で、起業されたりNPOを運営されたりしている女性たちと出会う機会をいただいたんです。
そのときに出会ったのが、ツナガル居場所のメンバーの一人である、山田さんでした。
――山田さんも松本先生と同じように子どもの居場所づくりに関心があったんですか?
松本先生:
そうなんです。山田さんは社会教育士の資格をお持ちで、地域で子どもの居場所づくりの活動をされてきた方です。それで山田さんから「紹介したい人がいる」と言われてお会いしたのが、もう一人の理事である石野さんでした。
石野さんは言語聴覚士と保育士の資格をお持ちで、お子さんや大人の知能・読み書きに関する検査をやっています。
山田さんと石野さんのお子さんは不登校児で、私も子どもの居場所づくりや日本の公教育の現状に興味があったから、そういう共通の問題意識を持つ3人が集まって話す中で、このテーマで本格的に活動していくには法人格があった方がいいよねという話になって。
法人にもいろいろな形態があるじゃないですか。非営利の法人でいえば、NPO法人とか一般社団法人(非営利型)とかですね。正直最初は、一般社団法人(非営利型)がちょうどよいかなと考えていました。NPO法人は私たちがやりたいことにはマッチするけど、設立に10人必要だし、必要な書類も多いのでちょっと辛いなと。
法人化の検討をしていたのが2023年だったんですが、たまたま石野さんがワーカーズコープの情報をキャッチしてきて、労働者協同組合に興味を持ちました。
――2022年の労働者協同組合法施行の翌年ですね。
松本先生:
そうそう。その時点で静岡県内には藤枝市に労協法人が一つありましたが、磐田市では初めての立ち上げでした。また、現衆議院議員で、協同組合の振興を公約に掲げていた小山展弘さんが磐田から出ています。小山さんは、2025年5月末の国会で、「国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る決議」の提出者として趣旨弁明を行って採択されていますが、小山さんはそれ以前から磐田市で労働者協同組合の勉強会を何回か開催していて、労働者協同組合に関心を持つ人が増えていて広がる基盤がありました。
――労協法人設立の人数要件(3名)もクリアしていますね。
松本先生:
はい。その後、デジタルクリエイターの近藤さんも加わってくれることになりました。彼はホームページ制作や、名刺・チラシのデザイン、インスタの動画制作といったことを個人事業としてやっていて、ツナガル居場所でも制作関係は近藤さんが担当しています。そして、近藤さんからの紹介で入ってきてくれたのが宇野さん。宇野さんは当時個人事業主としてカメラマンをしていました。
――みなさん、さまざまな資格やスキルをお持ちで、それを労働者協同組合で生かされている訳ですね。
事業の方向性を全ての組合員とすり合わせる

――実際の労働者協同組合の運営について聞きたいのですが、労働者協同組合の運営で一番大変なのは、「合意形成」なんじゃないかと思うんです。「組合員の意見が適切に反映されること」が法律上定められている法人は他になくて、理念はとても共感するんですが、同時に、意見を適切に反映するってものすごく大変な気がするんですが、実際どうですか?
松本先生:
ツナガル居場所の場合、その辺は案外ゆるいかもしれません。
ただ、どういう「事業」をやっていくかという方向性のすり合わせは、この一年結構苦労しました。法人として運営するには当然収入が必要ですが、ツナガル居場所がやっている不登校児の居場所支援は、それ単体では収益事業にはなりません。
助成金を頂いている取り組みもありますが、継続的にもらえるわけではありませんし、講演会などのイベントも開催しますが人件費が出るほどにはなりません。
福祉の中でも、高齢者介護や学童であれば、労働者協同組合でも委託事業を受けられます。「制度の狭間の福祉事業」をやりたいのであれば、NPO法人の方が向いているように思います。NPO法人の方が断然認知されていますし、支援してくれるところもたくさんあります。大規模な労働者協同組合であれば、「制度の狭間の福祉事業」にも手を出しやすいと思うのですが、小規模な労働者協同組合では「制度の狭間の福祉事業」のみで運営していくのは厳しいというのが、正直な実感です。
――なるほど…経営が難しいんですね。
松本先生:
ツナガル居場所の運営を支えるために、理事がそれぞれ自分のスキルを持ち寄って、発達に関する検査、デジタル学習教室、グリーン事業(草刈りや植物相談など)と3本柱を立てて事業を軌道に乗せる方向でいますが、それでもやはり経営は難しいです。
事業が拡大してくると、アルバイトを雇う必要性も出てきて、就業規則や労働契約関連の書類を作る必要が出てきます。自分たちだけで就業規則を作るのは不安があるから、社労士さんに作成してもらいたいけど、そこに本当にお金かけるべきなのかといった話し合いもしました。それと、誰がどのような保険に入った方がよいのかなど、いろいろな意見が出てきます。そういった一つ一つを丁寧に話し合って決めていくのは時間がかかります。
とはいえ、意見反映や合意形成がめちゃくちゃしんどいかというと、ツナガル居場所はそうでもなくて。みんなそれぞれ好き勝手言いますが、最後はなんとなくまとまっていく感じです。そこが、労働者協同組合を運営する面白さでもあると思います。
2025年3月に、私が書いた本の出版記念講演会を開催したのですが、終わった後にはじめて飲み会をして、ツナガル居場所の活動を組合員と振り返りました。それからちょっと良い方向に温度感が変わりました。今まで気を遣って言えなかったところも、「とりあえず言っておこうかな」と思うようになりました。「もしかしたら関係ないかもしれないけど、一応情報共有しておこうかな」とか、「こういうイベントがあるから一緒に行ってみない?」とか。そういう情報共有が増えたと思います。
――遠慮の壁が取り払われたという訳ですね。
松本先生:
はい、些細なことかもしれませんが、遠慮しないで意見できることは大事です。私たちが運営しているのは労協法人なので、自分の意見はきちんと言おうという意識が今は強いです。
――労働者協同組合法の基本原理である「適切な意見反映」は、メリットであると同時に、それによって意思決定に時間がかかるというデメリットも孕んでいるように思います。そのあたりは実感としていかがでしょうか?
松本先生:
めちゃくちゃ時間がかかるのは確かです。ただ、会議の仕方に決まりがある訳ではないし、みんなが納得する方法で意思決定できればそれでいいんじゃないかという感じで、割と柔軟に捉えています。
労働者協同組合で意見が分かれやすいテーマに、「事業を強くするのか、運動を強くするのか」ということがあります。これは”協同組合あるある”かもしれません(笑)。
ツナガル居場所も当初は全く収益をあげられていなかったので、「もうちょっと事業をやっていかなきゃいけないんじゃない?」と第三者から言われることもありました。でも、事業面ばかり強く意識しすぎると、本来自分たちがやりたい「子どもの居場所支援」という非営利的なものが見失われてしまうおそれもあるわけです。
それに、ツナガル居場所の場合、組合員が仲間として集まって設立したということがすごく大切なんです。仲違いしてまで事業をやりたくないと思っているから、「もっと事業を」と第三者から言われたときも、私は「仲間割れしてまで続けたくない」と発言しました。そのときの反応は人それぞれでしたが、自分が意見を言うことによって他の人も意見をいいやすくなったように思います。
話し合いをしている中で、「なんかちょっと変かな?」と違和感を感じることがあります。その時、自分からももちろん違和感を伝えますが、そういうときって他の組合員も同じように思っていたりすることもあるので、「時間をかけて考えよう」と言ってくれたりします。そういうことがあるので、どんなに話し合いが延びても別に苦痛ではないです。
――確かに、自分の意見を表明しない・できないのであれば、労働者協同組合にいる意味がないような気がしますね。
松本先生:
そうですね。でも、みんながみんな、自分の意見を持っていて的確に表明できるかというと、実際はなかなか難しいと思います。意見はあるけど、口で伝えるのが困難な人もいます。なので、その辺りは皆さんいろいろ工夫されていると思います。定期的にアンケートを実施して、そこに意見を書いてもらうといった実践をしている労働者協同組合もあります。
それと、発言しやすい仕組みづくりも大事だと思います。リーダーは、割と的確に自分の意見を表明できる人がなりがちで、自分の意見を言えない人に合わせる文化ってあまりないじゃないですか。でもそうすると結局、必ずしも「適切な意見反映」にならない可能性もある。だから、意見を言えない・言わない人にファシリテーターになってもらう仕組みにしてしまうのもありだと思うんですよね。最初から「できない」「向いていない」と決めつけるのではなくて、無茶振りしてみることも大切かもしれません。
運営のマインドとして、「私たちは、みんなが経営者(経営にコミットする)なんだから、意見を言っていかなきゃいけないよね」という原点に戻っているところに、労働者協同組合の意味があるように思います。
――労協法人では意見を表明するのが苦手な人も経営者になれるというのが、ミソかもしれませんね。
労働者協同組合は経営者が複数存在するコモン
―先生のご著書『労働者協同組合とは何か』を読んで、労働者協同組合とコモン(公共財)との親和性を改めて感じたのですが、その辺りのお話を伺えますか?
松本先生:
『人新世の「資本論」』で有名な斎藤幸平さんは、「労働者協同組合の働き方(仕事)自体がコモン」という風におっしゃっていますけど、それはまさにそうかなと思うところがあります。
私、一人で起業したいなと思っていた時期がありました。一人でやろうと思えば一人でもできるけど、実際はハードルが高いわけです。でも、みんなで起業するならできるかも、と思いました。その選択肢の一つが労働者協同組合だったというわけです。
労働者協同組合という法人として協同して働くことの意義は、みんなで責任を分担できることだと思うんです。個人事業だと、誰かから仕事を依頼されたとき、すべてを自分で決めるしかありませんが、労働者協同組合であれば「うちはみんなで共同経営して意思決定しているので、持ち帰らせてください」と遠慮なく言うことができます。実際、事業のことは、まず組合員全員に相談して、その上で決めます。そうすると、責任を押し付け合うのではなく、分担することができます。そこが労働者協同組合の良さだなと思うようになりました。本業で仕事をする際に良い影響が出ることも、大きなメリットです。
――よく「経営者は孤独だ」と言われますが、話せる相手が常にいるっていいですね。
収入面が大きな課題
――法人としての収益や、組合員の収入面は実際どうですか?
松本先生:
正直なところ、ケア労働や草刈りといった、人手が必要な事業で稼ぐのはかなり厳しいと思っています。でも、ツナガル居場所の組合員は「民間企業で勤めるのと同じくらいの収入が得られるようにしたい」と常に言っています。とても大切なことだと思っています。
――そういう人が一人でもいらっしゃるといいですね、適度な緊張感が生まれる。
松本先生:
そうそう、事業も頑張らなきゃって思います。労働者協同組合の先行事例が多数ある海外では、有名で大きな労協法人でも倒産していたりするので。
日本は労働者協同組合法の施行から今年で3年目とまだ日が浅いし、ツナガル居場所も設立して2年目なのでこれからですが、日本に労働者協同組合が定着するには、もう少し認知度が上がっていく必要があると思っています。「労働者協同組合なるものがあるんだ、そういう働き方があるんだ」ということがもっと知られるようになれば、新たな働き方の選択肢にもなるし、結果的に法人の数も増えていくと思うので。
――私も労働者協同組合のことはここ1年くらいで初めて知りました。確かに認知度は課題なんでしょうね。私事ですが、妻が労働者協同組合の設立を検討しているので、アドバイスがあれば是非お願いします。
松本先生:
法人の設立自体は他の法人形態に比べてすごく楽なんですが、問題はその後で、情報がなくて苦労するところはあるかもしれません。ちょっと細かいことを確認しようとすると、行政機関をたらい回しにされがちです。ただそれも、これから認知度が上がっていけば、改善されるとは思いますが。
それと、最初の3人(法人設立に必要な最低人数)の組合員選びがとても重要です。法人を運営する上では、人数が4〜5人くらいいると良いと思います。4〜5人いるといろいろな意見が出ますし、でも多すぎないのでバランス的にちょうど良いと思っています。
社労士さんや行政書士さんなど、士業の方に入ってもらうのも良いですね。
市場経済に奪われた人間性を取り戻す
――労働者協同組合の内外両方に対して遠慮をしないというのはポイントなんですね。前例が少ない黎明期ならではの面白さがありそうです。
松本先生:
労働者協同組合に関する先行研究の中で「労働者協同組合(協同組合)は、人間性を回復する組織だ」と書かれていたことがあって、初めてその言葉を目にしたときはあんまり実感がわかなかったんですが、自分で労働者協同組合を始めて一年くらい活動して「私、これ、人間性回復してるんだ」って実感するようになったんです。
というのも、活動をしていると、本当にいろいろなことを考えるんですよ。例えば、労働者協同組合含め、何らかの団体の代表になると扶養から外れなければならないのですが、そうすると、そもそも扶養って何なの?とか、百何十万の壁って何なの?とか、自分事として日頃から考えるようになりました。
他にも、不登校児の居場所支援をしていると、今の学校のシステムってちょっとおかしいところがあるよねという話になったり、今まで受け身で受け流していたことも、「あれちょっとおかしくない?」「これどうにかならない?」といったように、仲間と一緒に気軽に話すことが増えました。
あと、労働者協同組合は、会社みたいに社長(使用者)と従業員の組織ではないせいか、そもそも労働って何だっけ?という話題にもなりやすいです。ボランタリーな労働とかケア労働って賃金がもらえないから労働じゃないの?いや、立派な労働でしょといった具合です。
そういう、今まで受け流してきたあれこれを「見える化」していくと、間違っていることは間違っていると言わなきゃいけないという気持ちになってくるし、だんだん話題が、政治のことにも展開していきます。議員の仕事って何?市長って実際何をしているんだっけ?政治ってそもそも何?選挙ってそもそも何?と、仕組みに対する疑問が湧いてきます。
――それで思い出したんですが、少し前に妻が「令和の米騒動っていうけど、結局何が原因なのか私よく分かってないんだよね」という問題提起をしてきて、彼女が調べたことを聞く時間があったんです。一通り聞いて思ったのは、こんなに身近で主食である米のことですら、その価格の決まり方についても、米が収穫されてからスーパーの店頭に並ぶまでのプロセスも、言われてみれば全然知らないな、ということでした。
きっとそういう所与のようになってしまっていることを疑問に思って調べたり、おかしいことがあれば何らかの提言をしたりアクションをとることが、「人間性を取り戻す」行為なのだろうなと感じました。
松本先生:
まさにそうだと思います。市場経済が「効率性」を追求する中で私たちから奪われるものがあって、その失ったものを、労働者協同組合の活動を通じて自分たちに取り戻していっている感じです。
労働者協同組合の活動の中では、私は私でいてよくて、私を認めてくれる仲間もいる。労働者協同組合は自分にとっての居場所にもなるので、私はいろいろな人がそうやって自分の居場所を複数持つことが大事だと思うんです。
そして、現状を、希望を持って変えたいと思ったら、とにかく声を上げること。そうしないと誰にも伝わらないです。一声発する、そして発し続けることが大事だなと思います。

◇あとがき
日本における労働者協同組合は、制度としての歴史は浅く、運営にはまだまだ困難も多い。それでも、そこには「誰もが受け入れられ、役割を持てる場所」を自分たちの手で創造する面白さがあることも感じたインタビューでした。不登校の子どもたちの居場所づくりをはじめ、実践の中で見えてくる協同労働の可能性は、経済合理性最優先の社会によってもたらされた「疎外」への一つの応答なのかもしれません。労働と暮らしがつながる場としての労働者協同組合の意義を、改めて考えさせられました。



