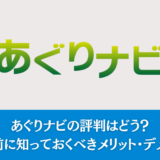農業が抱える問題点・課題が改めてクローズアップされている。「農業従事者の減少・高齢化」-「耕作放棄地の増加」-「食料自給率の低下」-「農業の法人化の動きがある一方で、新規参入のハードルの高さ」等々。TPP(環太平洋パートナーシップ)への署名、参加による「国際的貿易協定で海外からの安価な農産物との競争激化が、農家経営を圧迫している」と指摘し大上段から「構造的問題」と断じる向きもある。
課題は共有せざるを得ない。が、「農業は楽しい」という想いがこの身に沁みついている。同じ歳の同業者(物書き稼業)が15年余前に、『「家庭菜園」 この素晴らしい世界』(講談社刊)を上梓した。彼は発刊当時で既に、「家庭菜園歴20年余」のベテラン。60歳の折りそんな彼を師匠に、件の書籍の編集担当者ともども弟子入りした。毎週土日は師匠の家庭菜園で、泥に塗れた。炎天下の真夏には、コンビニのソーメンくらいしか喉を通らなかった。真冬に近場のラーメン屋ですすった塩ラーメンの美味さは、今でも忘れられない。
農業と真っ向から取り組んでいるミライ菜園:畠山友史代表に今回取材を申し込んだのは、農業に生涯の舵を切ったその本音を知りたかったからである。幸い快諾を頂いた。
畠山氏が農業に寄り添った原点は、故郷の原風景の消失(耕作放棄地の増加)
畠山氏は埼玉県入間市で生まれ育った。私は所沢市の住人。原点を耳にした時、頷いた。
筑波大学大学院でロボット工学を学んだ畠山氏は、卒業後に大手電機メーカーに職を求めた。名古屋市で上下水道のシステム開発を担った。いま、こう振り返る。
「久方ぶりに(入間市の)実家に帰った時でした。物凄いショックを受けました。故郷の名産は、狭山茶です。思春期の頃は茶畑に囲まれ、日々を送っていました。ところが久しぶりの故郷では、いわば原風景とも言える茶畑が失われてきていたのです。聞くと、後継者不足やなにやらの事情で耕作放棄地が急増していると知りました。心にポッカリと穴が開きました。このことが、農業と関わって生きる原点になりました」。
私の住処近くにも狭山茶の茶畑がある。日々愛飲している。茶畑には適宜な間隔で支柱が建ち、先端に扇風機の羽根のようなものがついている。何だろう、と思い狭山茶の販売店で教えてもらった。「防霜(ぼうそう)ファン」。「寒くなると地表の温度は冷え込むが、茶畑の地上6~7mには逆転層という温かい空気の層ができる。逆転層の空気を地表に吹き付け茶畑を温める装置」だと知った。緻密な技法にいたく感心した。爾来(狭山)茶の虜になった。(狭山)茶畑が目の前から消えたらショックを受けるに違いない。心底、そう思う。だから畠山氏の話に頷けた、というわけである。
畠山氏は7年余りサラリーマン生活を送ったが久方ぶりの狭山市で受けた大ショック以降、気持ちの中に「農業に関わりたい」という想いが日増しに膨らんでいった。起業家というのはそもそも、「心の想い」に立ち位置を置く御仁なのかもしれない。2019年、人生の舵を大きく「農業」に切った。
どうしたのか。「農家との接点はなかったので、農業をまずは現場で知ろうと思いまして愛知県一宮市のイチゴ農園でアルバイトを始めたんです」。慣れていくにつれ「病害虫被害の深刻さを知った」という。
畠山氏は、実は家庭菜園組。「ベランダが野菜の緑で埋め尽くされることに、癒しを覚えています」。ベランダ菜園とはいえ単に種を蒔き、苗を植えて水をやっていればOKというわけにはいかない。例えば苗の選び方ひとつからして大事。失敗を繰り返し先達に知恵を拝借して身につける以外にない。件のイチゴ農園でも苺の苗が次々と枯れてしまったことがあった。農園経営者の目は、「原因」を見抜いていた。「病害虫にやられた」のだと教えられた。
病害虫に、心がフォーカスした。
AIへの驚嘆がなかったら・・・
畠山氏の脳裏には「AI」の二文字が湧いた。農業は言わば、アナログの世界。「直面した課題:病害虫」に「最先端のハイテク:AIで対峙できるのではないか」、と考えたのだった。
筑波大に学んでいた時期、AIは登場した。が正確性に欠け、使いづらいという印象だった。それが2012年、就職早々の時期に「大きな衝撃を受けた」という。具体的に、こう振り返った。
「AIが物凄く進化していました。それまではチェスで勝つとかはできても、画像認識などは不得手。そうだったはずのAIが、画像から物体を正確に認識するまでに進んでいたのです」。
当時はネットで検索しても、なかなか欲しい病害虫の情報にたどり着けなかった。「AIを活用すれば、画像から簡単に病害虫を特定できると考えました」と続けた。
時系列を追うとその後、故郷で「幼い頃の原風景が消失している」ことにショックを受け、農業と関わる生活に心が大きく傾いていた。
進化したAIを認識した時、農業への道筋がつながった。「AIを活かして農業と向き合う」。こうして2019年5月に、ミライ菜園は設立された。
実際にミライ菜園は、どうその認識を広めていったのか。
SCIBAI(サイバイ)-TENRYO(テンリョウ)

2023年から、SCIBAIの開発に取り組んだ。AI病害虫を画像で診断(識別)できるアプリ。相応の評価が得られた。開発早々からダウンロードが相次ぎ、5万回余りに達した。が農家側からの反応(要求)は、更に踏み込んだものになった。「蝕んでいる病害虫が何なのかよりも、いつ襲ってくるのかを知りたい」。
そこで、TENRYOの開発に並行して取り組んだ。AIによる病害虫の予測サービスを提供する防除DXアプリである。
農業関連の資料を繰ると、「病害虫による農業被害は収穫量の約4割にも及ぶ」-
「適当なタイミングの農薬散布が必要」-「かつては勘と経験で散布を行ってきたが、従事者の高齢化などで困難になっている」とある。
TENRYOは、こうした一連の問題を解決する。畠山氏はこう説明してくれた。
「各地の20年分の気象データと、アプリユーザーから寄せられる発生履歴をデータベースに独自のAIで病害虫の発生を予測する防除アプリです。現状でキャベツ・ブロッコリー・ネギ・苺など露地野菜や果物など14種類に対応しています」。

ミライ菜園のホームページを覗くと「AIによる発生警戒アラートで適宜な防除ができるため、農薬の使用量が最小限で済む」とある。
TENRYOの開発に当たっては3年前から愛知、群馬の農協と連携し約50件の農家で実証実験を重ねた。豊橋市の「アグリミートアップ」(ビジネスコンテスト)での入選。農林中金が出資する「Agventure Lab」のインキュベーションプログラムでの採択。そんな風に認められた結果が、JA豊橋/JA群馬との業務提携の契機となった。それぞれの実証実験で、例えば「ブロッコリー農家で15%の収穫量の増加、キャベツ農家から4%の増加」等々が発現。着実に認知度(導入実績)を広め・高めた。
畠山氏は、今後の方向・方針を「病害虫と対峙し続ける。対応作物を増やし続ける。それを可能にするシステム開発と取り組む。病害虫被害による農家の減収を極力阻止する」と展望する。
畠山氏が痛感している、名古屋の起業創出の土壌
畠山氏は、「名古屋はスタートアップ企業を産み出す土壌があると考えます。その為のインフラ整備が進められているからです」とした。
内閣府は「世界と伍するスタートアップ・エコシステムの拠点形成策とし、「スタートアップ・エコシステム『グローバル拠点都市』」の認定と取り組んでいる。2020年度に、名古屋市を認定した。その持つ意味は大きい。名古屋はトヨタ自動車を頂きに自動車部品メーカーで形成する、いわば城下町の歴史が色濃かった。内閣府が投じた一石は、名古屋に新たな顔を産み出した。
そうした流れを本格化させたのは24年に開業した「ステーションエーアイ」。心臓部。単なるオフィスではない。スタートアップ企業/大企業/投資家/研究者/支援機関が一堂に会する日本最大級のオープンイノベーション拠点。あらゆる支援がワンストップで提供される。
「2029年までに1000社のスタートアップ企業が集う」計画が明らかにされている。
ミライ菜園は言わば、その先達企業。
畠山氏は「上場を視野に」とした。