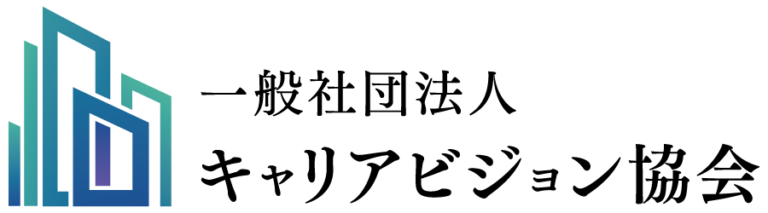文化人類学という学問分野をご存知でしょうか。さまざまな文化や社会、そこに生きる人間について調査・研究し、比較を行う学問です。元々はヨーロッパの人々が他文化について調査するために始まった分野ですが、徐々に世界中に広がり現在では多様な文化や社会を研究する学問分野となっています。
長野市にある清泉女学院大学(2025年4月より共学化し「清泉大学」)の小泉真理教授は、文化人類学をアメリカで学ばれました。文化人類学者として2年半もアフリカに住んだ経験や、実際に異文化の中で生活した経験から今の若者に思うことなど、多岐にわたる貴重なお話を伺いました。
(記事公開日:2025年1月17日)

小泉 真理 先生
清泉女学院大学 人間学部 文化学科 教授・学部長
学位:イェール大学大学院(米国)人類学専攻 博士号
主な担当科目:文化人類学概論、比較文化論
文化人類学的視点から人間社会の多様性や普遍性について考えながら、今という時代を探求していきます。世界観、儀礼の意味、家族の形、生活様式などに焦点をあて日本や海外の人々暮しを理解していきます。さらに、現代社会の課題解決に向けた文化の可能性を考えていきます。研究プロジェクトに取り組み、文献調査やフィールドワーク行い、成果をまとめます。
文化人類学との出会い
――小泉先生は文化人類学を専門とされていますが、この学問分野との出会いについてお聞かせ願えますか。
大学生の頃英文学を専攻していたのですが、ヨーロッパやアメリカの映画が好きで、異文化に飛び込んでみたいという想いをずっと持っていました。そこでアメリカの東海岸にあるニューヨーク州立大学に留学をすることにしたのです。アメリカでの生活は楽しく、留学期間を終えても日本に帰りたくないと思うほどでした。その頃はまだ日本では男女雇用機会均等法が成立していなかったこともあり、帰国して働きたいとも思えなくて。アメリカに居続けるため、大学院に行くという選択肢を採りました。
大学院で何を学ぼうかと悩んだ時、ニューヨークの大学で受けた文化人類学の授業が頭をよぎりました。その授業を担当していた教授がアフリカを専門とした文化人類学の先生で、その授業に衝撃を受けたことを思い出したのです。日本に来る前から映画で観ていたアメリカの文化にはさほどギャップを感じなかったのですが、その授業でアフリカの文化を知った時「まだまだ知らない世界があるな」と思い、すごく魅力的だと感じたのです。そこで、大学院ではアフリカを研究対象として文化人類学を学ぶことに決めました。アフリカの文化を研究されている先生がいるところを探して、イェール大学の大学院へ進むことになりました。
アフリカで2年半、現地の人々と共に生活

――大学院では実際にアフリカに足を運んで研究されたのですか。
そうですね。文化人類学においては「参与観察」と言うのですが、調査対象となる現地でそこに住んでいる人と同じように生活し、経験を積んで情報を集めることが大切です。私も2年半の間、タンザニアの標高1800mの村に住みました。
なぜタンザニアにしたのかといいますと、最初にどこを研究対象にしようか考えた時に、まだあまり研究者が入っていない所がいいなと思いまして。また当時からマラリアが流行っていたのですが、標高1000m以上のところにはマラリアがいないと言われていましたので、ある程度標高の高いところに行きたかったというのもあります。現在は温暖化の影響で、1000m以上でもマラリアが見られるようになってしまったみたいですが。
そこでまだ研究が進んでいないところで、かつ高地の地域を探しました。そうしたらタンザニアの南の方にリビングストン山脈という、かなり高い山が連なっている地域が目に留まりました。そこは1960年代にアメリカ人が調査に入って以来研究されていないようだったので、ここにしようと思って足を踏み入れました。
泊まる所も決まらないままその地域にひとまず辿り着きましたが、村の人々には植民地経験があるので、異質な人間に対してはやはり警戒心がある訳です。私は白人ではないのですが彼らよりは肌が白いので、白人に対する恐れのようなものがあったのでしょう。また私は当時スワヒリ語でコミュニケーションを取ろうとしたのですが、彼らが話すのは民族語でした。どうしたものかと困っていたら、一人の男性がスワヒリ語で「どうしたの」と話しかけてくれました。その男性は教会の関係者で、私が「研究をしたいから滞在したい」と訳を話したら、教会の事務所の一画を住まいとして借してもらえることになりました。
私にとっては、ここにキリスト教の教会があるのが少し意外でした。元々私が師事していた先生がアフリカの宗教を研究している人だったので、私も現地の宗教を調べようと思ってタンザニアを選んだのです。しかしいざ来てみたら、実際のところ村民の8割はキリスト教徒でした。植民地化の過程で200年以上前からキリスト教が布教されていて、かなりの人が改宗をしていたのですね。
そのようにして住む所も決まり、2年半その地域で人々と生活を共にしました。私は適応力があったようで、少しずつ言語コミュニケーションもとれるようになってきました。地域の人々も、私がどんな人間なのか分かれば警戒心を解いて助けてくれました。2年半の間は一度もアメリカや日本に帰らなかったのですが、その村の一員として過ごせたので、ある意味村人が家族のようでしたね。
村にも馴染んで暮らしていたのですが、そうしているうちに先生から「そろそろ帰ってきて論文を書きなさい」と言われ、アメリカに戻りました。大学院には計7年間いて、かなり面白い経験をしたと思っています。アフリカでの生活は大変なように思われるかもしれませんが、その時は別に苦でもなかったです。
帰国し、大学教員に

いよいよ大学院も修了し、さあどうしようということになりました。アメリカで文化人類学の学位をとっても企業に就職ができるわけでもなかったので、日本に戻って大学で教えるのがいいかなと思って帰国しました。
大学に就職してからも1-2年に一度くらいはアフリカの現地での調査をしていました。ただこの10年は学校の仕事が忙しくてなかなか行けていないです。1カ月休みが取れたとしても、正味研究ができるのは2週間程度で、調査費用もかさむので難しいのです。コストを考えると難しいですね。
現在所属している清泉女学院大学に来てからは21年になります。出身は横浜なのですが、長野には住んでみたいと思っていました。ニューヨークからアフリカに行った時、時間の流れが全然違っていて。ニューヨークは大都会ですから、人もエネルギッシュで日々目まぐるしい。一方でアフリカはすごくゆったりとしていて、人々が人間らしく生きている印象がありました。そういう世界に2年半いたので、日本に帰ったらそういう世界で生活をしたいなという想いがありまして。山が好きで、アフリカでも山の中にいたので、長野は住む場所としてはぴったりでした。
授業に込めた願い
――清泉女学院大学は2025年度から清泉大学として共学化するとのことですが、小泉先生は変わらず文化人類学を教えるご予定なのでしょうか。
はい。現在は人間学部文化学科という名前ですが、人文社会科学部文化芸術学科に移行します。担当する科目は変わらない予定です。
私が現在教えている主な科目は文化人類学概論と比較文化論です、本学の学生の多くは長野県内で生まれ育っています。皆さん授業を受けると驚きます。「そんな世界あるの」「そんな人たちがいるの」と、自分たちの世界が他の世界とは違うということに気付くようです。そういう意味で、刺激になるような授業であればいいなと思って講義をしています。
でも、「文化人類学を専攻しても食べていけないよ」と伝えています(笑)。職業に繋がらない学問なのです。全く実用的ではない学問なので、心理学や情報系の学問と違って仕事に結び付きにくいです。
ただ、「実際の仕事には結びつかないけど面白い学問だよ」とも伝えています。私はキャリア教育も担当しているのですが、人生全体をキャリアだと捉えて、今後どういうふうに生きていくのか考えてもらうようにしています。文化人類学を学んで異文化に触れた人たちは、いわゆるキャリア教育と呼ばれる職業選びのようなものよりも、もう少し広い視野で自分のこれからの世界や生き方を考えられるようになってもらえたらいいなという想いもあります。
文化人類学を学んで、彼女らがどういうふうに消化してくれるかはわかりませんが、きっとどこかでは役に立つと思いながら授業をしています。

他者を多角的に理解し、さらに別の他者に伝える
――お話を伺っていると、文化人類学はむしろこれからの時代にとても必要な学問のように思われます。
そうですよね。文化人類学の特徴として、「文化に優劣をつけない」というスタンスがあります。異質なものを見たときに毛嫌いするとか、「ありえない」と否定をしないのが文化人類学です。他者を理解し、受け入れる学問なのですね。ですからそういった視点を学生が意識をし、あるいは気付いてもらえると、彼女らの人生も変わっていくのではないかと思っています。
文化人類学の調査の最終目的は、調査をまとめた民族誌を書くことです。なぜそれを書くのかというと、自分の文化圏の人々に別の文化に住む人々の営みを伝えるという点が一つの目的です。そして異文化を理解することで、自らの社会や文化を見つめ直すための学問だと私は考えています。
もう一つ、文化人類学の良い特徴は「多角的、総合的に人間の生き方を見つめる」というスタンスです。いろいろな角度から人間を見ていくのです。しかし、現代はインターネットの普及によって、物事を一つの面だけを見る人が多くなっています。多角的にものを考えたり議論したりする場が少ないので、画一的な偏った考え方の人間が育ってしまっているような気がします。インターネットには情報がたくさんあるはずなのに、自分に合った情報だけを目にする仕組みになっているので、偏ってしまうのですね。
そんな時代だからこそ、ネットにある情報からだけでなく、自分の肌感覚で知ることが大切だと感じています。それが文化人類学におけるフィールドワークだと、文化人類学者の仲間とよく話しています。私が若い頃は情報といえば書物や一部の映像に限られていて、行動しないとなかなか違う文化には出会えませんでした。だから「本当は世界ってどうなっているんだろう?」と疑問に思ったら、自分で見に行かなければならない環境でした。文化人類学を学ぶことで、学生たちには自分で実際に目にすることが大事だとわかってもらいたいです。