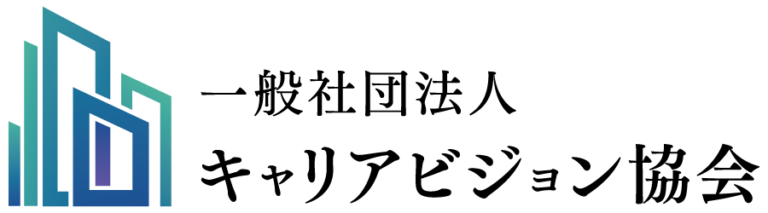罪を犯した人が更生するためには、本人の努力はもちろん、保護司や教誨師といった支える存在、地域の理解も欠かせません。
長年にわたり更生保護事業に取り組んできた、西本願寺の学寮を起源とする龍谷大学。その伝統を活かし、教誨師が学べる場を設けることから始まり、現在では履修証明プログラムの矯正・保護教育プログラムを開講するなど、学生に限らず広く学びを提供しています。
今回は龍谷大学法学部教授であり、矯正・保護総合センター長を務める浜井浩一教授に、履修証明プログラム「矯正・保護課程(矯正・保護教育プログラム)」の概要や更生を阻む社会の課題についてお話いただきました。

浜井浩一先生
龍谷大学法学部教授
矯正・保護総合センター長
早稲田大学教育学部卒業後、法務省に入省。刑務所などの現場実務を経験。実務を通じて直面した課題の解決策を論文として発表するなかで大学から誘われ、「龍谷大学にいけば面白いことができるかもしれない」と教員の道へ。専門は犯罪学。
目次 閉じる
広がる学びの場

――「矯正・保護課程(矯正・保護教育プログラム)」は、どのような経緯で開設されたのですか。
龍谷大学は西本願寺の学寮が起源となっているのですが、西本願寺ではもともと更生保護事業が行われていました。こうした伝統の下、教誨師向けの課程を作るなかで、1952年文学部に教誨師の養成を主な目的とした「矯正講座」を設置しました。そして、1968年に法学部が開設されたことを受け、学部生にも学びの場を提供しようと、1977年には特別研修講座「矯正課程」(現在の「矯正・保護課程」)を開設しました。 教誨師の学びの場を作るところからスタートし、この特色ある学びを学生はもちろん保護司や一般の方々にも提供する形で広がっていきました。
社会人の方と学生が一緒に大学の授業を受講することには、大きな意義があると思います。特にそれぞれの視点で意見を交わすことできるグループワークは、非常に有意義なものになると思います。例えば、高齢者が刑務所に入るケースの多くが万引きによるもので、繰り返し万引きをする人が増えているという話をした後に学生同士で議論をしてもらうと、コンビニでアルバイトをしている学生から実際に高齢者の万引きを捕まえた経験があるといった話が出てきました。もし、この場に保護司の方がいて体験談を共有してくれれば、さらに新たな気づきが得られると思います。教員が一方的に話す授業よりも、こうした機会を少しずつ増やしていくことが重要だと感じています。
しかし、社会人の方と学生が一緒に受講するとなると、時間帯を合わせるのが大変なんです。学部生には2〜4講時目の時間帯が人気ですが、社会人の方は仕事の関係で5講時目以降でなければ出席が難しくなっています。学部生向けの単位科目として提供するとなると、どうしても学部生の都合に合わせたプログラムになりがちで、社会人の受講生は徐々に減少する傾向にありました。そこで、昨年から受講がしやすいように、オンライン、オンデマンドでも受講できるようにしたところ、昨年度は受講生が増加しました。
ただ、オンデマンドやオンラインで全国どこからでも受講できるにもかかわらず、現状では受講者が近畿地方に偏っており、本学を知らない方々に講座の存在が十分に伝わっていないことが一つの課題です。広報活動により力を入れなければいけないと感じています。このような講座を展開しているのは日本では本学のみで、保護司や福祉関係、教育、生活指導などの関連分野に従事する方々には、潜在的なニーズがあるはずです。実際、「勉強の場がない」と多くの方が口にされています。
本講座は1科目3,140円で、気軽に受講いただくことが可能です。オンラインで今年度社会人のみに提供している科目は「犯罪学」「被害者学」「矯正医学」「アディクション論」の4科目(大学に来て受講できる科目は学生に提供している科目と同じで、約30科目あります)があり、実務経験者から学べるプログラムになっています。来年から学生にも人気のある「犯罪心理学」もこれに加える予定です。
更生と反省
――保護司という重要な仕事が、より多くの方に認知されることが社会のためにも必要ですよね。
私がよく話すのは、罪を犯した人たちが更生するのは社会に戻ってからということです。更生とは、社会で普通に生活できるようになることなんです。多くの人は更生と反省を混同しており、刑務所や少年院などの施設内で更生すると考えがちです。しかし施設内ではこれまでの生活を振り返り、被害者のことを考えて反省することはできますが、ある種拘禁されると同時に社会から守られている状況で簡単には更生できません。
社会で普通に生きていけるようになるためには、地域社会の理解が不可欠です。保護司は、その地域社会の代表者であり、その役割には大きな意味があります。
――先生からご覧になって現代の日本社会は、罪を犯した方が更生しやすい社会だと思われますか。
真逆だと思います。かつて厳罰化が進んだ際には刑務所が過剰収容になることがありましたが、現在は犯罪が減少し、刑務所や少年院が次々と閉鎖されている状況です。しかし、その一方で、高齢受刑者が増加しており、刑務所はどちらかというと社会福祉施設化していると言えます。当然、認知症を患う受刑者も増えています。約半数の受刑者が死ぬまでに一度は再び刑務所に戻ってくるのですが、高齢者の場合は戻ってこない方の多くがすでに亡くなっている可能性もあり、50%の方が更生しているのかは疑問です。
日本社会は、罪を犯した人々を自分たちとは異なる存在として排除する傾向が強いように感じます。日本は縦割り行政なので、法務省の仕事、厚生労働省の仕事と分かれていて、罪を犯した人が高齢者であろうと、障害を持っていようと、ホームレスであろうと、その対応はすべて法務省の仕事になります。しかし法務省は社会的な資源を持っていないため、少年院や刑務所に収容するしか方法がありません。出所後の対応についても、厚生労働省や地方自治体はつい最近まで法務省の仕事と捉えていたわけです。高齢者であったり働けない刑余者は生活保護を受けられなければ、生活を維持するのは困難です。そうなると、刑余者は、再犯するか、自殺をするか、ホームレスになるかの選択肢しかないわけです。ホームレスになるか自殺する覚悟があれば刑務所には帰ってこないと言う受刑者もいますが、結局刑務所に帰ってくる選択をしてしまうんです。
少し前まで生活保護も水際作戦で、受給がしづらい状況でした。受刑者の多くは住所を抹消されており、申請時に住所を聞かれて「わかりません」と答えると、「それでは受け付けられません」と申請すら受け付けてもらえません。本来、生活保護の申請は権利であり、申請があれば受け付けなければいけません。生活保護の財源の4分の1は地方財源であるため、申請を受けるほど地方自治体の支出も増えます。そのため、窓口の担当者の勉強不足もありますが、意図的に申請を諦めさせるような態度を取り、申請を減らそうとする「水際作戦」が行われていました。
このような状況の中、北九州市では生活保護を受けられず、「おにぎりが食べたい」と書き残して餓死する事件が発生し、大きな問題となりました。この事件が起きる直前、北九州市は生活保護申請者が減少したことから自立を成功させているとして表彰されていました。しかし、実際には水際作戦によって申請者を減らしていただけだったんです。
他にも、福祉の助けが得られず起こってしまった事件として、下関駅舎放火事件があります。放火をした男性は70歳で刑務所を出所しましたが、過去に10回も服役を繰り返していました。知的障害を持っており、そのことは裁判で何度も認定されていました。しかし福祉の支援は一切なく、出所後すぐに生活が苦しくなって警察に保護されます。警察は福祉事務所に連れて行ったのですが、例によって住所がないため保護申請を拒否され、隣町行きの切符を渡されて市から追い出されました。このような対応が複数の福祉事務所で繰り返され、最後に彼がたどり着いたのが下関でした。下関駅舎は24時間営業ではないため、午前2時頃に「もう閉めるので出て行ってくれ」と言われ、行き場所もなく刑務所に帰りたいとの思いから放火に及んでしまったんです。
唯一の居場所と化す刑務所
――グレーな断り方で、たらい回しにされているケースもあるんですね。
下関駅舎を放火した男性は、実は事件を起こす前に一度救急車で病院に運ばれているんです。その際に、男性がお金を持っていなかったため、病院のケースワーカーさんが生活保護の医療扶助の手続きを行っています。ですから、男性に知的障害があり、刑務所出所者で身寄りもなく、 このまま放置すればホームレスになることは、生活保護の窓口担当者も総合病院のケースワーカーさんも全員わかっていたわけです。それにもかかわらず、結局はたらい回しにされて事件が起きてしまいました。
唯一たらい回しをしないのが刑務所なんです。刑務所は裁判所が懲役3年と言い渡すと、必ずその期間収容し、たらい回しにすることはありません。制度上、 刑務所だけが唯一「No」と言わない場所になっています。なかには、名前や生年月日すら言えない人もいて、なぜこのような人を刑務所に収容するのか疑問に思うこともあります。裁判は調書によって進められるため、本人が答えられなくても問題ないんです。裁判官が読み上げたことに対して、「はい」と答えればそれで終わりです。本人がきちんと話せなくても、警察官や検察官が本人の言葉として調書を書き、最後に本人に確認させる形で作成することができます。
ですから、誰も人を見ていないんです。裁判が行われる際は刑務官が拘置所から法廷まで被告を連れていくのですが、間違えて異なる法廷に連れていってしまい裁判が始まっても、裁判官も弁護人も検察官も誰も気づかないことが実際にありました。日本の刑事司法は事件処理機械のようにオートメーション化されていて、99.9パーセントが有罪という実態があり、基本的にスクリーニング機能はほとんど働いていません。そのため、認知症で自分のことすら何も言えない人も、刑務所に送られてくるんです。懲役期間が終われば出されますが、刑務所が唯一自分を拒否されない場所になってしまっているんです。いわゆる刑務所志願といって、刑務所に入りたくて事件を起こす人が日本には結構いるんです。これは、先進国の中でもほとんど例のないことです。
刑務所に認知症や障害を持つ方が多く収容されていることは薄々知られていたものの、これまで対応はされてきませんでした。下関駅舎放火事件はドキュメンタリーとしても取り上げられ、この事件をきっかけに福祉関係者がようやく重い腰を上げて厚生労働省に働きかけ、2009年から地域生活定着事業が開始されました。
社会的孤立が再犯を生む
私は地域生活定着支援センターの設立に最初から関わっていたのですが、市町村の担当者と話をした際に、「刑務所を出られた方ですよね。それなら、法務省が山の中などに施設を作って、そちらで面倒を見ればいいのでは」と言われたことがありました。それでは、刑務所から出た人を、別の刑務所に入れるのと同じことではないですか。市町村の人は、刑務所を出た人も市民であるという認識がまったくなかったんです。私はその言葉にあ然とすると同時に怒りを覚えました。罪を犯して刑務所に入った人は「普通の人ではない」、法務省が対応すればいいという社会が、日本の再犯率の高さを招いているのではないでしょうか。
再犯の最大の要因は、社会的孤立です。孤立し、ここには自分の居場所がないと感じたとき、人は再び犯罪に走ってしまいます。多くの人が「もう二度と刑務所には戻りたくない」と思い、社会に出て頑張ろうとしますが、仕事がうまくいかないこともあります。また、自尊感情が低下しているため、些細なことでも差別されていると感じやすく、実際に特殊な目で見られることも少なくありません。
さらに、長く刑務所で生活してきた人が社会に馴染むのは簡単ではありません。刑務所の中では、言われたこと以外は一切できず、ロボットのような生活を送ることになります。決められた時間に起き、食事も上げ膳据え膳で、自分で行うのは部屋の掃除ぐらいです。あとは、コミュニケーションが一切禁止された中で、決められた作業を黙々とこなすだけです。人とのコミュニケーションも自分で考えて行動する機会も全くない生活を2〜3年送った状態で社会に出て仕事に就いても、わからないことがあっても尋ねることさえできないんです。結果として、職場でうまくいかず、辞めてしまうケースが多いのです。
罪を犯した人が受け入れられにくい社会だからこそ、再び犯罪に手を染めてしまうのです。日本では罪を犯した本人だけでなく、その家族も特殊な目で見られる傾向があります。死刑囚の家族の多くは崩壊し、自殺に至るケースも少なくありません。
根強い差別意識
逆に言えば 、自分が何かをすれば家族にも厳しい目が向けられることは、みんな知っているわけです。私は「家族人質社会」と呼んでいるのですが、我々全員が家族を人質に取られている状態なのです。だからこそ、お互いに「自分に対してここまでひどいことはしないだろう」と、自分の置かれた立場を相手に投影して安心していられるんです。
東野圭吾さんの小説『手紙』では、強盗殺人を犯した兄を持つ弟が、雇い主から解雇される場面があります。その際に、雇い主が弟に「我々は君のことを差別しなきゃならないんだ。自分が罪を犯せば家族をも苦しめることになる―すべての犯罪者にそう思い知らせるためにもね。」というのですが、まさにこういうことなんだろうなと思います。日本は、長年こういう社会なわけです。
ただ、日本の治安の良さは、ある種の相互監視状態に支えられているところもあります。一時、生活保護を受けている人がパチンコに行くのは、生活保護の不正受給ではないかと問題になったことがありました。そこで、兵庫県の小野市では、生活保護を受けている人を市民全員で監視して不適切な行動をとった場合は市に報告するよう求める条例が作られたんです。市議会でこのような議論をして条例にすることが、変だっていう感覚がないんです。
私が刑務所に勤務していた際に、DARCを立ち上げた近藤さんを刑務所に招いて、受刑者に指導をしてもらったことがあるんです。DARCというのは薬物依存症から立ち直った方が運営する、薬物依存症の方の回復施設です。近藤さんには前科がありますが、当時は前科のある人が受刑者を指導するなんて考えられないことでした。そのため、所長には薬物依存症の専門家であると紹介し、前科のことは伝えませんでした。しかし時間が経つにつれて、その事実はどうでもよくなっていくんです。薬物依存症から立ち直った人が指導するのと、私や精神科の先生が指導するのとでは、受刑者の態度は180度といっていいほど変わります。薬物を断ち切った人が話す内容は重みがあり、説得力が全く違います。
近藤さんは少年院の先生や薬物撲滅運動を推進している厚生労働省の外郭団体「ダメ。ゼッタイ。」の理事長とともに国会に招かれ、薬物対策について議論したことがあります。その議論が終わった後に刑務所に来て指導を行ってくれたのですが、その際に「今日、面白い話があったんだよ」と言うんです。国会である議員さんが「DARCは財政的に厳しい状況ですが、『ダメ。ゼッタイ。』は国の支援を受けており、寄付も多く集まっています。協力して薬物撲滅に取り組むことはできないのでしょうか?」と質問したそうです。すると、「ダメ。ゼッタイ。」の理事長は、「うちはライオンズクラブや大学生など、薬物を使用したことのない人たちと一緒に活動しているので、DARCさんとは住む世界が違う」と答えたそうです。
私も後で調べましたが、このやり取りは国会の議事録にも記録されています。このような差別意識を持っていること自体が、問題だという認識がないんです。「薬物をやめよう」という同じ目的意識を持って活動しているにもかかわらず、薬物を使用した経験があると、それだけで仲間と見なさないわけです。「薬物を使用した時点で同じ人間ではない」という姿勢に、疑問を感じていないんです。このように罪を犯した人たちを差別することが当たり前だと考える人が多く存在していて、同じ人間として見られないことに大きな問題があると思います。
矯正・保護課程の中でも、こうした話をしています。矯正・保護課程はもともと保護司や教誨師、篤志面接委員など、関係団体でボランティアをされている方々をメインターゲットにしていましたが、最近ではこうした問題に関心を持ってくれる方も少しずつ増えてきました。市町村では再犯防止推進計画を立ててネットワークによる支援を進めていますし、司法福祉が社会福祉士の試験に必修科目として含まれるようになりました。こうした動きもあり、福祉や教育関係の方々の参加も少しずつ増えているように感じます。