ゲーセン女子。本稿の主人公:おくむらなつこさんは、自らをそう称す。何故かはご本人の口から、後でご説明頂く。
一昨年5月に設立されたLinkArcade代表。アーケードゲーム機のオフィス内レンタル設置サービス、『アケシェア』を展開している。企業などを対象にした、ゲームセンター(以下、ゲーセン)に設置されている「アーケードゲーム機」をレンタルするビジネス。ゲーム機は通常のコインでのプレイのほか、フリープレイ対応も可能。企業による両替機の集金対応不要。クレーンゲーム機や、e-Sports向けビデオゲーム専用筐体などを取り扱う。1台からレンタル可能。月単位の契約。ちなみにゲーム機は提携しているゲーセン運営企業からレンタル可能な業者の在庫を、業者自らが運び込む。昼間、ネクタイを締めたサラリーマンがゲーセンで楽しむ姿も少なくない。社員の福利厚生策として、興味深い施策ともいえる。
どんな経緯でおくむらさんは、かくなるビジネスを始めるに至ったのか。おくむらさんを取材した。
アケシェアは、ゲーセン女子のゲーセン業界に向けた恩返しでもある
おくむらさんは「幼いころの記憶は、おぼろげなんですが」としたが、三歳の時からピアノを習っていた。小学生になると生まれ育った県境をまたいだピアノ教室に、足を運ぶようになった。
「人気の先生でお弟子さんが多かった。有名な先生だったんです。レッスン時間は予約制でしたが大方、遅れてなかなか順番が来ない。待ち時間を真横にあったゲーセンでつぶすようになったんです」。これがゲーセンとの出会いだった。「大音量と大画面のゲーセンに、妙に惹かれました」。
ゲーセン女子への「ホップ」は、「妙に惹かれた」以降のゲーセン行脚。お小遣いとしてお母さんからせしめた?100円を握りしめ、放課後にゲーセンへ。休みには足をのばして学校帰りでは難しい、遠めのゲーセンに出かけた。「母は、私が100円をなんに使うのかは重々承知していたはずですよ」と笑う。
「最初にハマったのはすでにレトロゲームになっていた、電気音響が販売していた平安京エイリアンというゲームでした」。
取材で最もきつかったのは、その口から次々に飛び出してきたゲームの名前。メモしておくのが精一杯。どんな代物かは「後で調べよう」と分かったふりをしてメモだけとった。がそれらはいずれも、由緒正しいゲーム揃いだった。例えば「平安京エイリアン」は、1979年に東大の学生サークル「理論科学グループ」が開発したコンピューターゲーム。最初はパソコンゲームだったが80年に、電気音響という会社がアーケードゲームとして発売した。
100円でゲームを楽しんだ後もランドセルを背負ったまま、おくむらさんはゲーセンを離れなかった。喜々とした顔つきでゲームと向き合っている客の後ろに立って、目をさらにして自身をもゲームを見守った。こんなこともあった。「後ろから眺めていたらおっちゃんが、”すわり~な、わしは母ちゃん怒られるからもう引き上げるさかい代わりにやってや”ということも珍しくなかった」と言う。おくむらさんは「ゲーセンには人間の壁がなかった」としみじみ語る。ゲーセンのスタッフと言葉を交わす機会も日増しに増えていった。
そして、おくむらさんのゲーセン女子への「ステップ」は中学生の時代。
「わたし、いじめにあったんです。先生も母も、学校に行きなさいと怒る。でも学校に行くといじめられる。死んでしまおうかと、自動車の前に飛び出そうとしたこともありました。本当に、ひょっとしたら死を選んでいたかもしれなかった。でも、ゲーセンとゲーセンの常連さんたちのお陰で踏ん張れた。中学校の同級生がいるエリアは避けて、1時間先のゲーセンに行ったりもしました。ゲーセンでの知り合いは、中学校という社会とは違って年齢も職業も違う、本名も知らなかったりする。だけど好きなもの(ゲーム)を通してコミュニティがある。中学校の外には、別の世界があることを知ることができたんです。”ひとつの社会の中でいじめにあっても、その外には他の社会があるということを知って欲しい。ゲーセンはその一つだと自身が体験できた。いまの会社を興した大きな理由として、”ゲーセンへの恩返し”という気持ちがあります」。
ゲーセン女子を名乗ったわけ
ゲーセンコミュニティを地域社会に作りたいという思いから、「ゲーセンは文化だから・・・」という想いが膨らんでいった。
まずブログを書くようになった。通い詰めて顔見知りになったゲーセンのスタッフから、例えば流行っている作品の「何故か」という生の情報を耳にし、ゲーム機の攻略ではなくコミュニティを発信。業界のトップからは「ゲーセン経営事情」を教えてもらい、ゲーム機メーカーにも飛び込んだ。そうこうするうちに「貴方はなにもの」と問われることも増えた。
あえて言う。おくむらさんは、なかなかの戦略家でもある。「ゲーセン好き、だけでは弱い。ゲーセン女子を名乗り、踏み込んでいこう」と決めた。「ゲーセン女子」を前面に押し出して取材をし、生の情報を基にブログを書き続けた。そして遂には、自著を上梓した。『ゲーセンさんぽ』。2016年1月の1冊目を皮切りに22年1月まで、計5冊を発表した。ゲーセン女子への「ジャンプ」である。
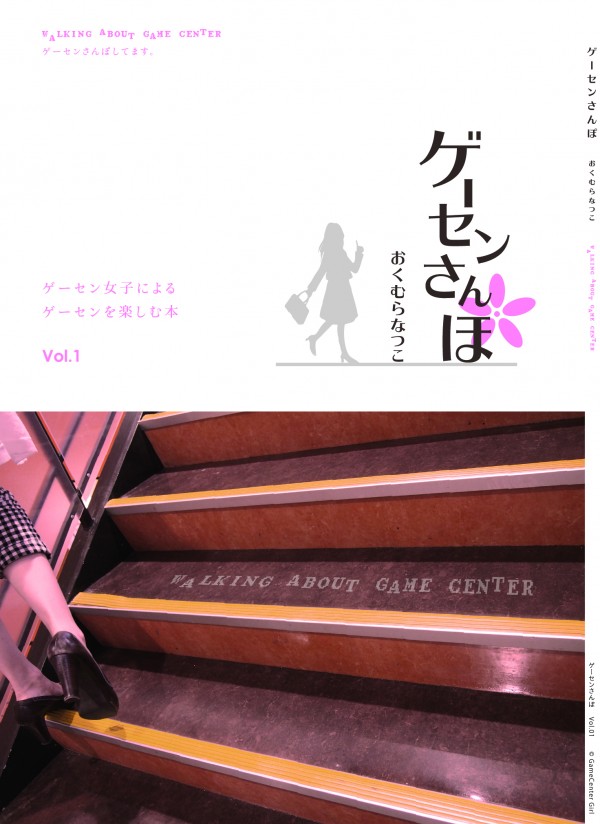
そうなるとおくむらさんには、ゲーセン関連業界から逆に、経営や運営などの相談もされる立場になっていた。
ゲーセン女子が語る、ゲーセンのいま、そして今後
私は意地悪。取材に当たり「相手が不愉快に思う話はないか」を探す癖がある。JAIA(アミューズメント業界の調査を手掛ける)の、こんなデータに出会った。「ゲーセンの店舗数は減少傾向・・・」。「がゲーセンの市場規模は少しずつだが増加している」。後者は伏して、ゲーセン女子にぶつけた。がおくむらさんは、淡々と語った。
「ゲーセン業界は、ターニングポイントの時期にあります。同じ機械を置いていても、中小と大手では経営・運営方法に違っています。また、マーケティングと海外展開が加速しました。郊外店をはじめとして大型店舗化など、店舗数は横ばいでも設置台数は伸びているんですよ。
国内市場規模という観点でみると横這いから+αしている感じでしょう。
ゲーセンは今後とも存在し続けます。文化ですから」。
ゲーセンとゲーム機を企業コミュニティにプレゼンする日々が続いている。が「ゲーセンを楽しむ時間はまったく変わっていません」とした。



