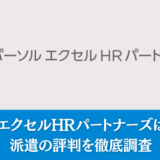山形県鶴岡市は庄内地方の南部に位置し、東北で一番の総面積を誇る市です。現在でも数多くの在来作物や郷土料理が食べられている鶴岡市は、平成26年に国内で初めてユネスコ食文化創造都市に認定されました。市役所には、「食文化」を課名にした「食文化創造都市推進課」があります。
今回はそちらで働く本間歩さんに、全国的に見てもトップクラスといえるような食文化が今日まで残ってきた背景と、今後の展望などについて伺いました。




庄内平野の農村風景
「食文化創造都市推進課」の設立
――「食文化創造都市推進課」という課は、他では聞かないかなり珍しい課だと思いますが、この課はどういった経緯で発足したのでしょうか。
鶴岡市は平成17年に六つの市町村が合併してできた市です。新たな鶴岡市として何か一つの方向に向かっていこうということで、旧市町村それぞれの地域に多く残っている在来作物や豊かな食文化を活かし、ユネスコ創造都市ネットワークの食文化分野への加盟を目指すことになりました。
市の体制としては、平成25年に、当時の政策推進課(現在の政策企画課)内の課内室として、「食文化推進室」ができました。その4年後、平成29年に、「食文化創造都市推進課」として独立した形になります。この間、平成26年にユネスコ創造都市ネットワークの食文化分野への加盟認定を受け、日本初のユネスコ食文化創造都市となりました。そして、ユネスコ認定後にさらに力を入れていくため、単独の課になったという背景があります。

各地域が持つ豊かな食文化
――食文化が発展する要因には、採れる食材の種類とか料理の仕方とか、様々な条件がありますよね。旧来より庄内地方の中心地であった鶴岡地域は、海に面した城下町だったんですよね。
そうですね。鶴岡地域はかつての城下町で農業が独自の発展を遂げてきました。そのほかの地域もそれぞれ特徴的な食文化があります。
また、気候も同じ市内で全然違いますね。海側は比較的雪が少ないですが、山の方はかなり降ります。例えば、山菜は雪があってこそ育つというのもあるので、変化に富んだ地形や四季の変化が相まって幅広い食文化を生み出しているのかなと思います。


――食文化が発展するために条件がよい場所は全国にたくさんあれど、その中でも鶴岡市の食文化は、トップクラスともいえるほど発展しているのはなぜだと思いますか。
例えば、在来作物が残ってきたという点でいえば、背景には種を守り継いできた農家さんたちの努力があります。他にも、出羽三山信仰のような精神文化や城下町である鶴岡の気質・風土など、食以外の文化と結びついたことで、現在にまで色濃く残っているものもあります。これらや土地柄などが複合的に組み合わさった結果、独自の食文化として発展してきたのだと思います。


羽黒山伏と精進料理
――本間さんは、鶴岡市で育ったんですよね。ほかの地域にお住まいのことがあれば、その地域と比べて、食べ物の違いを感じたことはありますか。
育ったのは鶴岡市で、鶴岡以外には、新潟と東京に住んだことがあります。
大学時代を過ごした新潟は鶴岡と同じ日本海側で、食文化も似ているなと感じました。東京は全国各地の食が集まっているということもあり、東京独自の食文化を感じたことはあまりないというのが正直なところです。
日本はどこに行ってもある程度は美味しいものを食べられると思いますが、そんななかでも、鶴岡は平均的なレベルが高く、四季を感じられる郷土料理や汁物文化など、豊かな食文化があるなと、外に出ると特に思います。


市内の在来作物だけでも60種ある
――鶴岡市にお住まいだと、基本的に鶴岡で採れたものをよく食べるんですか。
地元のものばかり食べているかと言われると、正直そうではない部分もあるんですが、鶴岡でしか作られていない作物があったり、季節ごとに食材や料理があったりというのは、ほかの地域と比べた特徴なのかなと感じます。
――いわゆる在来作物が多いということですか。
そうですね。山形県内で見ると180種類ぐらいの在来作物があって、そのうちの60種類が、鶴岡市にあります。
時期によって獲れる作物が違い、その時期ごとに定番の料理があります。春先ですと「孟宗汁」や「孟宗ご飯」、夏は「だだちゃ豆」というような感じで、それぞれの季節に思い浮かぶ食べ物があるのは、一つの特徴だと思います。
小さい頃から「民田なす」や「温海かぶ」といった在来作物の漬物を食べているので、今でもその季節になると食べたくなりますね。
一部の在来作物については、繋いでいく作り手さんが少なくなってきているという課題があります。そのため、料理教室などで在来作物を使う取組や、生産者さんと飲食店をマッチングさせる取組などを行っています。食文化を途絶えさせないための取組は今後も強化していき、行政だけではなく、様々な方々と協力しながら進めていこうというところですね。




左上から時計回りに「民田なす」「温海かぶ」「月山筍」「藤沢かぶ」
――在来作物を繋ぐにしても、持続可能な生産体制がないと難しいですよね。
そうですね。今後の持続可能な生産を考えると、生産者がいる今のうちから、色々と手を打っていかなきゃいけないと考えています。特に若い世代への馴染みが薄いと感じますが、令和6年度に実施した在来作物生産者・飲食店等マッチング事業では、若者たちが来るようなお店でも、在来作物を扱っていただきました。ただ、取組が一つあったからといって、ずっとそれだけでいいという問題でもない。やはり続けていくことが必要かと思います。
若い世代へ食文化をつなぐ

――食文化維持のために色々な取組をされていらっしゃいますが、給食もなるべく地元産の食材を使っているそうですね。
地元産の食材だけで賄うのはなかなか難しいですが、子どもたちに地元の食材や郷土料理などを知ってもらうためにも、なるべく地元のものを使用するよう取り組んでいます。鶴岡は給食発祥の地と言われており、私も小学生の時は、昼食として食事を提供した当時の献立を再現した給食を、年に1回は食べていました。本当にシンプルなメニューで、鮭とおにぎり、煮びたしなどが出てきます。
――鶴岡市では、食文化への理解が深められるよう、地域の郷土食や行事食を積極的に学校給食で提供していますよね。また、地元産野菜や地場産水産物の利用率も高い目標設定になっていますよね。
「鶴岡市第2次食文化創造都市推進プラン」でも学校給食に関する様々な目標を立てています。例えば、行事食と郷土料理 の提供回数は34回、在来作物は25回としています。しかし、在来作物や郷土料理をそのまま出すとなると、なかなかハードルが高いんです。その年の獲れ高にも左右されますし、そもそもの生産量が少ない品目もあります。そのため、在来作物を刻んでソースにして提供するなど、給食センターでも工夫しながら、子どもたちに食べてもらう回数を増やしていく方向で進めているところです。
また、食育・食文化理解促進のための「鶴岡型ESD」という取り組みを市内小中学校で実施しています。食文化食育体験、生産者との交流等を通じて、地域の食文化へ関心を向け、理解を深めたり、在来作物や郷土食・行事食、食べるための「知恵」等を学び、知識を深めたりすることで、地域資源や伝統技法が後世に受け継がれ、持続可能な食や食文化の実現につながります。

――お話を伺っていると、市が一体となって食文化の維持・発展に取り組んでおられますね。
そうですね。鶴岡市内には、料理人と生産者が直接繋がっていたり、自ら食育の取り組みをされている団体があります。特に行政が主導しなくても、民間団体等が自ら動いている部分もあり、そういったことも全体的なレベルアップに繋がっていると思います。
料理人と生産者の連携の事例でいうと、「サスティナ鶴岡」という団体があります。料理人や農家、漁業者、飲食関係の方などが一緒になって、様々なワークショップなどを企画し、子どもたちに食の豊かさを伝える取組をしています。最近では農林水産大臣賞を受賞されるほど、すごく一生懸命に取り組んでおられ、市としても支援をしています。こういった方々のように、次世代にどう伝え残していくかというところまで考えている、意識の高い方が多いというのが鶴岡の特徴だと思います。
――すごいですね。皆さん郷土愛がありますね。
本当にそうですね。自分もこの課に来るまでは正直あまり意識していなかったんですが、様々な立場の方の「鶴岡の食や食文化を繋いでいこう、発展させていこう」という想いが、ユネスコ認定やその後の取組に繋がっているんだなと実感しています。


サスティナ鶴岡の活動
維持だけでなく、発展させるために


日本酒造りも盛んで市内には酒蔵が7つある
――令和7年度以降も、これまでの事業を発展させるようなイメージですか?
これまではどちらかというと、食文化の保存・継承に重きを置いていたように思います。令和7年度以降は、これまでの取組をベースとしながら、「産業にどう結びつけていくのか」を念頭に入れて各種取組を進めていきます。
また、令和7年度から、内閣府の「地方大学・地域産業創生交付金事業」に採択された「鶴岡ガストロノミックイノベーション計画」が山形大学農学部と慶應義塾大学先端生命科学研究所との連携により始動します。鶴岡市には、「鶴岡サイエンスパーク」という、バイオ研究拠点があり、この研究拠点や農業・食産業、食文化、高等教育機関の集積といった鶴岡市の強みを有機的に結合し、一体的に事業を推進することにより、高い相乗効果の実現を目指しています。具体的な取組はこれからですが、これまで守り繋いできた食や食文化を大切にしながら、食産業・食文化に新たな価値を創造する事業も動き出しています。
――素晴らしいですね。まさに温故知新の町という印象です。ありがとうございました。
・つるおか食の原風景・・・食文化創造都市推進協議会が作成したパンフレット
・Creative Cities Network / UNESCO・・・ユネスコ創造都市ネットワーク公式サイト(英語)