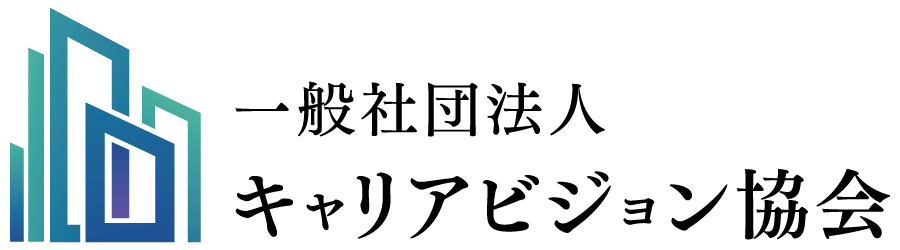茨城県つくば市のNPO法人「ユアフィールドつくば」。
農業と福祉事業を合わせた「農福連携」事業に2011年から取り組んでいます。
代表理事の伊藤文弥さんに、農福連携事業を営む中で感じた経営の面白さや社会の課題について伺いました。
行間には、障がいのある人たちにどういう風に働いてほしいか、暮らしてほしいか、どんな社会にしたいかという思いが滲んでいます。
また、後半では養鶏を担当する社員の荒間 瑛(あらま よう)さんにもお話を伺いました。
農福連携事業の始まり

伊藤文弥さん(以下、伊藤):
僕は大学生の時に、現つくば市長、当時は市議会議員だった五十嵐 立青(いがらし たつお)氏の下でインターンシップをしたのですが、その頃に五十嵐がこの事業を立ち上げたんですね。当初は五十嵐が代表で、僕が副代表だったのですが、五十嵐が市長になったタイミングで、僕が代表に替わったという流れです。
僕は五十嵐と一緒に何かをやりたいという気持ちがとても強かったので、この事業を一緒に始めたのです。元々、「農福連携」というテーマに強い関心があった訳ではないんです。むしろ、「何かもっと他に格好良いことがしたいな」と思っていたくらいで。 結局はこの仕事をやっていくと決めたのですが、当時はこの仕事の奥深さや楽しさや意義を理解していない状態でのスタートでした。
では、なぜ五十嵐が農業をやった方が良いと考えていたかというと、農業をする人が少ないからです。だから、高齢化が進んだり耕作放棄地が広がったりという現状があって、その担い手を増やしていかなければいけない、と。
あとは、障がいのある人達は働く場所がないという課題もあったので、そこに着眼して農福連携事業を立ち上げたわけですね。
この事業を始めた当初、世の中の障がい者施設の農業は、本当に狭い面積でちょこちょことやって、そこで採れたものを自分達で食べるという域をなかなか出られずにいる状態が多かったように思います。

問題意識が吹き飛んだ

伊藤:
僕は当初、農業という産業においても、働くかぎりは生産性を上げる、お金を稼ぐことがすごく大事だと思っていました。色々な人が「農業は儲からないぞ」と言っていたんですが、僕は「そんなのはやり方次第だろう」と思っていました。
農業に限らずなのですが、最低賃金を稼ぐことがいかに難しいのかということをすごく感じます。ほとんどの人が稼いでいないというか。
僕達は農業をやる人がもっと増えないといけないと思ってこの事業を始めたわけなのですが、僕達に野菜づくりを教えてくれた久松達央さんが「農家はもっと減っていい」という本を出版して、僕の認識が大きく間違っていたんだなということに気付かされたりもしました。
さらに福祉の方で言うと、五十嵐と僕がこの事業を始めた13年前は、本当に障がいのある人たちの働く施設が少なかったんですが、そこから7年くらいですごく増えたんです。地域としては施設が供給過剰になってしまいました。
そして、障がいのある人たちは、今いるところから動きたくないという気持ちが大きいので、滅多に施設を移動しないんですよ。
仕事の内容や職場の質、会社としての体制、受け取れる工賃などで、他の施設と比較するとかなり良いレベルになっていたとしても、なかなかよそから移ることはないんです。
そのような状況なので、農福連携事業を始めた当初の、「福祉施設が少ない」「農業の担い手が少ない」という問題意識は、結構序盤で吹き飛びました。
考える余地があることが面白い

伊藤:
現在、僕は純粋に楽しさでこの事業を運営しています。
おいしい野菜ができて嬉しいとか、障がいのある人達とのコミュニケーションが面白い、といったことももちろんありますし、何より福祉や農業の奥深さに魅せられています。
例えば福祉の話でいうと、もしも僕たちが就労支援だけを運営していたとしたら、その支援の中だけでできることを考えると思うんです。
でも、やっぱりその中だけでは解決できないことがあるんです。昼夜逆転の生活を送っている人に就労支援の現場だけでサポートをするのは難しい。ほとんどが昼間の仕事ですから。
そういった場合に、「私たちは就労支援の現場だから、そこはもう範疇ではありません」と言ってしまえば、それで終わりなんです。
そこで止まらずに、どうしたらより良くできるのかと考えると、本当にきりがない。どんな組織を作ったら良いのか、どんな制度があったら良いのか、どんな風に採用したら良いのか、と考える余地が沢山あります。
その結果、訪問介護ステーションまで始めました。
そういった、事業としての奥深さが福祉・農業経営にはあります。
そして、今僕たちがやっていることを続けていくと、すごく良い事業が作れるかもしれないという気持ちがあります。10年後、20年後には、本当に日本を代表する福祉事業になる可能性がある、と。
そうするためには、やっぱり戦略的に、どうやって負けないようにするのかということはすごく考えます。
僕たちの事業のサービス提供エリアを広げる必要性は感じません。エリアを広げていくのではなく、狭いエリアで複数の事業を組み合わせることで、僕たちにしか出せない価値を出していきたいと思っています。
ではその中でどうやって障がいのある人たちにとっても、社会にとっても、働く人たちにとっても良いモデルを作っていけるか。それを考えるのはとても面白いですね。
障がいのある人たちの選択肢を守る

伊藤:
今、福祉業界には異業種の人たちがビジネスとしてすごい数で参入していて、サービスの質よりも売り上げの大きさが彼らの格になっているという印象があります。
その一方で、全然売り上げはないけれども、福祉に思いを持って、とても良い活動をしている人たちも沢山いて、そういうところが困っているんですね。素敵な活動をされているのに、お金がついていなかったり、採用が上手くいっていなかったり。
やっぱり、異業種から入ってきた人たちの方が経営が上手なので、そちらの方がどんどん増えて、思いのある人たちの経営が今後難しくなっていくんじゃないかと予想しています。
だから、僕たちもちゃんとビジネスのことを勉強しないと、異業種の人たちに勝てないんです。
異業種の人たちは今、すごい勢いでグループホームを増やしています。そして、最初はグループホームの運営を安定させるんですね。で、その時点では、入居者たちは別の就労支援施設へ通っています。
ところが、グループホームの次に、自分たちで就労支援事業も始めるんですね。そうしたら、「うちの就労支援施設で働かなければ、うちのグループホームには住み続けられません」という縛りが出てくる可能性があります。フランチャイズ展開をしている会社の説明会に参加したことがあるのですが、実際にそのような戦略を描いていきましょうという説明をしているのを聞きました。
先ほど言ったように、障がいのある人たちは移動を好まないので、半ば強制的にグループホームと就労施設のセットに組み込まれてしまって、働く場所・住む場所を選べなくなってしまうんです。
この未来は、ちょっとえぐいと思いました。
だから、僕たちはグループホームを増やさないといけない。でないと、ごきげんファームに通い続けたいと思ってくれている人たちが、半ば強制的に他の施設に移動しなければいけなくなる可能性があるからです。
養鶏に加えて鶏肉の処理場も

荒間瑛さん(以下、荒間):
ごきげんファームには養鶏場がありまして、私はそこで働いています。
さらに、鶏肉の処理場も自分たちで持ちたいと思っています。
というのも、養鶏や家畜というものはどんな飼い方をしていたとしても、本当に端的に言えば、構造的に暴力なんですよね。
でも、特に私たちは平飼いをしているので、外の人からは「鳥が幸せですね」とか、色々言われるんです。
そういった中で、もう少し自分たちのやっていることを自覚していかなければいけない。その責任があると思います。
私はこの2年間、屠殺する場面を何度か見てきているのですが、何と言いますか、その中にかなり家畜化することの構造、さらには痛みの部分も凝縮されていると思っていて。
なので、そこを自分たちでちゃんと担うことで、私たち自身も、もしかしたら買う人も、鶏に対して何をしているのかということを自覚できるかもしれません。
自覚するだけで鶏に許してもらえるのかと言ったらわかりませんが、私たちが鶏を育てて食べ物にするまでを担うことが、小さくても社会的な運動になっていけば、今よりも工場畜産的なものは減っていくのではないかと思っています。痛みがそういったものに対してストッパーになるのではないかな、と。
工業的に扱われない権利のようなものを、私は家畜に対しても想定しています。
処理場を作ることに対する私の動機はそういったところです。
伊藤:
荒間の言っていることは基本的にはわかるんですね。福祉というものは、相手の権利を想像するという部分もありますから。「なんで障がいのある人たちの権利を考えている団体が、鶏の権利は一切考えないですか」って荒間に言われてハッとしました。
ただ、毎月100万円の赤字が出るんだったら、鶏の権利を考えられないと思うんですよね。その前にこちらが潰れてしまいます。だから、僕は事業としてやっていける目途がどうやったらつくのだろうと考えました。
処理場を建てるなら使える助成金がないか探しましょうとか、処理場としてだけではなくて福祉施設としても活用できる可能性がないかを検討しましょうとか。
で、色々と勘案すると、採算的にすごくプラスになるかどうかわからないけれども、大コケせずにやってはいけるなと。それに、採算の他に何か特別な意味があれば、やれるかなと思っています。
それが荒間にとっては先ほど言ったようなことで、僕にとっては、「鶏肉を売る福祉施設としては日本一になれる可能性がある」ということです。
鶏肉まで扱う福祉施設はないんですね。やっぱり処理場まで持つのは、なかなかやれません。そもそも養鶏をやっているところが少ないですし。
だから、食鳥処理まで始めることができれば、食肉だけの収支ではなく色んな可能性が出てくるんじゃないかと思っています。

福祉と養鶏の親和性

伊藤:
実は、農福連携を運営していて、一番手応えを感じているのが養鶏なんです。障がいのある人たちも社員も働きやすいんですね。何個卵を採れるのかが読めるので。
これが例えば、ほうれん草であれば、40日後に絶対に採れるかと言われたら、気象による不確定要素が多いんですよね。お米も季節労働ですし、機械作業が多いので、障がいのある人たちの働く仕事を日常的にたくさん作るのは難しいです。
それらと比較すれば、養鶏は雨であっても卵が採れるし、餌も与えるし、水の交換もするし、作業に参加する余地が広くあります。
それに、季節に応じて鶏の様子も変わるので、毎日同じ作業の繰り返しという感じでもないんですね。
荒間:
そうですね、私自身、毎日の仕事に退屈することはありませんし、まだ養鶏施設として安定期に入っていないというのもあって、どうしたらより良くなるのかと考え続けなければいけないというのもありますね。
それに、障がいのあるスタッフたちも「鶏がこれだけいると寂しくないね」とよく言うんです。そういう感覚は本当に私にもあります。福祉施設でやることの意味というところで、やっぱり植物よりも動物の方が、少し共感しやすい部分があると思います。色んな気持ちの交流があったりして。
そんなこともあり、今の飼い方ならば作業的になりすぎることはありませんし、働いてくれている人たちもそれぞれの振る舞いをしているので、職場とはいえあまり管理的にはなっていません。
伊藤:
鶏を物のように扱い始めると、やっぱり良くないなと思うので。今はそうなっていない、そうなりづらい飼い方ができていると思います。生き物がちゃんとそこにいるという状態になっていますね。採れる卵もおいしいしですしね。
生活の中心に卵が

荒間:
おいしさを目標に作っているという部分が良くも悪くもなくて、餌の材料の選び方も、地域から出るビールやワインの廃棄物や、等級外の麦・大豆をどう活用するかという点に重きを置いています。
ただ、私たちの卵を描くためには、餌だけとか、鶏だけ、卵だけに着目するのではなくて。みんなで生活していて過ごす時間、その中心に「そういえば卵あったね」というくらいの感覚があります。
伊藤:
それは先ほど荒間が言った「管理的になっていない」ということとつながると思うんですが、うちは福祉施設としてはちょっと珍しい方だと思うんですよね。
他の施設だと、「この時間は喋っちゃいけません」とか「この線から出てはいけません」とか、管理的になってしまう場面が多いと聞きます。 でも、僕たちは障がいのある人たちとそういう関係性を作るのは好きじゃないです。それは外で作業しているというのもありますし、そもそも上下関係がそれほどしっかりしていないんです。障がいのある人と社員の線引きも。
先日も、障がいのあるスタッフから僕の携帯に「そっちの方に俺の水筒忘れてないか?」と電話がかかってきまして。そんな電話が代表にかかってくるんですね、と笑い話になりました。
やりたい気持ちが大事

伊藤:
多くの人にとって、仕事はやっぱりストレスのかかるものですし、できればやりたくないという気持ちがあると思うんですが、僕が極力持っていたいのは、「あなたがこの仕事をやりたいと言って今ここにいるんですよね」ということです。
もちろん仕事の中には、楽しいことも大変なこともあると思うのですが、それらは独立しているわけではなくて、繋がっていることだと思っています。
福祉の仕事は、サービスを受ける側からしたら「やりたくない人」から受けたくないと思うんですよ。
例えば、「本当はこの人の介護なんてしたくないし、面倒くさいし、やりたくないけど仕事だから仕方なくやるか」なんていうのは、前提から間違ってしまっていますよね。 やっぱり、弱い立場にある人たちにどう向き合っていくかという時に、やりたくないのであればやらない方が良いなと思います。
荒間:
私は、屠殺をやっていて結構精神的にきついなと思うこともあるんですが、でも、多分みんながいるからやれているんだろうなと思っています。みんながいると感じさせてくれる職場という意味では、居心地が良いんじゃないかなと思います。